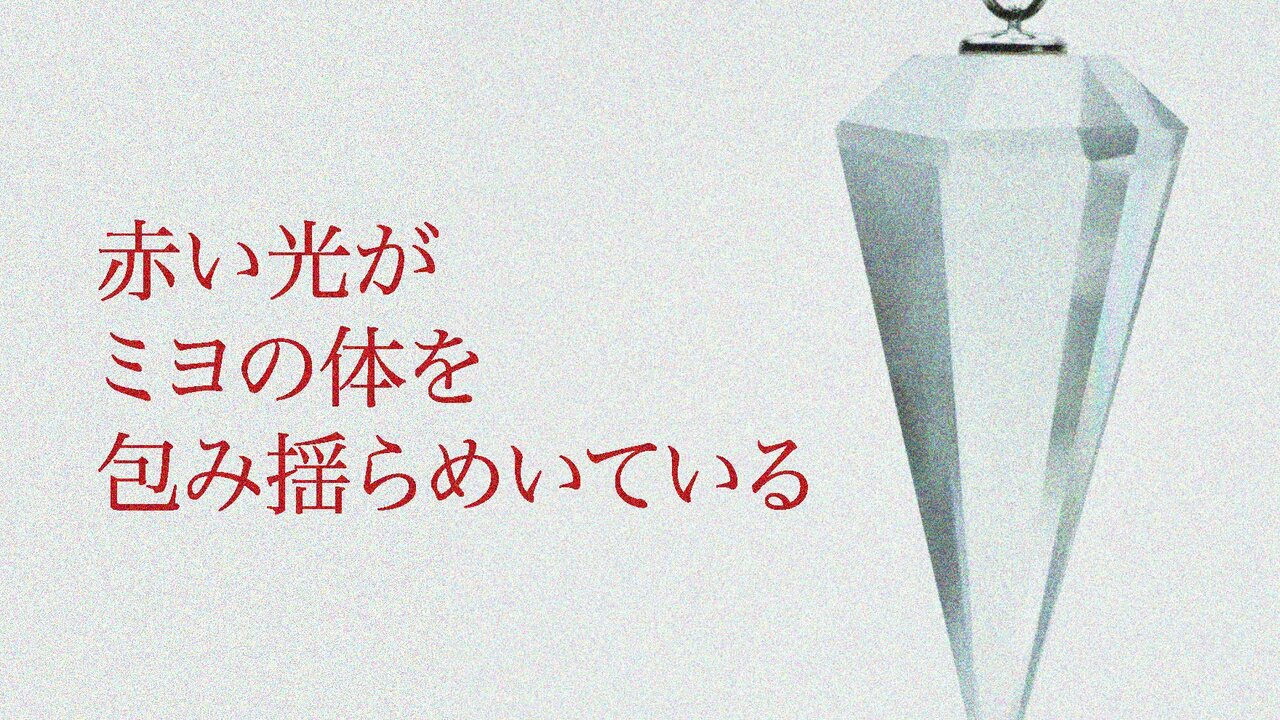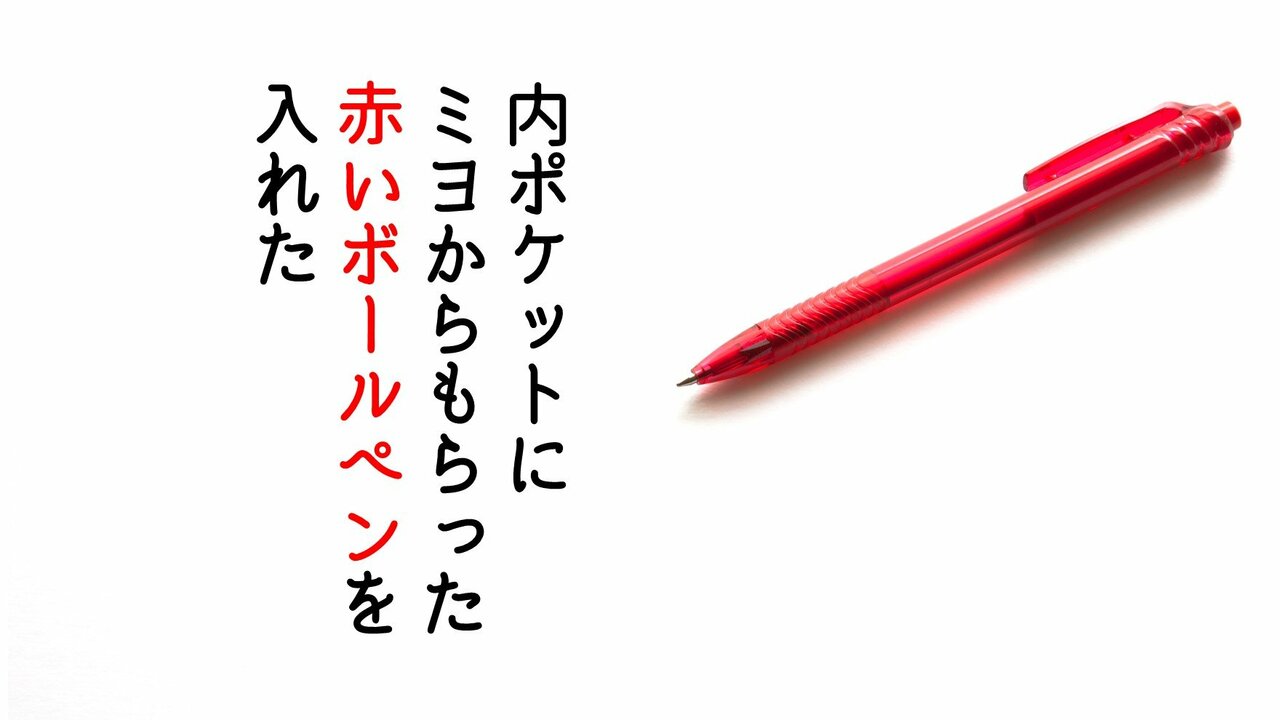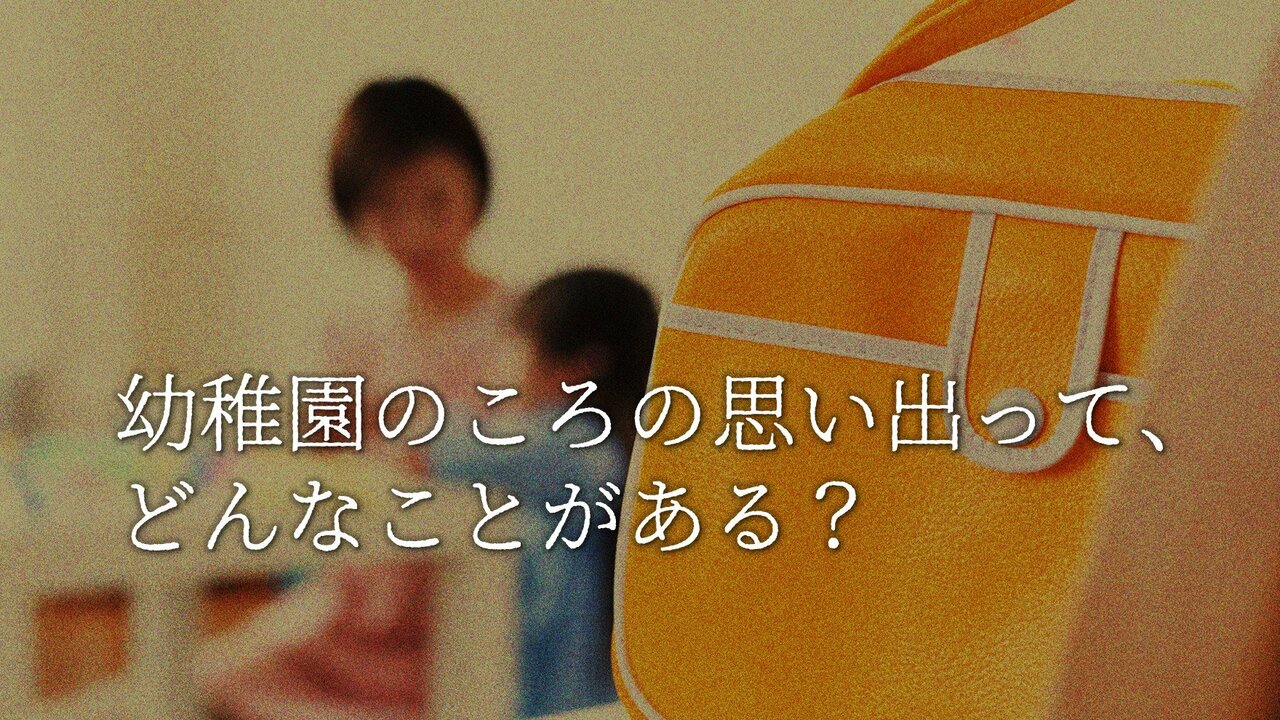第二章 希望
翌日、達也は結花といっしょに、みそぎ学園高校の文化祭に来ていた。隣では結花が一人、はしゃいでいる。
「すごい人だね! 説明会の時の倍はいるんじゃない?」
一般公開のこの日は、在校生だけでなく生徒の家族や卒業生、達也や結花のような、みそぎ学園高校を志望している受験生、さらには近隣住民など、人、人、人であふれかえっていた。結花の携帯電話が鳴った。どうやら実花からの電話のようだ。
「わかった、うん、またあとでね」
実花との通話が終わり、結花は目を輝かせた。
「お姉ちゃんが、二年B組で手作りの携帯アクセサリーを売っているからおいでだって。達也くんはどうする?」
「僕は塾の友だちが来ているはずだから、まずはその人を探してみる。会えたらすぐに行くよ」
「わかった。じゃ、私の携帯に連絡してね」
結花は、姉のいる二年B組へ、人混みをかき分けながら走っていった。
「さてと」
携帯を確認すると、いつの間にかメールが一通届いていた。
『達也くん、こんにちは。今日は来てくれてますか? なんだかすごい人の数ね。校舎の裏手側にグラウンドがあるの。そこは全然人がいないと思うから、そっちで待ち合わせをしませんか? 連絡ください』
達也がグラウンドに行くと、ダウジングをしているミヨの姿があった。ぼんやりと遠くを見つめている。達也には気づいていない様子だ。
声をかけようとして、達也は息をのんだ。松本駅で見た時と同様、赤い光がミヨの体を包み揺らめいている。達也はなぜか声を発することができない。
冷や汗が背筋を伝う。ドクン。乱れる呼吸を整えようとすると、ミヨの口がゆっくりと開き何かをつぶやきはじめた。
ロッドはグラウンドの中央をずっと指し示している。赤い光が深紅へと徐々に変化していく。心拍数が異常な数を刻みはじめる。ミヨのつぶやく言葉に、L字のダウジングロッドが反応する。
達也は、いつの間にか体の自由を奪われていた。奇妙に揺れ動くダウジングロッドに全神経を集中させた次の瞬間、ロッドの先が勢いよく達也を指し示した。
達也が思わず視界のすべてを閉じてしまった時、自分を呼ぶ声が聞こえた。振り返ると、ミヨが達也を見つめていた。
「先……輩?」
「来てくれたのね」
達也から視線をそらすことなくミヨが見つめている。先ほどの状態が整理できない達也の隣で、ミヨが澄んだ青空を見上げた。