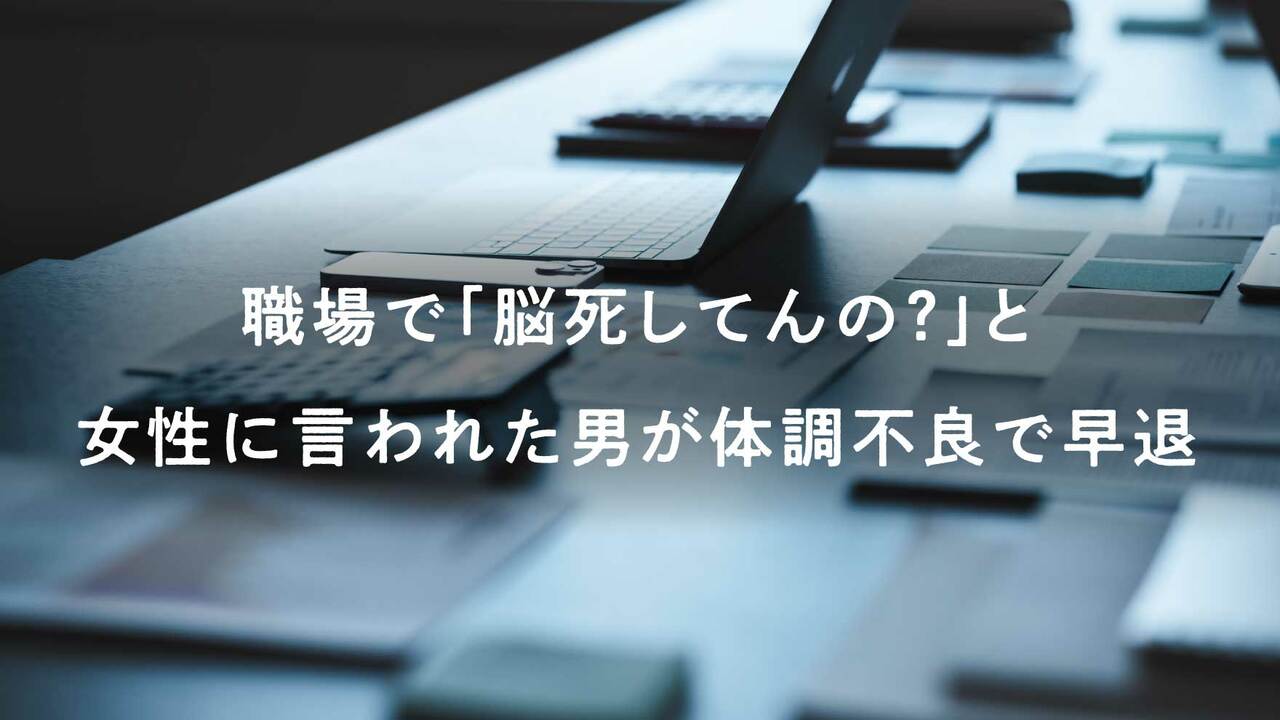父は九州でトップに入る大企業に勤めるサラリーマン。肩幅は大きく筋肉質で、白髪混じりの髪に、べっこう飴色の眼鏡をかけて眉間にはいつもシワが寄っている。スーツを着ている姿は威厳があった。
食後の家族団欒のひと時でさえ、バラエティ番組やドラマを観ることを許さず、家の中は殺伐とした空気が流れていた。口を開けば「勉強しろ」の一点ばり。
そんな父に対して、教育に厳しいだけで、父自身を悪い人だなんて思ったことは一度もなかった。
それに娘の私にはとても甘い顔をする一面も持ち合わせている。おもちゃ屋やデパートで私が何かに興味を示すと、母の反対を押し切ってなんでも買い与え、兄に比べ私だけまったく異なる扱いを受けていた。兄のことはお構いなしの私は素直に父に甘えた。気分屋だとしても優しい時の父が好きだった。
物心ついた頃から水泳、書道、ピアノを習っていたけれど、私はどれも好きではなかった。経験させてもらったことは感謝しているが、自主的に始めた習い事は一つもない。水泳と書道が特に嫌いで、練習をさぼってばかりで怒られることが多く、ピアノに関しては辞めることが決定した時、心の中で飛び跳ねた。バタフライまで泳げるようになった水泳にいたっては、上達すればするほど過呼吸になった。実際は過呼吸か分からないが、とにかく息をするのが苦しくなる。
母が迎えに来ると、すぐに一緒に帰ってしまうほど知らない場所も新しい環境も苦手で、一人では何もしたくなかったし、どこにも行きたくなかった。私は家で母と過ごす毎日を夢みていたのだ。
兄に次いで中学受験の勉強が始まる。
そのタイミングで習い事はすべて辞めた。塾の先生達は「成績の良い翔ちゃんの妹」として可愛がってくれた。兄の成績が良かった背景には父の「厳しい教育」がある。それは私に対するものとは比べられないほどに酷かった。
兄の難関中学への合格はとても喜んでいたが、入学したあとも一日にどのくらい勉強をしたのか、勉強量をチェックする。時間など一切関係なくすべて父のタイミングだったため、確認作業は深夜二時になることもあった。