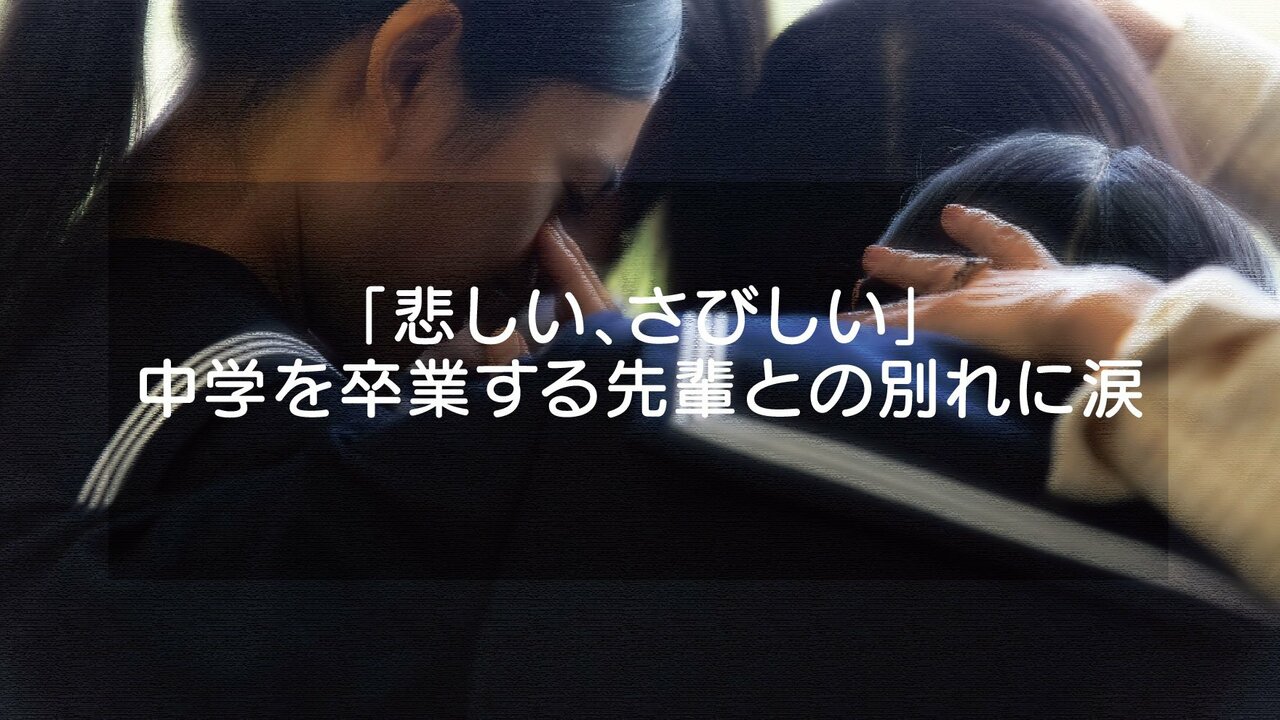マオは、フットワークの良さをここぞとばかりに発揮して、ちゃんと先輩情報をリサーチしてきた。それで先輩が、バレーボール部の中心選手でもあり、だれもが信頼し一目置く存在なのだということも知った。
会議に出はじめたころは、自分はあくまで委員長の代理だという意識もあり、”どうしてこの学校って、月に二回もこんな会議があるの?”と不満も感じていた。けれど、先輩がいてくれると思うと、そんな不満も少しは解消された。
ただ、先輩だのみの議事進行がパターン化してくると、だんだん「この人にまかせとけばいいや」という、ぬるま湯みたいな依存体質が会議の中に生まれてくる。
わたしもマオも、そのぬるま湯に肩まで浸かりきって、気持ちよくうとうとしている側の人間だった。たよれる上原先輩にすっかり寄りかかっていたのだ。
そんなある日―いつものように、先輩の巧みな裁きで淡々と議事は進み、わたしは、もうほとんどそれに関心をはらわず、マオとのおしゃべりにばかり身を入れていた。
会議が終わり、わたしたちは、散っていくほかの生徒に続いて腰をあげた。
すると突然、「ねえ、そこのきみたち」という声が背中にかかった。振り向くと、びっくりするくらいすぐそばに先輩が立っていた。
思わず顔を見あわせたわたしとマオを、先輩は、正面からじっと見つめた。
「今日、きみたちがここにきた理由はなにかな」
「え……」
「わたしは、この会議で、べつに目立っていい子ぶろうとしてるわけじゃないんだよね。ほんと言えば、黙っておとなしくしてたいほうなんだよ」
それは、わたしにとって、とても意外な言葉だった。
「それでもね、この会議にくると、やっぱりなにか言わなきゃいけないって、そう思っちゃう。それって、どうしてだと思う?」
「それは……」と言ったきり、答えを見つけられずにわたしは黙った。
「そんな、真剣に考えるほどすごい理由があるわけじゃないよ」
考えこんでいるわたしを見て、先輩は笑った。
「ここがわたしの学校で、ここが大好きだから。この学校を少しでも気持ちのいい、楽しいところにしたい。この会議は、そのためにみんなが集まって、思いを言葉にする場所だって思うから。ただ、それだけ」
わたしは、はっとして、胸の前で手をぎゅっと握りしめた。
「今度は、きみたちにもこの学校のこと、話してもらえるとうれしいよ」
先輩は、にっこり笑って部屋を出ていった。残されたわたしは、自分自身に対する恥ずかしさでいっぱいだった。マオもきっと、おんなじ気持ちだったと思う。
「あの……もう部屋、閉めるけどいい?」
迷惑そうな顔をした生徒会役員にそう言われるまで、わたしたちは、先生にしかられて「立ってなさい」と言われた小学生みたいに、その場でしょんぼりとうなだれていた。
「わたしもこの学校が大好きです!」そう胸を張って言える生徒になりたい―そんなささやかな目標が、そのときわたしの中に生まれた。そして、それからの会議でわたしとマオは、おずおずとではあるけれど、自分たちの意見を発言するようになった。