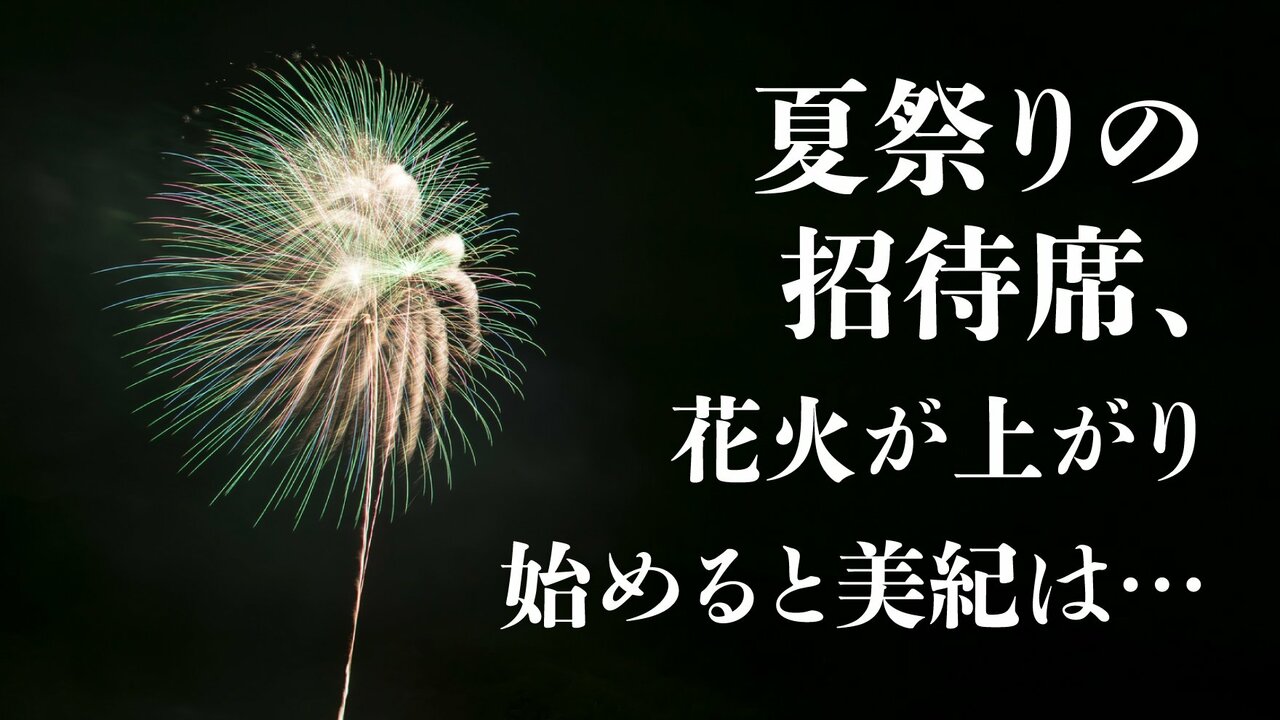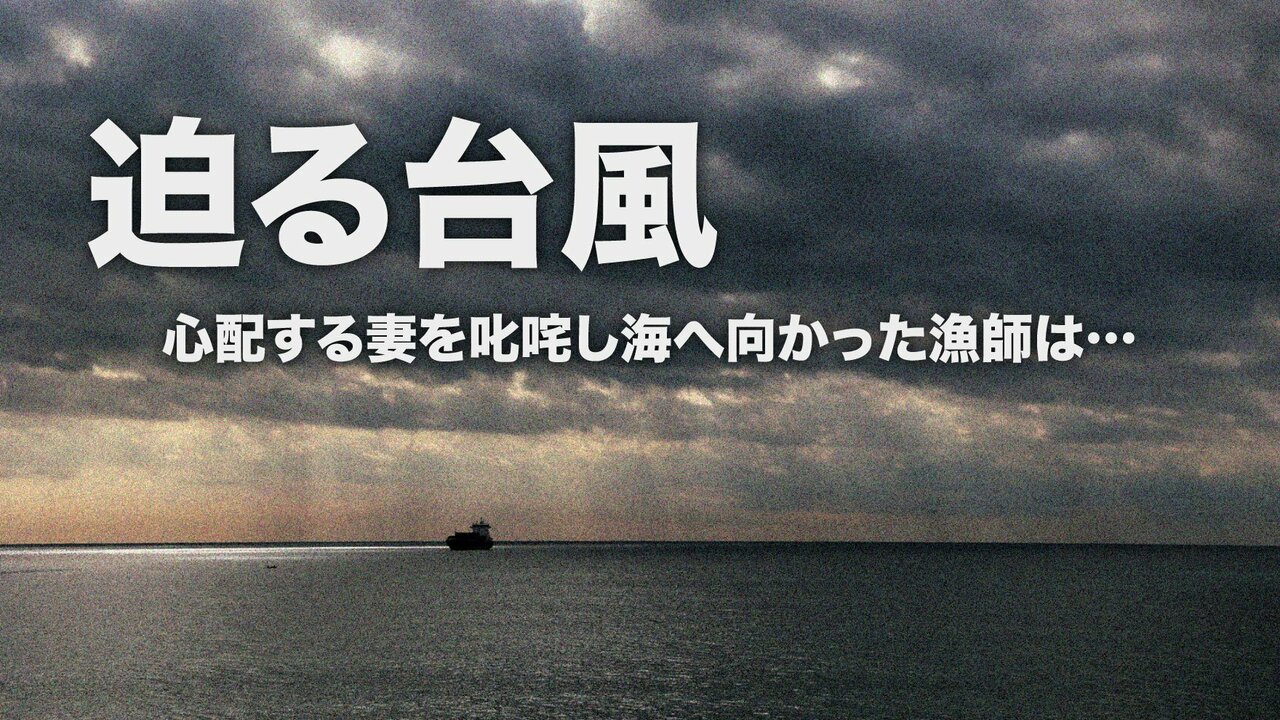夏祭り
帰りの車が橋に差し掛かったときだった。
「ママ、行きにも気になっていたのですが、橋の向こうに咲いているあの黄色い花は何という花ですか?」
そう言って奈美は黄色い花を沢山咲かせた川辺の木を指差した。
「ああ、あの花? 浜朴。地元では浜椿と呼ばれているの。ハイビスカスの仲間らしいわよ。初めて?」
美紀は奈美が指差す方をチラリと見てそう答えた。
「ええ、初めて見ます。綺麗な花ですね」
「少し潮気のある所に好んで生えるのよ。昔はここら辺りにも沢山あったけど、護岸工事やら河川改修やらで減ってしまったの。花は次から次へと沢山咲くけど、一つの花は一日しか持たない儚い一日花なのよ」
美紀はそう説明したが、奈美には強い日の光を受けて今を盛りと咲き誇る花の姿からは、見掛けとは異なり一日しか咲くことのできない儚い運命を持った花のようには見えなかった。
それでも美紀の言った一日花との言葉は浜椿が儚い花であることを奈美に強く印象づけた。
「花の命は短くて苦しきことのみ多かりき。林芙美子の詩だったかしら。女の一生なんて本当にそうだわね」
美紀はそう言って自嘲気味にフンと笑って見せた。
嫁入り先から出戻り、母のスナックを手伝って十年、母が亡くなり経営を引き継いでさらに十年ほどが経った。
酒を注いではグラスを洗い、カラオケを歌っている間に経ってしまった年月だった。儚く咲き終わる浜椿の花でさえ実をつける。
亡くなった母も似たような人生だったが娘という実をつけていた。
自分にはそれが無い。
気がつかなかったが忙しいが単調な日々の中、自分にも煌びやかな花の咲く頃があったのだろうか。自分は一日しか保たない浜椿よりも哀れかもしれない。そんなことをふと思いながら美紀はもう一度川辺の浜椿にチラリと目をやり、浜椿を眺める隣の奈美にも目を遣った。
奈美と漁火で暮らし始めて一月半ほどが経ち、心に深い傷を負った奈美を思い遣る気持ちは、気づかぬうちに美紀の生活に張りをもたらすようになっていた。
何気無い日常の会話や毎朝の「調子はどう?」と短いけれど奈美の体調を気遣う言葉の遣り取りは、美紀に守るべきものの存在があることを意識させ、奈美の好みを考えながら食事を作ることも何となく楽しくなった。美紀は奈美に肉親の情のようなものを感じ始めるようになっていた。