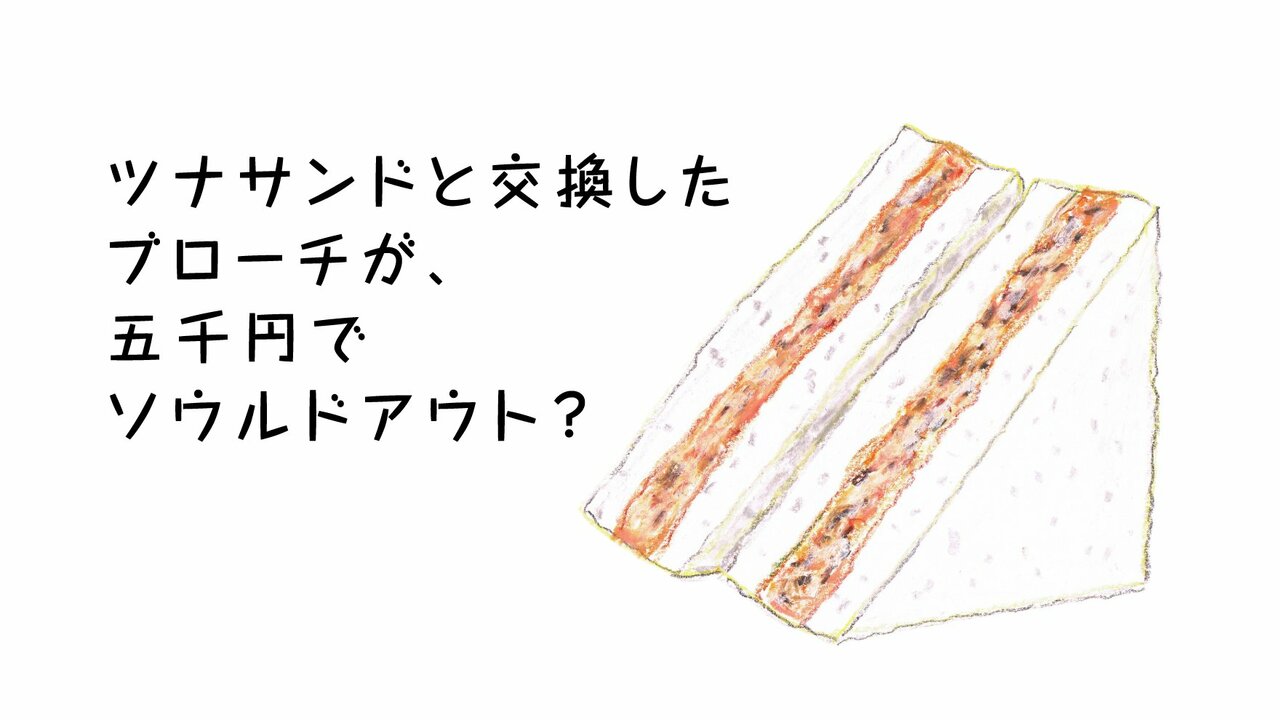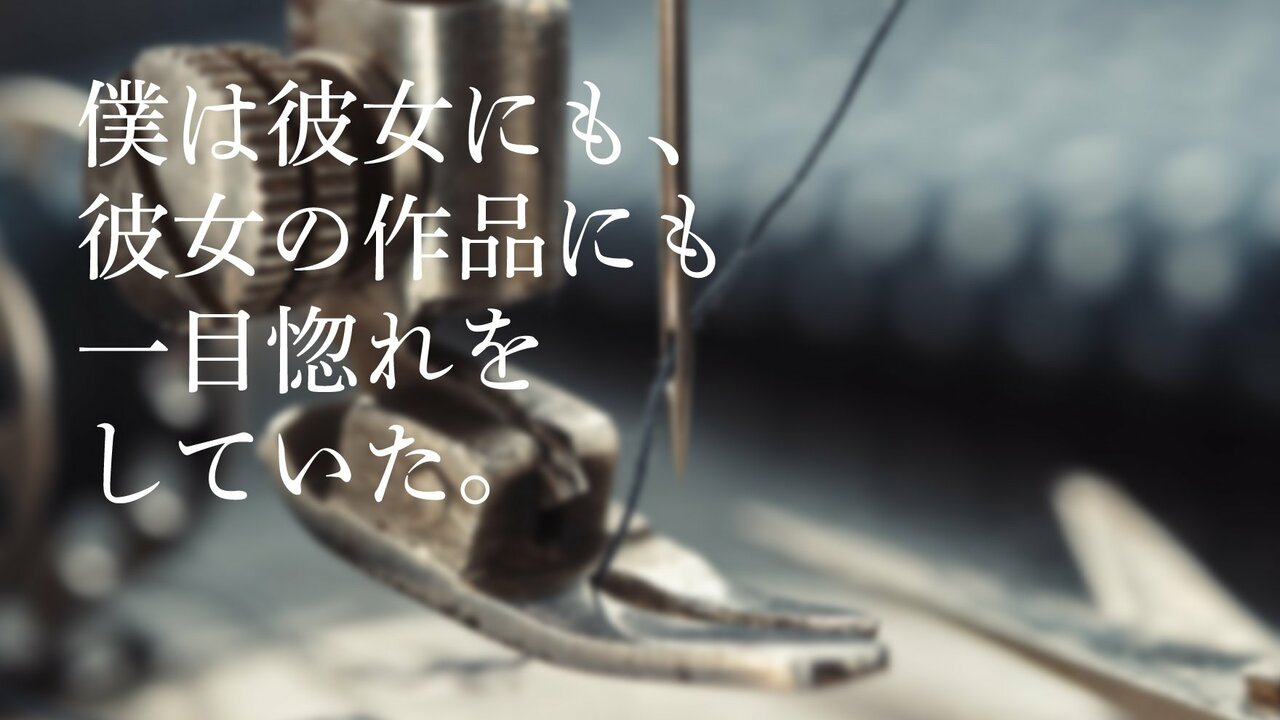選択した厄介
僕は二年制の美術系専門学校に入った。先生も親も心配していたけど成績をねじ伏せるほどの記憶を使った、本物そっくりのリアルな絵を実技試験で披露し、特別枠特待生の称号をもらった。その場にいた監督官の一人に漫画家のアシスタントにならないかと訊かれたけど丁重に断り、煩わしかった家を出たいと両親に言った時は、とても心配されたけど結局学校まで十分のところにワンルームの部屋を借りた。
僕は一人でも生きていける芸術家になりたい。世間的にも簡単じゃない厄介な職業だけど自由な仕事につけるようにと、春休みに入る直前の受験日締め切りギリギリに思い立った。
芸術は自由だ。過去を描くことも記憶を造形するのも。それに僕の体はこの記憶力と想像力を使うと芸術に一番向いている。昔からスポーツも見たら忘れないし真似が出来たけど、好きになれなかったのはチームプレイが苦手だったからだ。個人種目のスポーツもあるけど部活とか、そんな小さな人間関係の世界すら嫌いだった。
あとは単純に、絵やモノづくりが好きだったということが大きい。だからそこに関しては親も反対はしなかった。両親ともにエリートだからこそ分かるのだろう。僕がサラリーマンには向いていないということくらい。
「優!」
芸術家が狭き門だろうと関係ない。僕は僕の作品で人を癒したり興奮させたり感情を動かしたい。入学して三ヶ月、そう思うようになっていた。
今、僕が気に入って作っているのは木彫りのブローチだった。授業とは関係なく、休み時間を利用して曲線の集合体に見える葉の繊維のような細かい模様を彫り込んだデザインで作るのが楽しかった。授業だと必ずテーマやスケジュールに邪魔をされて自由度が少ない作品しか作れないけど、自由時間は自由だ。僕は僕がしたいことを純粋に楽しめた。
「優!」
作品が出来上がるとクラスメイトたちがコンビニのおにぎりやサンドウィッチを持って、交換してほしいと言ってくる。だから僕は作品を作り終わると順番にブローチ、時にはペンダントを交換している。
「上村優!」
「何?」
「お前生まれてからの記憶が全部あるって言う割には自分の名前に反応遅くないか?」
どうやら、また無視してしまっていたらしい。
「ごめん。どうしたの?」
僕の名前は『上村 優』。今まで下の名前で呼ぶのなんて両親くらいだったから、入学して四ヶ月もたつのに下の名前じゃ反応出来ない。しかも僕の下の名前を呼ぶのは隣の席の『花沢 健』ただ一人だった。