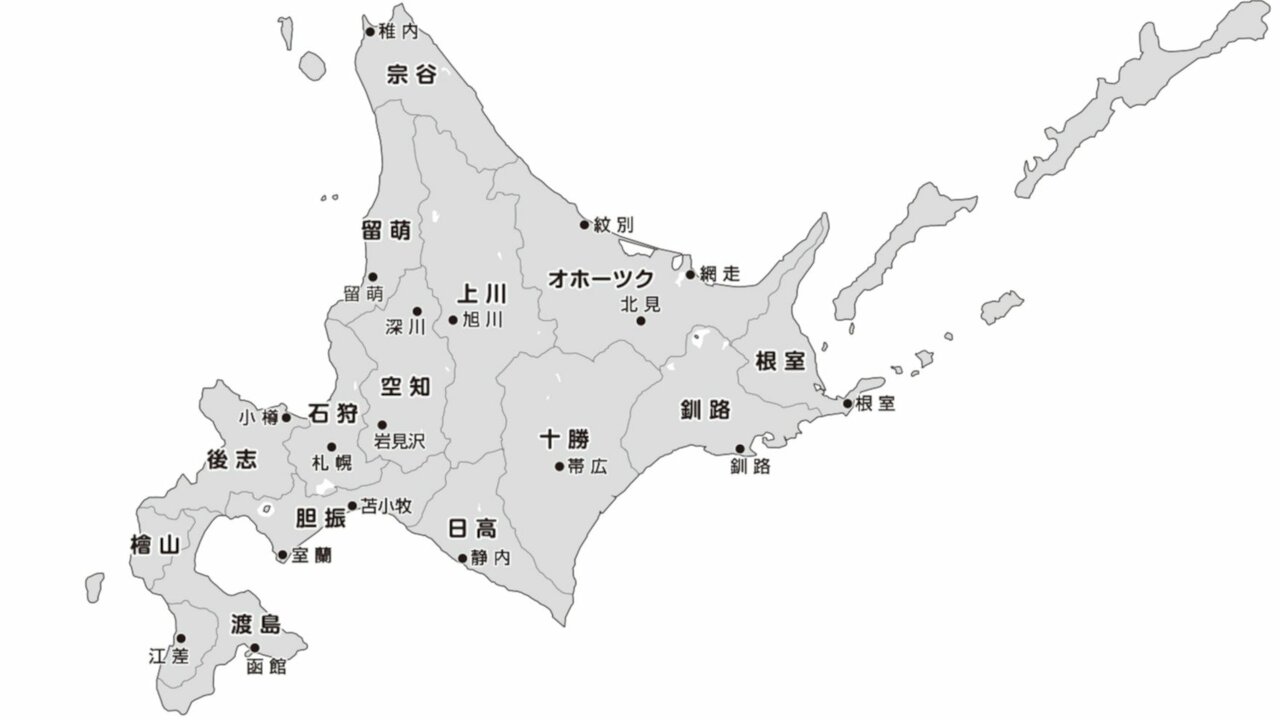第一部 佐伯俊夫
第二章 進展
春子さんは早く私に連絡したかったのか、かなり前のめりな言い方になっていました。
「えっ、本当ですか!」
「もったいぶるわけじゃないけど、電話でもなんだから明日お店に来ない? またオムレツを作ってあげる」
「今すぐ聞きたい気もしますが、他にも話がありそうですね」
「そうなのよ。こういうことって一つ思い出すと芋づる式に出てくるものなのね。あのあとあたしもなんだか気になっちゃって、主人の遺品とか改めて探してみたらいろいろわかったことがあって」
「わかりました。明日が待ち遠しいです。十時頃に伺いますね」
春子さんからの情報に興奮した気持ちにひと呼吸おき、テレビをつけると、いよいよ台風が本州に上陸したとのニュースが飛び込んできました。海沿いの中継に当たっている新人キャスターっぽい男性アナウンサーが着込んでいる雨具が、強風にあおられて踊り狂っている様子がライブで放映されています。
私は庭に面した木製の雨戸を閉めにかかりました。もし雨戸がなかったら、この家の中にまで台風の雨水が容赦なく侵入してくるのは想像にたやすいことでした。
古い雨戸がぎしぎしと音を立てながら、それでも懸命に次第に強まりつつある風雨を遮ってくれています。しかし雨戸をピタリと完全に閉め切ってしまうと嵐が近づく外界の音は遮断され、しんとした静けさが家の中を支配しました。
その静けさは、速度を増して接近する大型台風の前兆であると同時に、明日春子さんから聞く話が呼び込んでくるだろう謎解きの嵐の前触れでもあるようでした。
早めに布団に入ったものの、私はなかなか寝つけませんでした。雑誌の記者だったというその若い男性はいったいどんな風貌をしていたのか。この町にどういう取材をしに訪れたのか。そして《聖月夜》という詩を書き、地元の同人誌に投稿した目的は?
小雨の中で強行したゴルフの疲れが出たのか、宇宙のブラックホールに吸い込まれていくような感覚にとらわれ、いつのまにか私は深い眠りに落ちていました。
目を覚ましたのは翌日の朝七時過ぎです。雨戸を開けてみると、すでに嵐は去っていました。雲の隙間から太陽が顔を出しています。庭には強風でもぎ取られた木々の葉や小枝、どこかから飛んで来たガラクタまでもが吹き寄せられて惨憺(さんたん)たる様相でしたが、草木に残った雨の滴に朝の光が宿り、キラキラと輝いています。