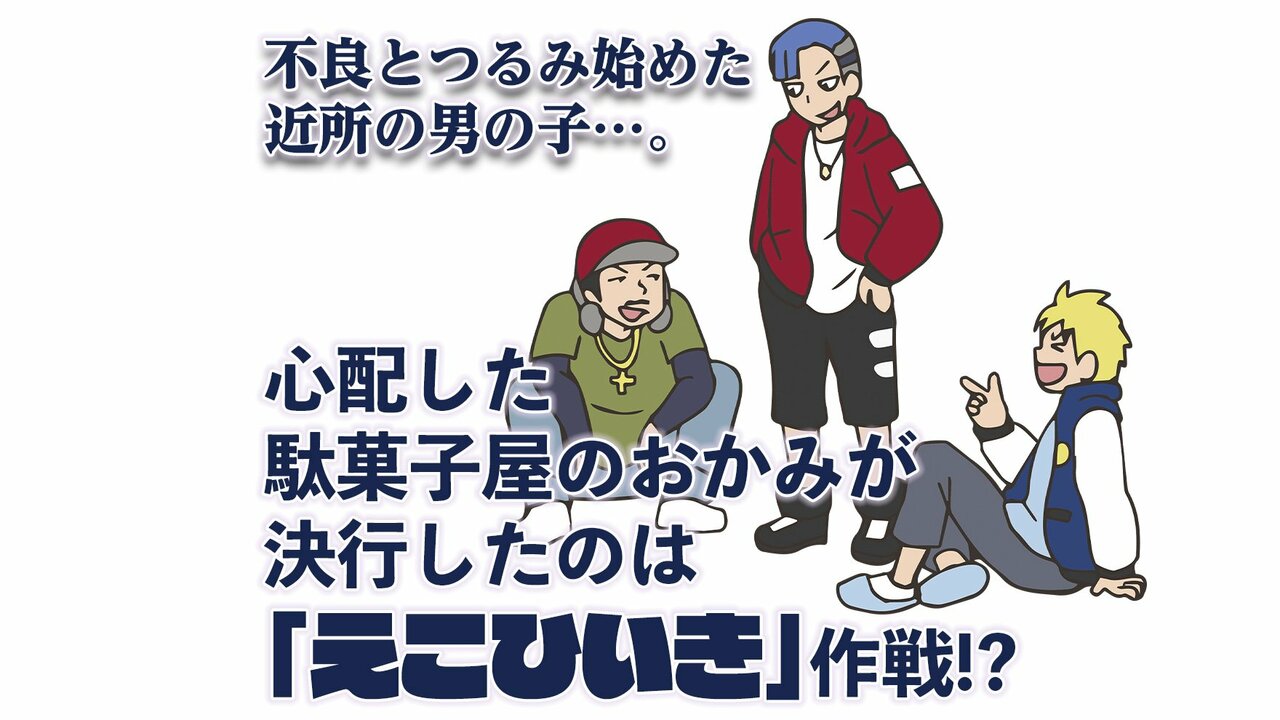また時にはどこまでも続く白い砂浜を裸足で歩く海辺の散歩。そして小高い山のハイキングなど、自然が豊かな場所ばかりを選んで二人は訪れた。
この間涼介は、史を抱きしめることも、一線を超えることもしないでいた。史への溢れるいとおしさと大切に思う気持ちが、それらの行為を封印したのだ。
二か月余りたったころ、涼介は史の両親に婚約の承諾を得るため池田家を訪れていた。涼介は、史に気持ちを確かめたわけではない。まして正式に求婚してはいない。史の気持ちは自分と同じだと思い込んでの行動であった。
「史さんと結婚させてください。高校を卒業するまで待ちます。東京で生活することも考えています」
中学校の教員をしている史の父は、「君は奥さんや子供をこの先一体どうするのか。幸せにしてあげる義務があるはずだろう」と、諭すように言った。承諾が得られないまま、夜の小雨の中を帰っていく涼介。
「ちょっと待って」後を追いかけようとする史に、母が声をかけた。「奥さんも子供さんもいる人は、必ず元のさやに納まるものよ」続けてこうも言った。「同じ女性に悲しい思いをさせていいの?」と。
史ははっと我にかえり、涼介の後を追うことを止めた。父は、「史よ、自分の人生を歩め」そう言って、やさしく肩に手を置いた。史は涼介への気持ちを整理するため、自問自答している。
〈好きだった? 確かに一緒にいて楽しかった〉〈映画やテレビで観るようなあんな激しさは? あったとは思えない〉〈結婚したかった? 今もわからない〉明確な答えが出るはずもなく、小雨の中を帰っていった涼介を追わなかった罪悪感が史の心を満たした。
〈あの頃の私は、恋をするには幼すぎたのかもしれないなあ〉史は時計に目をやりながらふと呟いた。待つ人はまだ来ない。窓の外に目をやると、小雨にけむる街はすでに黄昏が広がろうとしている。秋はまるで一日の終わりをせかすかのようだ。
〈もう少しこのまま待ってみよう。急な要件が入ったのかもしれない〉史は再び罪悪感を持つようになったあの夜からの出来事に心を戻した。