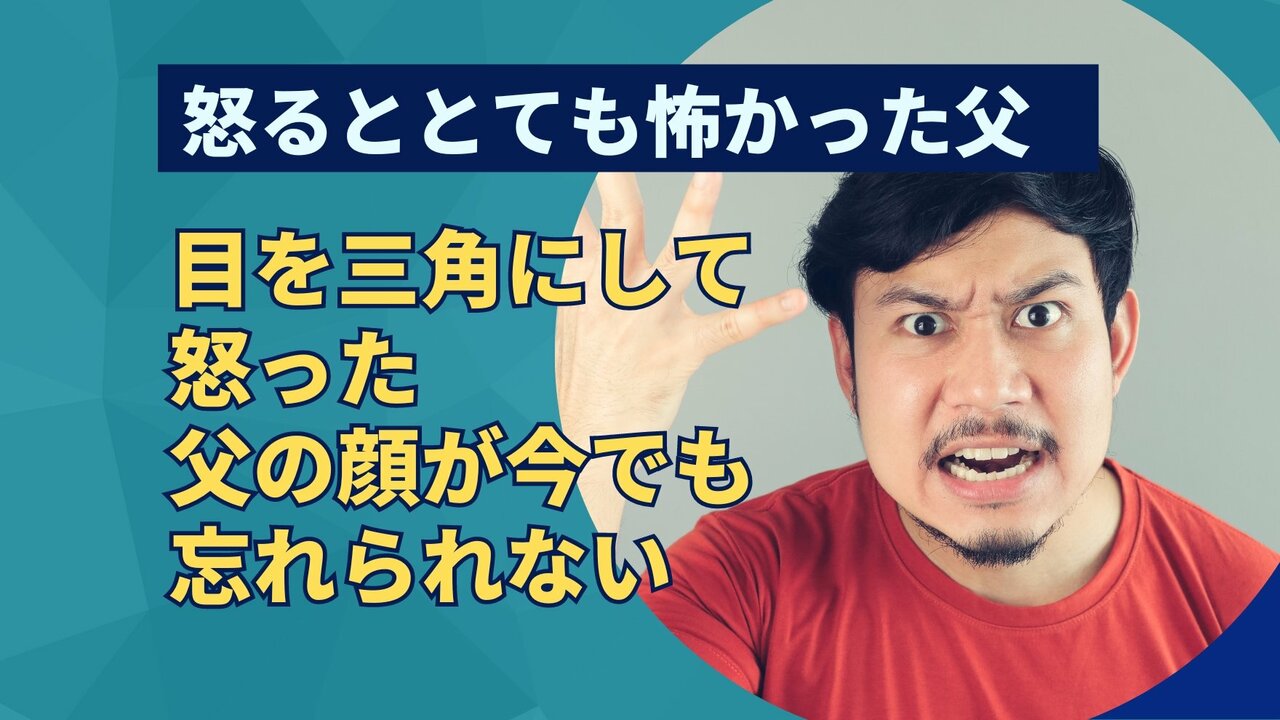【前回の記事を読む】義父が亡くなり3年を過ぎた頃、私の夢に義父が…。「そろそろ墓に入れてくれ」
第2章 家族 ~私を支えてくれた人たち~
朝昼晩の宴会
私が幼い頃の食卓は、今思うと他の家とは明らかに様子が違っていた。
6畳間の部屋に大きな長方形のテーブルが二つくっつけてあり、その周りにびっしりと若い衆がテーブルを囲んでいる。私も姉もその中で一緒に食べる。何人いたかは分からない。朝昼晩がこの光景であった。
父親が町工場を経営して住み込みの従業員がいた。増えてくると近くのアパートへと移り、通いで働いた人もいた。大勢のやんちゃな若者が多いためか父親は怒るととても怖くて、私は父の顔色をよく窺っていた。目を三角にして怒った顔が忘れられない。魚がおかずの時には隣に座る父親が怖かった。私は魚が苦手で手をつけないでいると「食べろ」とご飯茶碗に魚がのせられる。
今思うと食べやすく骨も取って一番美味しいところを入れてくれていた。
当時は心の中で「うわっ、美味しいご飯に魚の味がついちゃう」と思ったが父が怖くて口に出せず、我慢して食べた。お鍋の時もテーブルに一つ一つのっていたと記憶している。食事中は大人たちの話をじっと聞いているだけで面白かった。遠方から上京してくる若者もいて方言が飛び交っていた。
みんなが揃う食卓はにぎやかで、そこで笑いを取ると注目される嬉しさや逆に注目される緊張感も子ども心に学んだ。
食事のマナーでは、父が箸の持ち方や食べ方を注意することもあった。あるおとなしい男の子が(まだ10代ぐらいだったかと)食べる時にくちゃくちゃと音を立てるのだ。
「物を噛む時は口を閉じて、音を立てないんだぞ」と何度も注意を受けていたが、変わる様子はなかった。ある朝のこと、いつもいるはずの人が食卓にいない。
「ちょっと行って起こしてこい」
と父親に言われてアパートに走って起こしに行く。ドアをノックするが返事がないので開けて中に入ると布団の中はからっぽ。