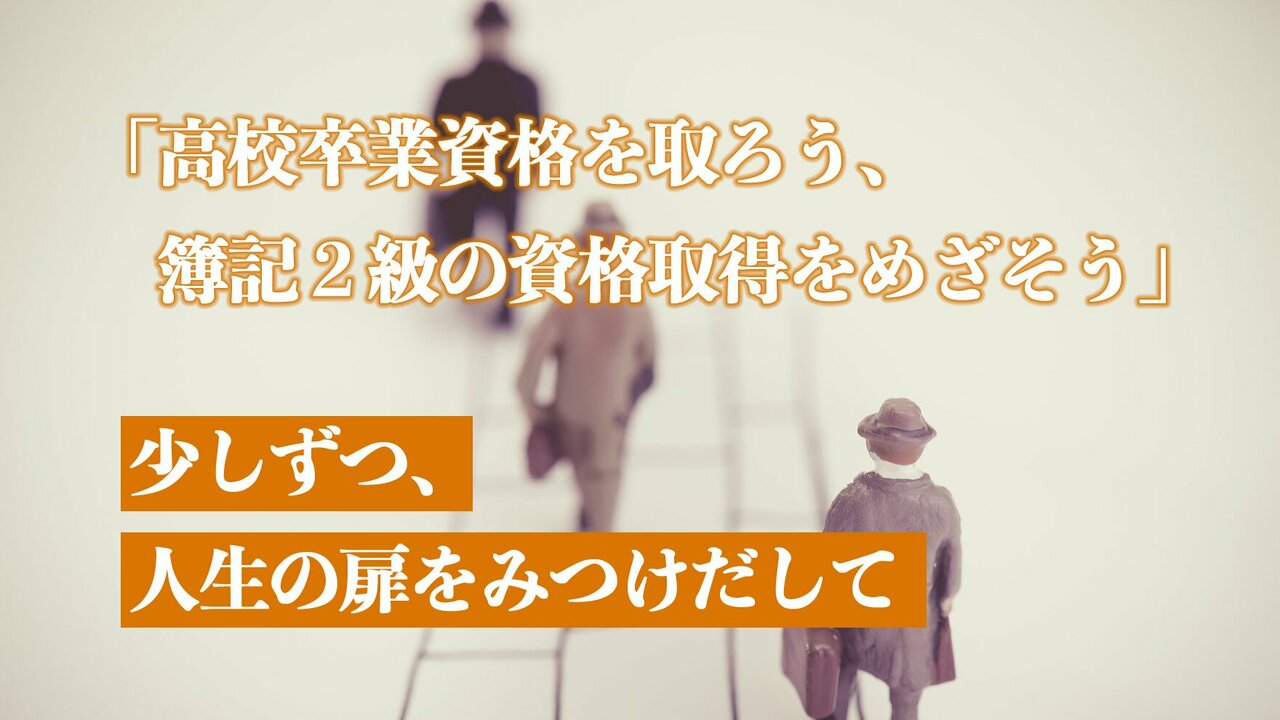第二部 カフェ「MICHI」が誕生してから
■信頼がゆらぐ時
引越しの日、予期せぬことが起きた。同じ官舎に住み、夫の発病までは最も親しくしていた友人親子が見送りに来てくれたのだ。
「ご栄転おめでとう、元気でね」
友人が笑顔で言った。傍で子供達も別れを惜しんでいるように見えた。疎遠になっていた友人親子との久々の時間は、仁美と娘たちにほんの少し明るい気持ちをもたらした。その一方で、仁美の気持ちは複雑であった。友人の夫と仁美の夫は、同じ法務省に勤める、いわば同僚である。この先、同じ職場で働くことになる可能性がなくはない。出世する夫にどのような気持ちを抱いたのか、友人の本当の気持ちをうかがい知ることはできないでいた。
信頼という二文字は、一瞬にして崩れ去ることを仁美は身をもって体験していたからである。一度崩れた関係は、修復することに多大の努力と年月が必要だ。仁美は、友人に対して、その努力を払う価値のある人かどうか、考える気持ちすらすでになくしていたのである。
■すれ違う心
夫の佑輔は、やさしい男性である。しかし、やさしさを伝える術を持ち合わせていなかったのだ。キャリア組として順調に昇進する佑輔は、謝るという振る舞い一つとっても、経験したことがなかったのである。謝るという行為は、部下からのものであり、自分には必要ないと思い込んでいた。
家庭において、素直に謝ることができていたら、ここまで冷え切った関係になることはなかったはずである。妻に、入院中のあのベンチでの行動を、きちんと説明できていたら、そして素直に謝っていればよかったのだが、それが上手く伝えられなかった。
そればかりではない。重要なことを、妻に伝えていなかった。佑輔は、単なる身勝手な出世欲が強いだけの男ではなかった。自分が出世することが、家族を幸せにできる最大のことだと思い込んでいたのだ。
それにも増して悔やまれるのは、妻の苦悩と向き合わなかったことである。佑輔は、家族が冷ややかな関係に陥ったことを悔やんでいた。何度か、妻と話し合うことを望んだが、心が通うことはなかった。仁美は、すでに離婚届を用意していたのだ。佑輔は、気持ちとは裏腹に、離婚を承諾するのだった。