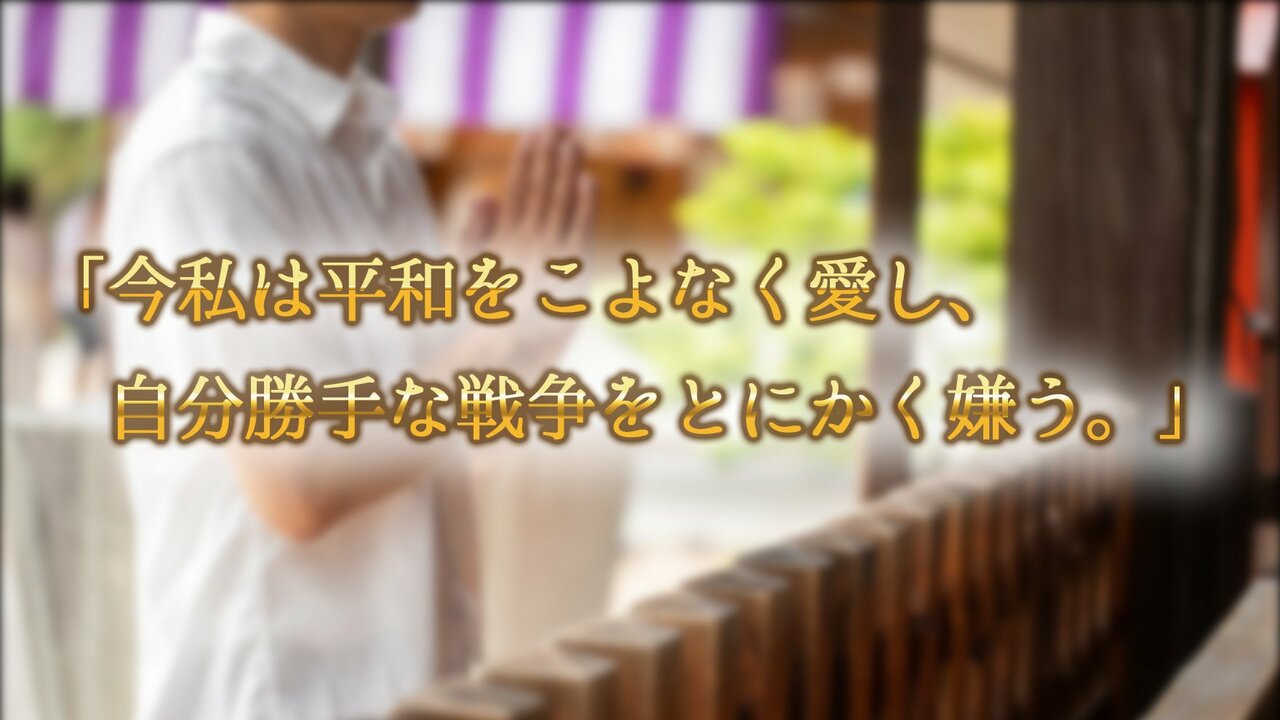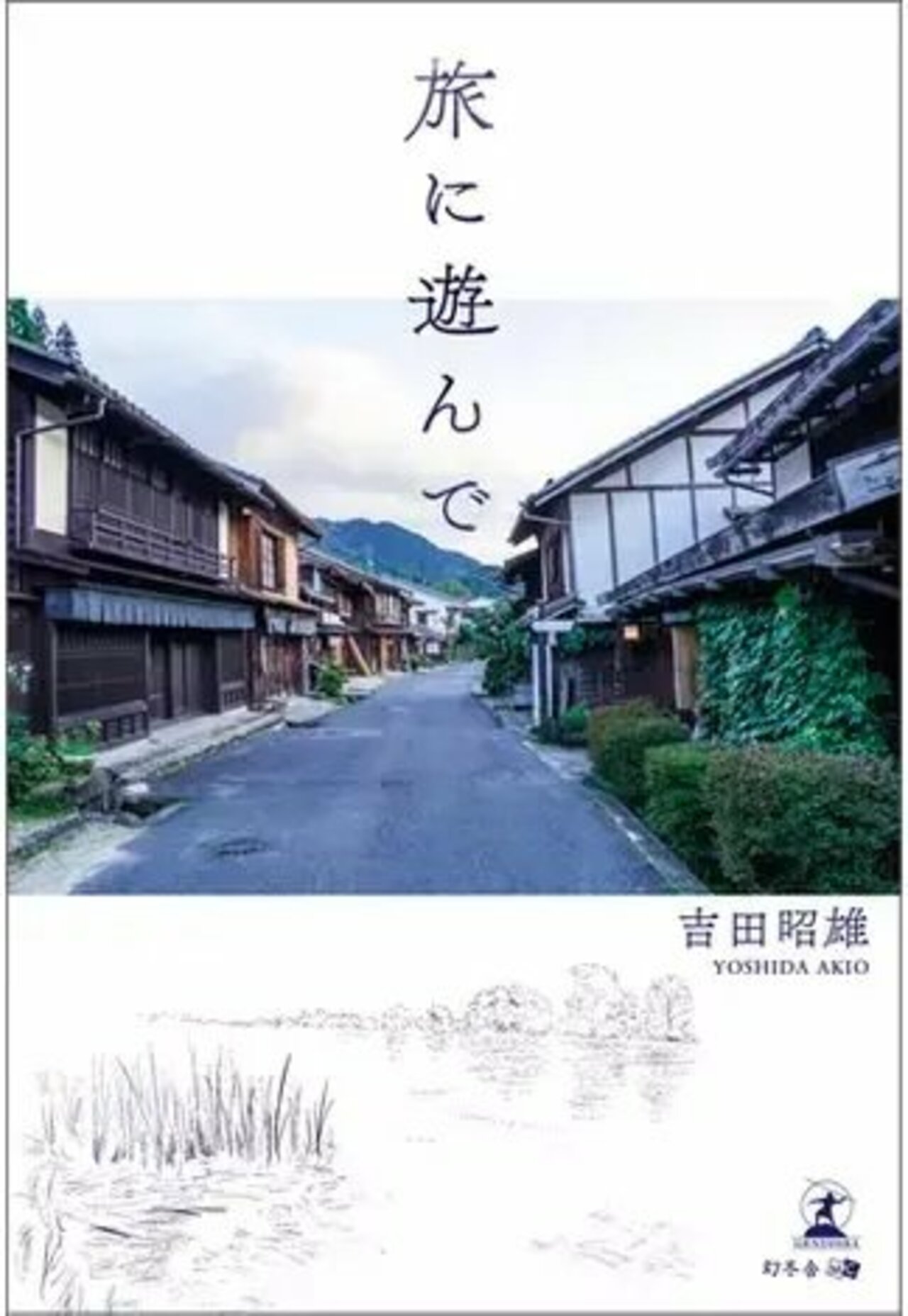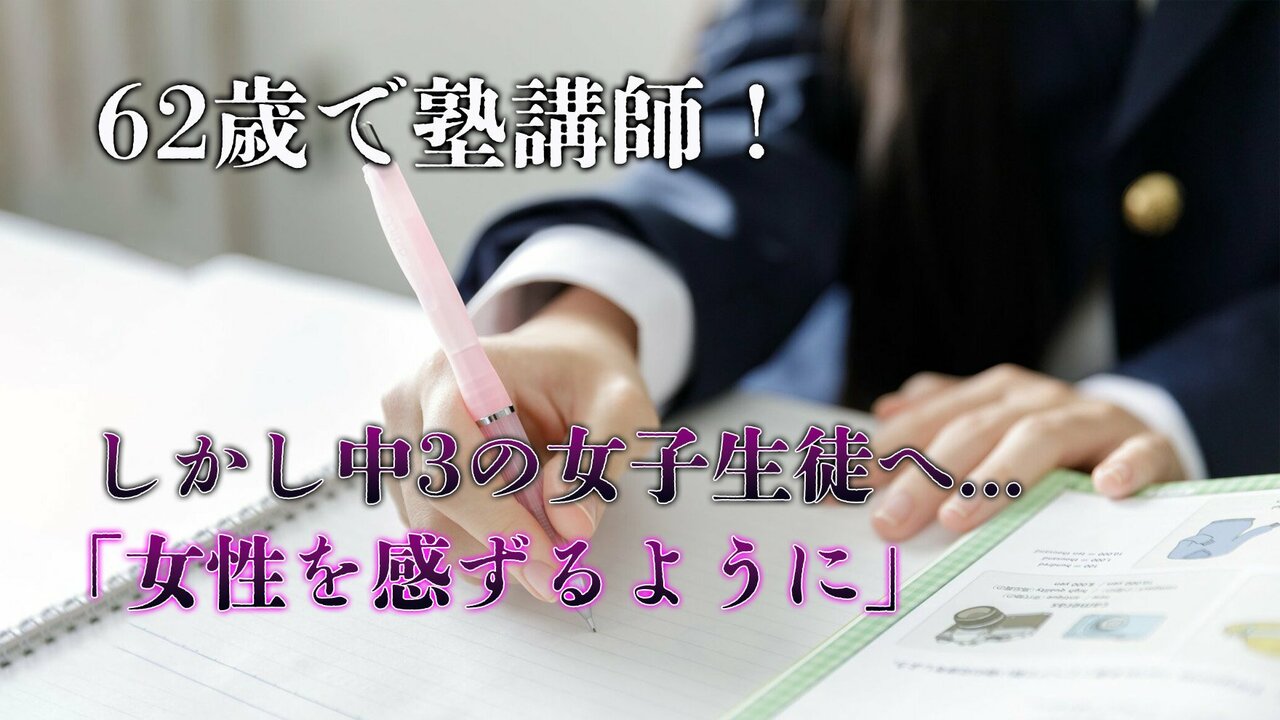第五章 読書
思い出に残る本との出会い
偶然にもこの隊は合唱という武器を持っていた。私も男声コーラスを経験していたからその良さは十分理解できる。熱帯雨林の雨にも暑さにも、また危機到来にも合唱とともに地元ビルマの人々と和し、イギリス軍との交戦の窮地も乗り越えていったのだ。更に敵軍視察や、終戦を迎えた時、まだ抵抗する別部隊の説得工作は涙するものがあった。
文章の上手いのは水島上等兵が生死がわからず、隊長ほか全員が、我が事のように思いやるところだ。数ヶ月かかっても姿を現さない水島を、隊長が殊のほか思いやる。そして自分がその役を果たさなかったという後悔の心。こうした部下とのつながりは現代社会では希薄になってしまったように思う。
人間が極限に至った時に本性が出るというが、この隊に水島が所属していたのは幸運だったのだろう。しかし水島は生きていた。ビルマの御坊様となって。ただ隊長は半信半疑。登場人物の心中の揺らぎは、読者を引きつけて止まない。
次の日の朝は、新聞もテレビも何も見ずにひたすら思いにふけった。私は水島ならそのように行動するだろうか、はたまた隊長のような振る舞いが出来るだろうか。とうとう水島は、仲間の疑問に答えた。イギリス兵の葬儀の時、立派な高僧の腕章を巻いて。
ビルマの人々はいずれも水島を尊敬して止まなかった。日本兵ではなくビルマ人として、そしてイギリス兵も彼を敵国日本人と知ってか知らずしてか何の咎めもなく、日常を過ごしていた。最後の水島からの手紙は更に涙を誘う。隊長や同僚への思いやり、日本の家族への思いやりに満ち満ちている。だが水島はあれだけ生きるも死ぬも皆と一緒に、という隊長の言葉を裏切った。脱走兵として汚名を受けてもである。
隊が日本へ帰る日、彼は一人遠くで見守っていた。そして「おーい、水島、一緒に帰ろう」との声かけに対し、得意の堅琴で「仰げば尊し」を演奏し、特に最後終曲のところで、『今こそ別れめ、いざさらば』を数回繰り返したとある。なんと悲劇的な永遠の別れであろう。私の放心状態は一日中続いた。