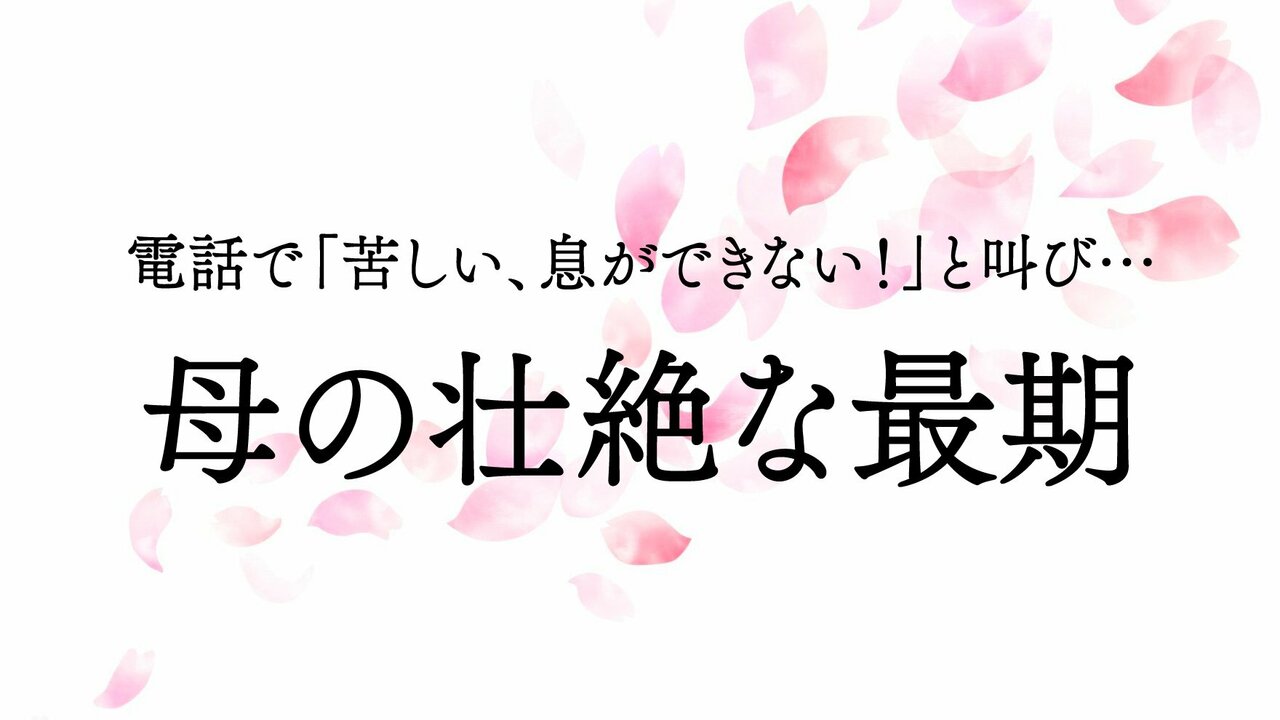外泊から帰院後、彼女のベッドの回りには犬の写真が飾られ、犬の雑誌がテーブルに並んだ。外泊までは彼女は他の入院患者とは一線を画していたが、彼女は犬に興味を示す人には胸襟を開いた。愛犬がコンテストで何回優勝したかを話し出すと、彼女は結核のことも入院のことも頭から消え去ってしまう様子だった。
「犬は私にとって恋人のようなものよ」
彼女はたびたび口にした。
それから月2回の外泊が恒例化し、そのたびに彼女は栄養を摂りに帰るんだと憎まれ口を叩きながら、でも笑顔をふりまきながら病院をあとにした。
遅々としてではあったが病気は治癒に向かっているように思えた。診察のたびに彼女の皮膚が張りと艶を取り戻しつつあるのがわかり、止まっていた生理も再開し体力も戻ってきていた。