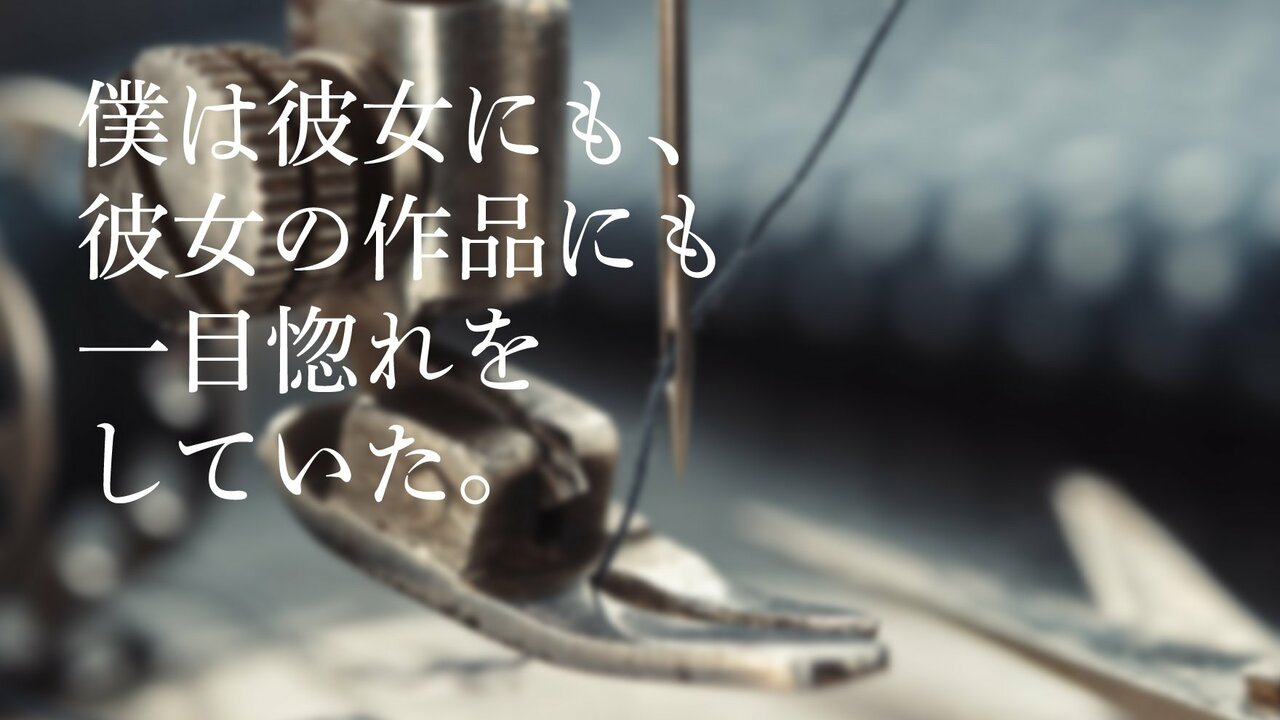僕は彼女にも彼女の作品にも一目惚れをした。なんで彼女の顔や服装が思い出せなかったのかは、今はわからないけど、作らなきゃ何も変わらないのは確かだ。
「そうだね。頭の中に設計図があっても作業に取り掛からなきゃ。完成させてまた城間さんに会ったら何か変わるかもしれないし、作ることに今は専念してみるよ。ありがとう、健ちゃん」
「おう。お前が城間さん忘れちゃっても、城間さんがお前を忘れられないくらい凄いもん作ったらいいじゃん」
健ちゃんはたくましい。答えを導き出すのも早いし、実行に移すのも早い。芸術家も色々いるけど、健ちゃんは野心家で、努力は失敗してからするタイプだ。
間違っても何度でもやり直す根性もある。だけど、一度無理だと思ったら見切りをつけるのも早い。無駄がなく、成功一直線に突っ走っていく。僕の隣にずっといる初めての友達。
「どうして城間さんの顔だけ覚えられないんだろう」
「さぁな」
もうすぐ夏休みに入る。その前にはブローチを完成させて渡したい。一体何に焦っているのだろう。何をこんなに怖がる必要があるのだろう。でも、早く完成させないと駄目だ。
僕が自称思い出の記憶が全部ある奴なら、城間さんの顔も覚えてなきゃ駄目だ。僕の一部が壊されたような、あるいは抜き取られて盗まれたような気分だった。僕は放課後、またガラス工芸学科の作品ギャラリーを徘徊した。
城間さんの作った硝子の海を眺めた。脳内では小波の音がする。胸にまで響く波の音は僕が二歳の時、初めて見た近所にある海の記憶のモノだった。