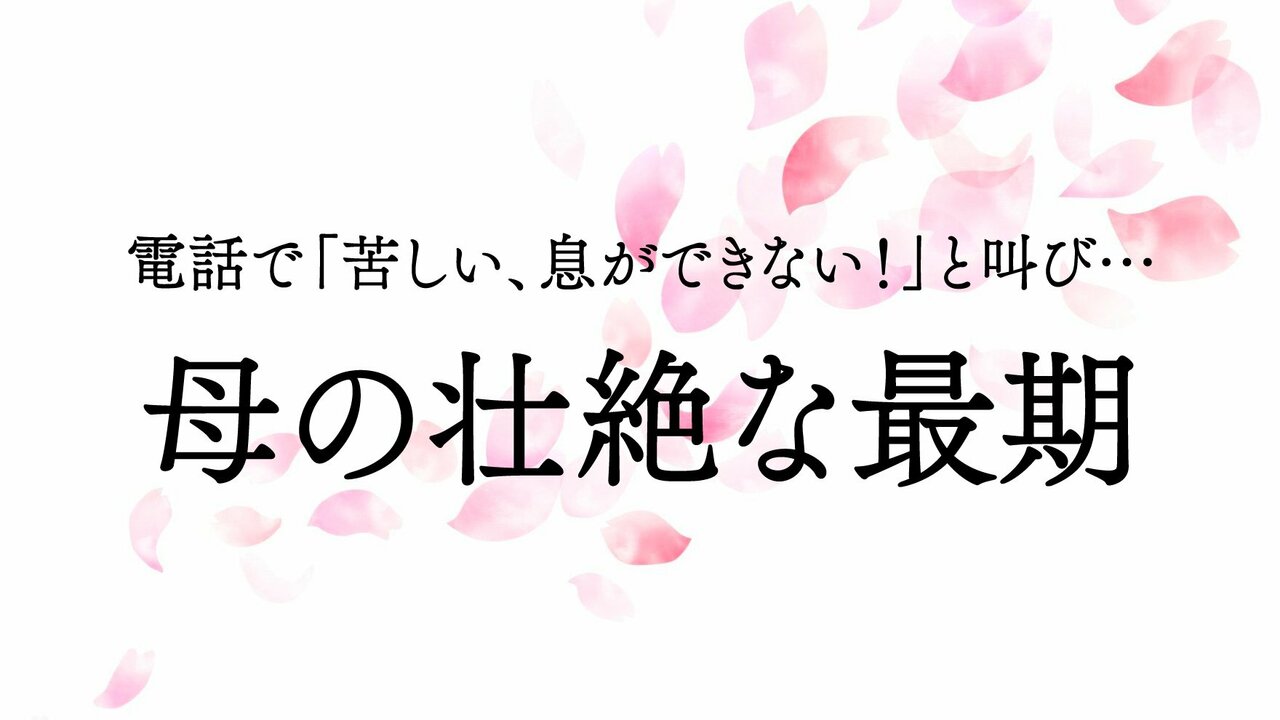「医療者」対「患者」という図式
問診のあと聴診、打診と診察は進み、最後に鎖骨上窩を触診して診察は終了した。
打診はいまや診断学上その位置を失いつつある手技であるが、教授の診察の流れにはいつも入っていた。数十年前の結核全盛時代には打診が胸水を評価するため欠かせない手技であったに違いない。
教授が打ち出す見事な音が患者の右背部では濁った。教授は打診だけで胸水貯留を診断し穿刺し、聴診器一つで空洞の位置を言い当てたという伝説の人だった。
椅子に座り直した教授は患者と妻を見つめ、そしてシャーカステンに目を移し、レントゲン写真を指示棒で差しながら説明を始めた。
二人は息を吞む。
「真ん中が心臓、これが鎖骨、そして肋骨、左右の黒い所が肺です。この下の黒い部分は胃の空気です。左の肺は問題ありませんが、右の肺の真ん中に白い影があります。また横隔膜の切れ込みが失われているので少し水が溜まっているようですね。ほら、ちょうどコップの端で水が上に上がるようにね、わかりますか?」
教授はここまでゆっくり説明し、言葉を止めた。
「はい」
心なしかかすれた声で男が返事し、妻は頷いた。
「おそらくこの影と水が血痰と胸痛の原因と考えられますが、何が起こっているのかは調べてみないとわかりません。外来で検査してもいいのですが、早く診断をつけ、すみやかに必要な治療を行なうために入院しましょうか。とりあえず、今日は血液検査をしておきましょう。それと、もし今痰が出れば採ってください」
教授は言葉を切り、じっと男と妻を見つめ、しばらくの沈黙ののち、夫婦の中に湧き起こったに違いない不安を和らげるように少し優しい声で「何か質問はありますか?」と尋ねた。
やや間を置いて男は乾いた喉を振り絞るように言った。
「結核でしょうか?」
当時はまだ結核を心配する人が多かったが、いつの頃からか主役は肺癌に変わっていた。そしてそれは紹介医が癌を結核と誤診した時代から結核を癌と誤診する時代に移っていった頃と時を同じくしていた。
教授は不安なまなざしを送る男の目を覗き込むようにして威厳と説得力に満ちた声で答えた。
「結核も可能性はありますが、他にもいくつもの可能性がありますので今の時点では何とも言えませんね」
男は特に表情も変えず頷き、教授に一礼し、「わかりました、よろしくお願いします」と言った。
男は教授の意図を察した外来看護師に導かれて、採血室に向かって部屋を出て行った。
男が採血室に入ったことを確認して、教授は部屋を出ようとする妻を手招きした。そして、妻の精神状態を推し量るようにじっと目を見つめ、やがて口を開いた。
「近所の先生から何か聞かれていますか?」
「レントゲンが曇っていると聞いていますが、それ以外は何も」
妻は怪訝そうに答えた。
おそらく教授は妻に悪性の可能性を説明するのは時期尚早と感じ取ったのであろう、「お話ししたように肺に影があって少し水が溜まっています。原因がわからないので入院して調べましょう」と告げるにとどめ、私の方に向き直り入院申し込みをするよう命じた。
一週間後、妻に付き添われて男が来院した。入院は初めてのようで緊張している様子だった。受け持ち看護師が病棟を案内し、入院カルテに記載する事項の問診が済むと彼は6人部屋に向かった。
入院時点ではまだ世間の匂いを残しているが、2~3日も経つと入院患者が板についてくる。これは不思議なもので世間ではいくら地位のある人でも入院してしまうと独特の雰囲気を醸し出してくる。医者、看護師対患者という図式になり、患者はある意味、弱者、被支配者になってしまうのだ。
この時代は医療サイドが情報を独占し、一方的に医者が治療方針を決め、患者は詳しいことがわからないままに従わざるを得なかったゆえだろうか。