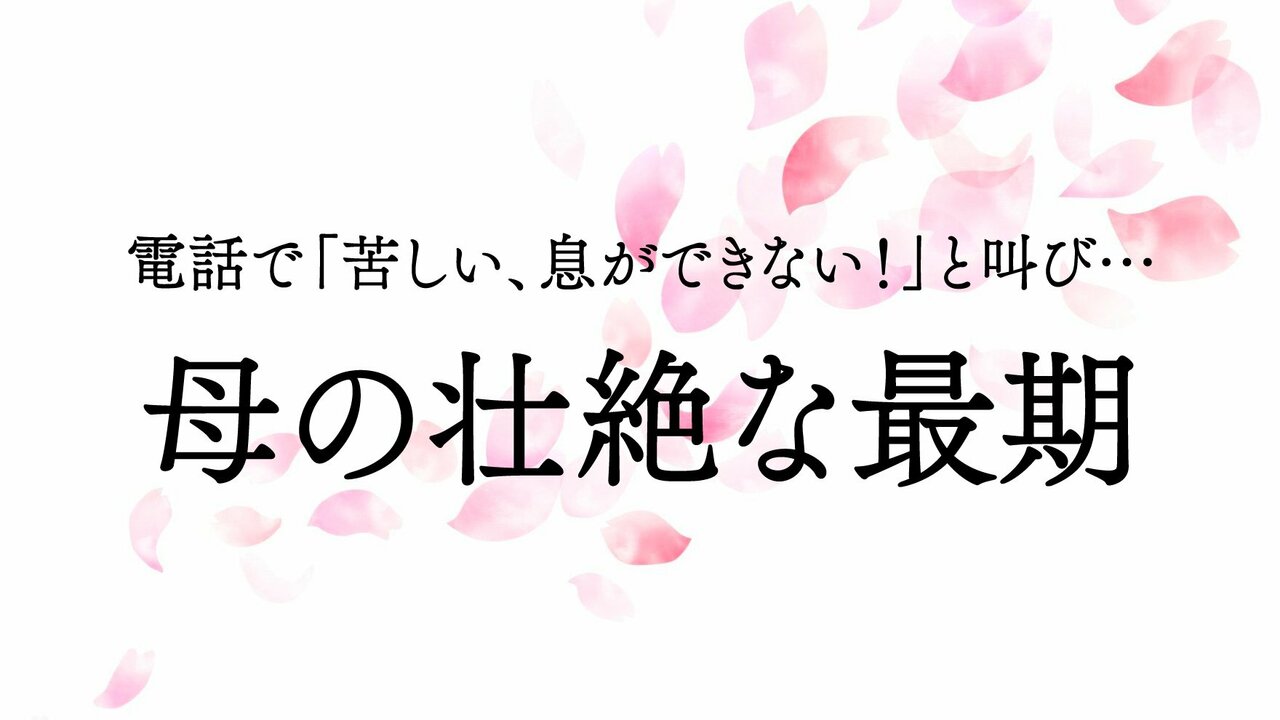生と死の狭間の世界
ちょうど出勤・通学時間で学生、OL、会社員も道を急ぎ、ざわめきと靴の音に混じり、少し離れた私鉄の駅から電車の止まる音、発車のベルの音が聞こえ、当たり前の日常が目の前に展開されている。しかしエレベーターで5階に上がり、病棟のドアをくぐると雰囲気は一変する。エレベーターが運んできた外界の空気は一瞬のうちに病棟の空気に飲み込まれてしまう。ここでは非日常である「病気であること」が当たり前。今までそんなことを思ったことはなかったが、この日はなぜか強く感じた。
ここでは病気や死は生と同様に日常となっている。生と死の世界を行き来し、人の運命を予めいくばくか知り、ある程度変え得る立場にいる我々はいったい何なのだろうか。ひょっとすると現代の我々の方が、いにしえの呪術師よりも呪術師に近いのではないだろうか。術後回復室に向かいながら私はそんなことを考えていた。
看護師が忙しく病棟内を行き来している。深夜勤務の看護師は仕事を片付けようとし、日勤の看護師はその日の仕事の確認と準備に追われている。この時間帯に指示を出すと「きっ」と睨まれるか無視される。廊下をくう胸腔ドレーン(肺と胸壁の間の空間に挿入するチューブ)がつながった箱を持った患者が点滴棒にすがるようにして歩いている。尿をためる袋をぶらさげて歩く人も病衣がはだけている若い女性も気にする様子はない。普段なら恥ずかしいと思うことが、ここでは麻痺してしまっている。
病棟に存在するのは患者と医療関係者の2種に色分けされた人間である。退院の日に患者の普段着の姿を見て違和感を覚えるのはそのためだろう。ここでは個人が失われ、患者として総括され、知らず知らずのうちに自分の中でも、そのような図式ができていることに気がつく。
509号室の前を通り過ぎる。この部屋の今の住人は肺癌の末期で、まもなく死を迎えようとしている。ドア1枚向こうは黄泉の国の暗闇が支配しつつある空間であるのに、なぜこちらはこんなに明るいのだろう。病院は、この世から黄泉の国に通じる道の途上にある乗換駅なのだろうか。光と闇が相半ばする生と死の狭間の世界なのだろうか。