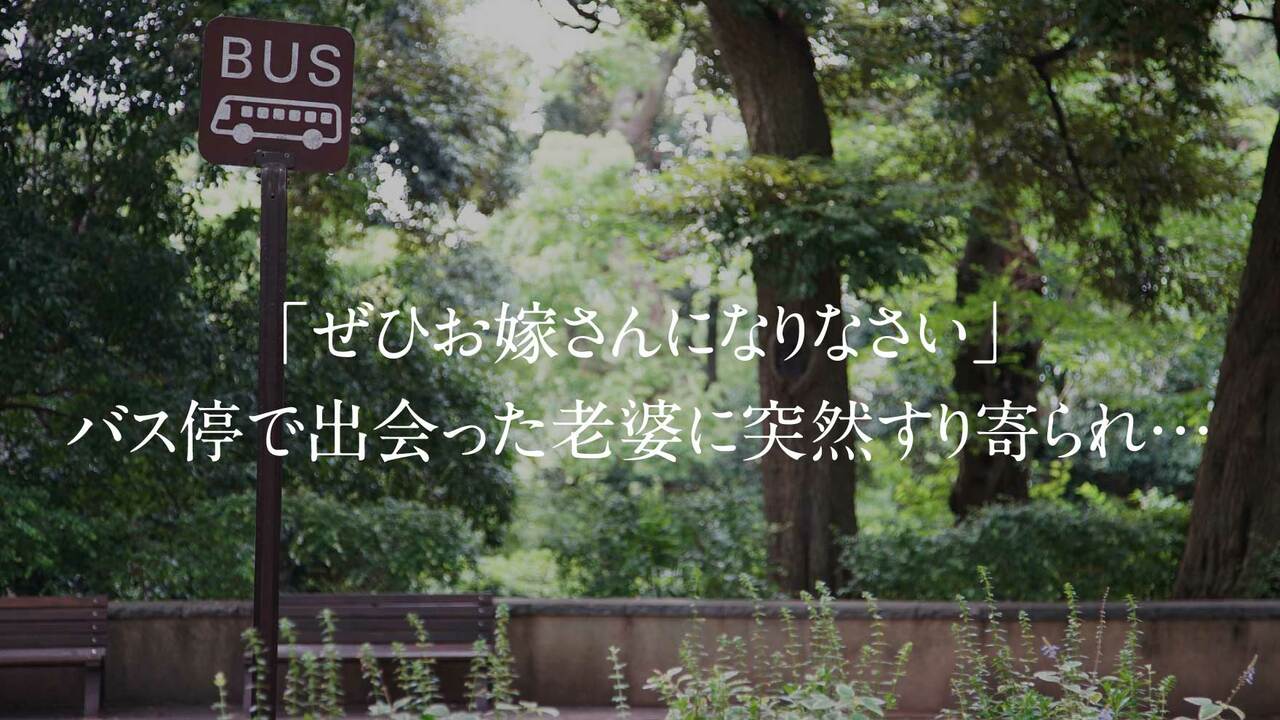当時の私は、鬱病が完治したばかりだった。
膠原病は一生治らないとしても、精神的病からの回復。特に神秘体験は特殊であり、プルースト的禅的体験。「永遠の今」の感覚。小鳥の鳴き声に救われた日々。ある意味、特殊な経験をした人間であり、なぜあのような経験が起ったのか不思議であった。
そんな矢先だった。森有正に出会ったのは。
早速、『森有正エッセー集成』五巻を購入した。『バビロンの流れのほとりにて』は、冒頭から私の心を鷲掴みにした。
「一つの生涯というものは、その過程を営む、生命の稚い日に、すでに、その本質において、残るところなく、露われているのではないだろうか。僕は現在を反省し、また幼年時代を回顧するとき、そう信ぜざるをえない。(中略)そして人はその人自身の死を死ぬことができるだろう。またその時、人は死を恐れない」
「人間が虚しく、あるいは無心になって、それを透き通して自然が見えるようになる時、僕が感じる一つの感情DESOLATIOM(悲しみ)とCONSOLATION(慰め)とが一つのものとして感じられるあの感情、あるいは感覚、と言ったほうが適当なのかもしれないが、そういう感情のことで、それがあたり前のことであるだけに、実に貴いものに思われるのだ。そしてこの感覚は哲学とか宗教とか大袈裟なことである前に、人間の日常の一つ一つの態度の中に出てくるのだ」
心にじんわりと何かが入り込んだ気がした。
最も大切なことは日常であり、理念や知識ではないのだろう。飾らずに実人生を生きること。
知識は誇ったり、所有するものでないことを、私はエーリッヒ・フロムから学んだ。「孤独は孤独であるがゆえに貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのだ」この文章に出会った時、私はほとんど泣き出しそうになっていた。
その日一日中、この言葉から響いてくるもの、この人の宿命的なもの。ひどく悲しくてとても豊かなものにとらわれて、消え去ることはなかった。
そしてさすがリルケの『マルテの手記』を九年もかけて読んだ人だけが持つ、豊かな時間の流れを感じた。それにしても、あんな悲惨な手記を、九年もかけて読まなければいけなかった人を、哀れに思ったりもした。
そこにどんな悲しみに満ちた、苦闘の時間が存在したのだろうか。