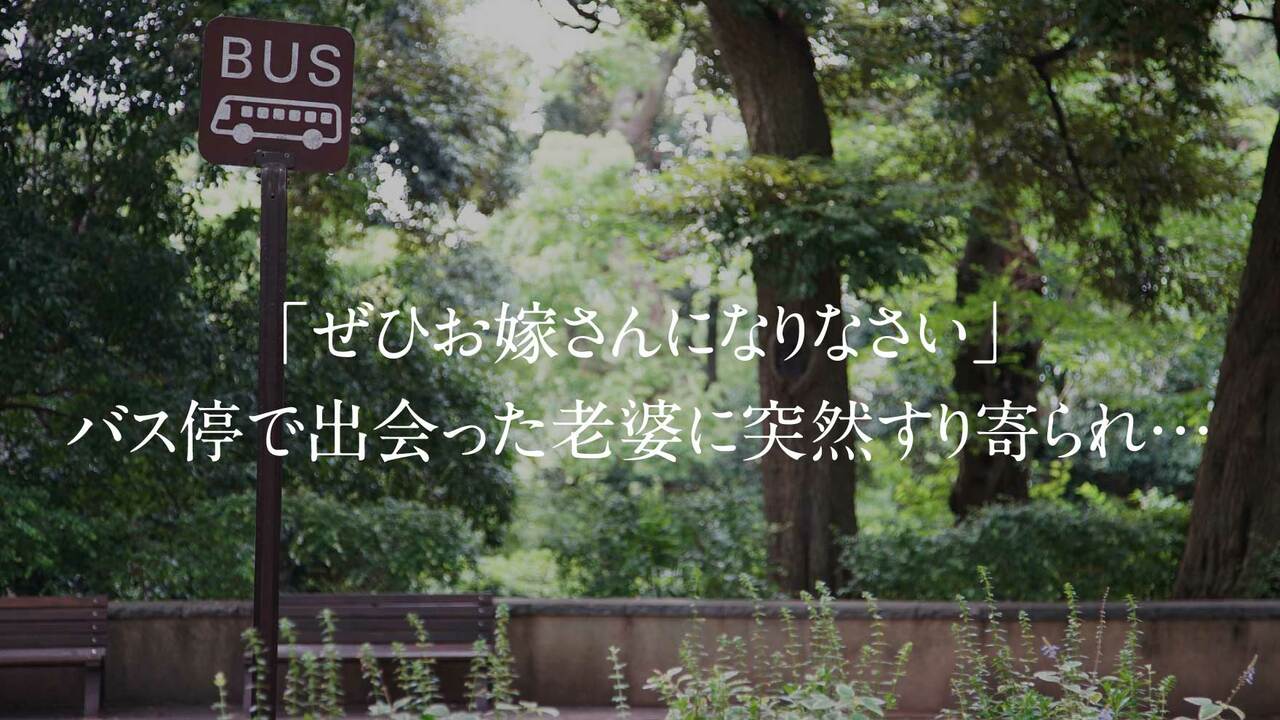一つの死
私は癇癪持ちの悪ガキに変身した。
困った母が、近所の偉いおじいさんの所に私を連れて行くようになった。右手に墨で三重丸を書いてもらい、おまじないをすると白い煙が出て、癇が逃げていくはずなのに、私の手から一度も煙が出たことはなかった。ひどい時は五重丸の時もあった。
私は小学生になった。学校までの道程を、棒を持って歩くようにもなった。私のきかなさは超一流だったと姉が語る。
親戚に浄土真宗の光照寺があった。当時光照寺は、住職を持たない無住寺院になっていた。
祖母は慈愛に満ちたとても信心深い人で、孫たちは週末になると、それぞれ雑巾を持ちお御堂の掃除をさせられた。
当時、私の村はまだ土葬で、「ごんぎつね」の葬列のように、死者を担ぎお墓へと向かった。祖父が死んだ時、妻はお墓に行けないしきたりのため、祖母は玄関にきちんと正座し、蓮如聖人の「白骨の御文」を朗々と静かに諳そらんじた。悲しみを胸に沈めた喪服姿の祖母は美しく、気品を漂わせ、その姿が映像のように浮かんでくることがある。
また、祖母は稲荷信仰を持っていた。京都伏見の稲荷神社が守り神様とかで、稲荷様の日が来ると、キツネの好きな油揚げを買いに行かされた。祖母はその油揚げで料理を作り、神棚にお供えして、長い間祈っていた。私たちも手を合わせ、祖母と一緒に祈った。
一週間で帰る日があると、七日帰りは仏様が帰られる日だからと言われ、前日靴だけ祖母の家に置きに行かされた。
私は祖母から、生活に根付いた宗教的心情の深さを感じていたのかもしれない。
お御堂の真ん中には、丸くて太い柱に囲まれた、金色の阿弥陀如来が安置されていた。
傍にピンクの造花で出来た蓮の花と、紫色の座布団に乗った赤銅色の木魚が置いてあった。その周辺や板張りの床を濡れ雑巾で拭き掃除をするのだが、子ども心にこの場所は特別な場所で、手を抜いてはいけないのだと思っていた。時々阿弥陀如来を眺めると、不思議な世界に誘い込まれるような気分も味わっていた。
お御堂の右手の窓側の場所に、赤い表装の「阿弥如来の来迎図」の掛け軸がかけてあった。
この絵も私を引き付けていた。
「この絵は何?」と祖母に聞いてみると、「良い行いをした人は、死んだ時、阿弥陀如来という仏様が迎えに来て、極楽浄土という所に連れて行ってくれんだぞ」と教えてくれた。小さかった私は、その言葉がどんな意味を持っているのか、よく理解する術を持たなかったが、心が温かくなったことを覚えている。その絵を眺めていると、確かに阿弥陀如来が迎えに来て、極楽浄土に連れて行ってくれるというイメージが表わされているように思われた。また祖母は、「悪いことをしたら閻魔様に舌を抜かれるんだから、良い行いをしなくてはなんねぇぞ」とも言った。
閻魔様とは誰なのか? おそらく舌を抜かれる位なのだから、よほど恐ろしい人に違いないと思った。極楽浄土がどんな所なのか知らなかったが、現実に見えなくても、その場所は薄紫の山並みの向こうにあるような気がした。絵がそんなことを教えてくれた。