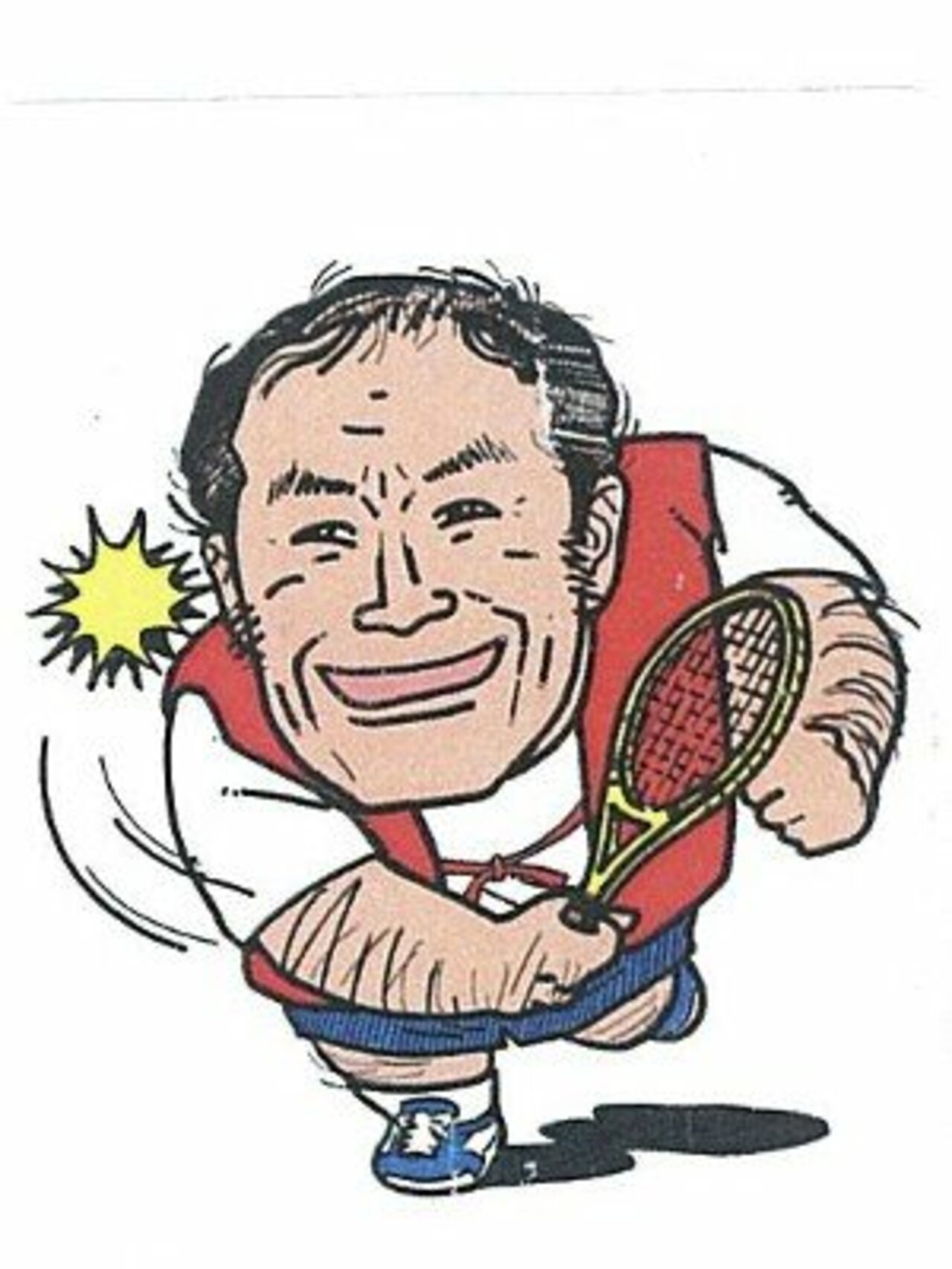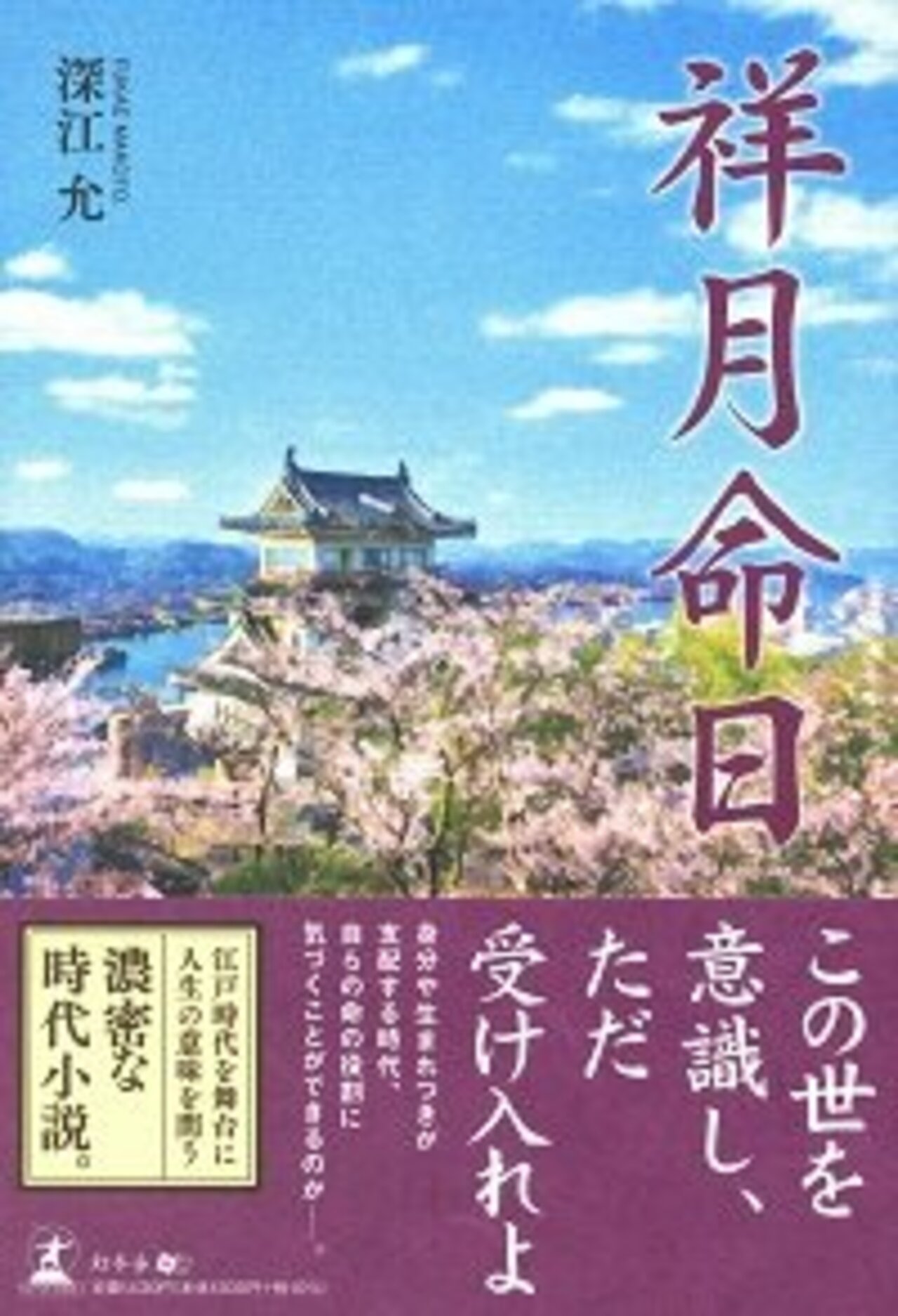その日も、一日勢戸屋を張っていたのだが、動きがなかったと見るやすぐに「いろは」に出向き、コノワタとナマコ酢でちびりちびり飲みながら遅い晩飯をとっていたときのことである。その吉三の近くで荷降ろしの人夫たちが声高で話をしていた。酔うと聴覚が麻痺し、自分の声が聞こえにくくなるから、勢い、声高になるのだ。吉三は聞くともなしに聞いていた。
「今日の荷は重かったな」
「知らないのか。あれは砂糖だ」
「すごい量だな」
「勢戸屋は砂糖の専売権を持っているんだ」
「誰かに取り入っているんだろうな。誰だかわからんが」
「勢戸屋は坊の入り江でも砂糖を運んでいるらしいぞ。去年の異国船難破事件で、しばらくの間は動けなかったらしいが」
吉三はそっと杯を口に運んだ。坊の入り江の吹という村に、ときどき薬を売りにいっている。だが、あそこでそんな話は聞いたことがない。抜け荷なら金崎港だろうとの先入観があるから、諸星玄臣と一緒に金崎港に出向いて、勢戸屋を見張ったり調べたりしているのだが、それが思いがけず、坊の入り江の名が挙がったのである。
坊の入り江とは南の藩境にある入り江で、人の立ち入らない危険な海である。日本海沿岸では冬場は厳しい風が吹く。その北寄りの強い風が坊の入り江にまともに吹き込むのだ。
雪交じりのゴーゴーとうなる風は、大きなうねりを生み、それを伴って入江に向かう。うねりは入江が狭くなるのと、入り江の中央に連なる岩礁のために、高さ四、五間の壁のように立ちあがり、大波となって押し寄せる。その迫力は、悩む心などひとたまりもなく吹き飛ばし、人の存在など圧倒する冬の海なのである。
さらに厄介なことに、坊の入り江の南側は断崖続きで、その際に蕪木川が流れ込んでいるので、風は入り江の南側、坊の岬から蕪木川河口まで続く断崖にぶつかって東に誘導され、入り江に立つ大波を引き連れて蕪木川を上流に向かって吹きあげていく。
海の水が蕪木川を逆流し、その塩害で下流域は荒涼として人のすまない土地だった。そんななかで、唯一、坊の入り江の北側の幾つかある窪地の一つに、吹という名の二十軒ほどの村落があった。村人は半農半漁で自給している。吉三は坊の入り江の抜け荷のことを小耳にはさんだときには、ちょっと信じられなかった。
吉三は、薬売りとして、吹の村には幾度となく訪れているので、坊の入り江の様子はよく知っている。それで、あんな海で抜け荷とは考えられないという先入観が強い。昨年の春に吹を訪れたときは、ものすごい嵐で足止めを食ったことがあった。
そのとき、その嵐で坊の入り江に見たこともない大きな異国の帆船が座礁するという事件に遭遇した。一人の生存者もいなくて、大騒ぎにならずに処理できたのはひとえに吉三の働きによるものだった。いまは、人の噂も七十五日で、もとのように人も近寄らない海なのである。そのような辺鄙で危険な海で抜け荷とは考え難いのであるが、吉三はとにかく諸星に報告した。