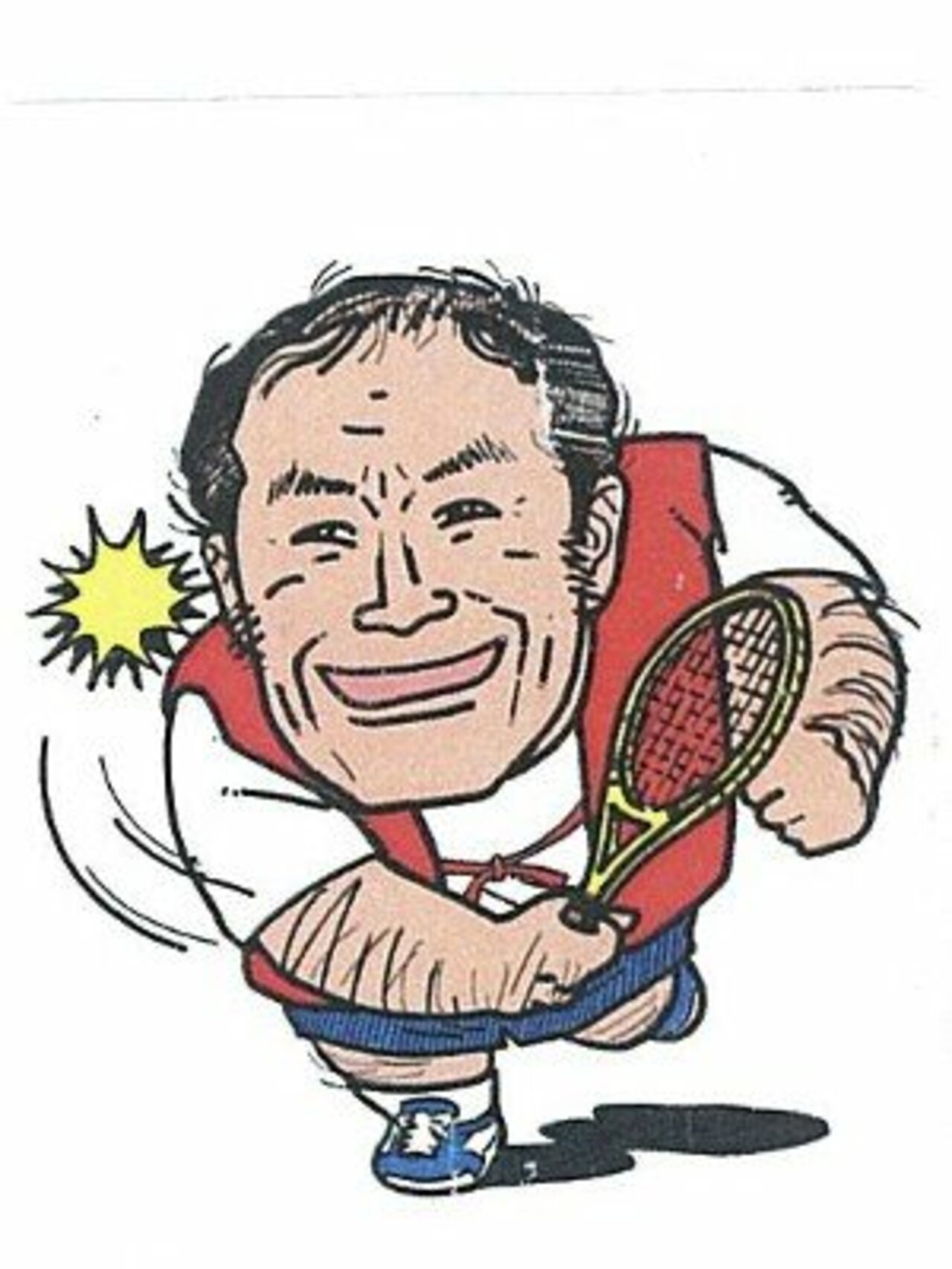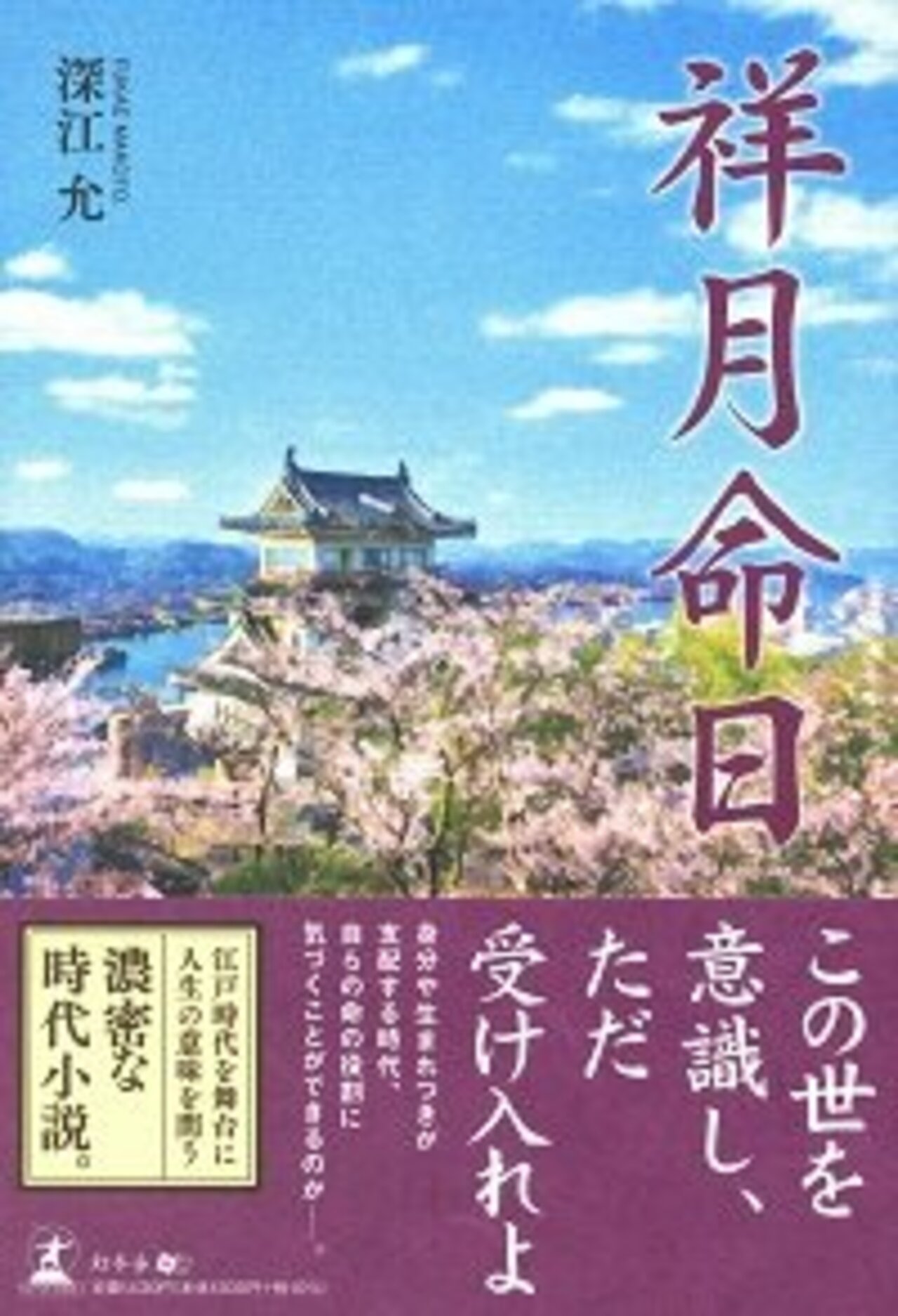脇坂と勢戸屋の密会
新宮寺隼人の息のかかった者が何やらきな臭い動きをしている。勢戸屋はそういう動きを察知するに敏感で、荷改めには進んで協力した。そうしながら、次席家老の脇坂兵頭に連絡を取り、誰の差し金か探りを入れた。
「勢戸屋、そんなに焦るな。まだ、我慢のときだ」
次席家老の脇坂兵頭は守谷口近くのお玉が池沿いにあるぼたん屋という料亭で、勢戸屋から饗応を受けていた。勢戸屋は多方面に多額の賄賂を贈り、そのおかげで帯刀が許されていて、輪丞と名乗っていた。
「そうは言っても、もう、だいぶ経ちますぜ」
勢戸屋は坊の入り江に大型の異国の帆船が座礁してから、そこでの抜け荷ができなくなって久しい。表向きの商売は堅調なのだが、うまみがなくて、抜け荷を再開したいと願っているのだ。
「あの船が撤去されてから半年以上たつが、こだわる奴がいてな。海防を強化しなければならないと、鷲の嘴に陣を張って、異国船の構造や性能を調べるために、荷揚げした荷物やら何やら調べているのだ。でも、それも、もうすぐ終わる」
勢戸屋は上方から古着を運んで売りさばき、店を大きくし、いまでは廻船問屋として上方は言うに及ばず、北から南からの産物を運んで手広く商売をしている。北は昆布、いりこ、南は砂糖、鰹節などを扱うのである。茶葉を運ぶこともあり、もっぱら藩内の消費に道筋をつけてきた。その点、藩内の産業振興にも力点を置いている米問屋の浦紗屋、織物の阿佐美屋、油問屋の蔦屋とは違った。
その勢戸屋があるときから抜け荷に手を出した。最初は中国や韓国からの漢方薬などの薬種を取り扱ったのだが、徐々に手を広げ、美術工芸品や骨董、婦人が身につける装飾品なども扱い、最終的には砂糖に目をつけたのだ。
河北藩は古くから上方との交流が盛んで、戦がなくなると心に余裕ができ、安寧に通じるあるいは保つものが求められ、上方からの茶道、華道、能といった芸能が受け入れられた。それらは北陸人の気質とも相まって、独自の伝統をつくっていった。特にたしなみの一つとして茶道が尊まれ、茶会が盛んに催された。
その際に食事が振る舞われるようになるに伴い、独自の食文化も育まれた。二河城下は食材が豊富だった。特に金崎港から朝どれの魚介類が粗衣川経由で運ばれ、城下の栄町の近くにある市場にもちこまれる。朝どれの活けじめにしたヒラメが城下まで運ばれてくる頃には、ちょうど良くうまみが出始めるといった具合である。
盆地の北側には畑地が広がり、季節、季節の葉ものにも事欠かなかった。昆布、いりこ、鰹節、イシルなどを使って出汁をとるなど、調理法が工夫され、砂糖を加えた濃い味の調理も好まれた。茶の湯が催されると、緑茶の豊潤な香りと渋みに合う茶菓として、和菓子のような砂糖を使った甘みの菓子が工夫され、それが人気となり、茶席に欠かせないものになるのである。
このように城下での砂糖の需要が高まると、抜け目のない勢戸屋は砂糖の取扱量を増やし、そのうえ、砂糖は贅沢品であるとしての徴税対象から逃れるために、抜け荷を始めたのである。砂糖の抜け荷は坊の入り江の沖で瀬取りして、坊の入り江から蕪木川を遡り、そこで陸揚げして城下に運びこんだ。