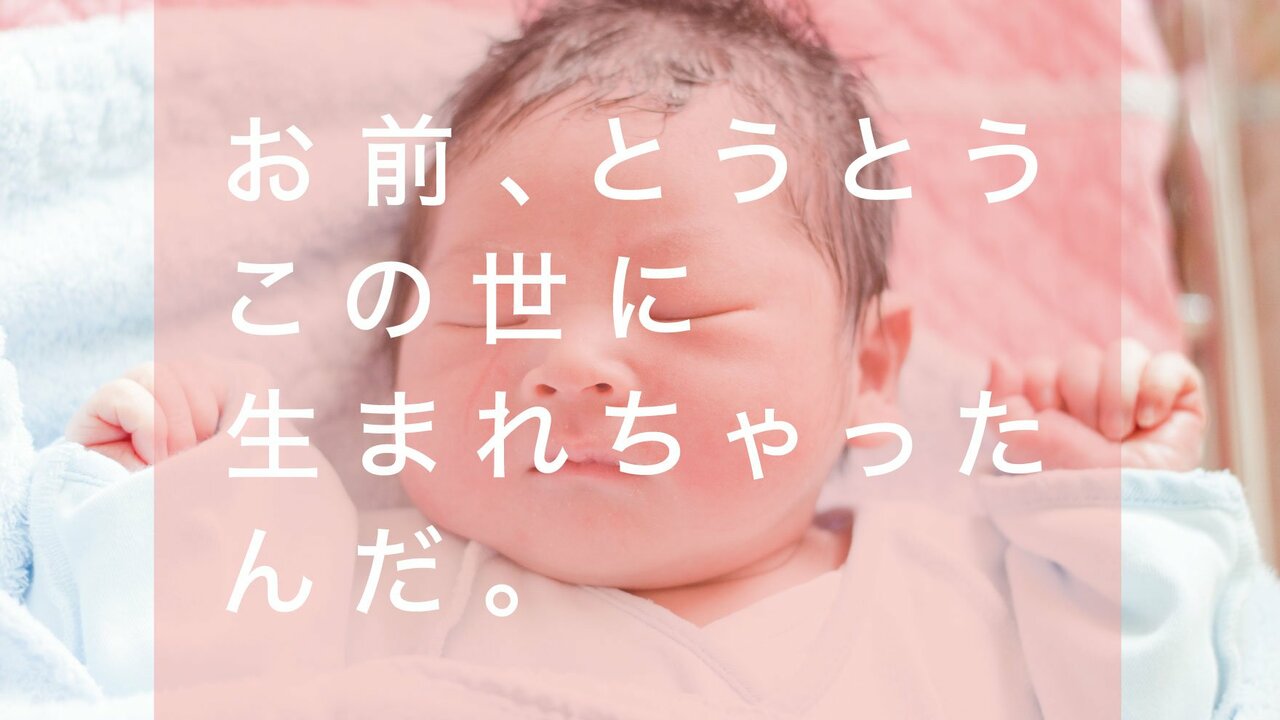午前中に家に帰り着いて、淳を待っていた。脱皮したような軽快な気分が、日が傾くに連れ沈んでくる。出産では男はただの役立たず。そこに舞い戻ってくる。夕日になって西北から茜の筋が林を射る頃に静かに帰ってきた。玄関で抱擁しても嫌がりもせず喜びもしない。
「疲れた? 友だちはどうだった?」
「逢えた……元気になれるといいけど……」
「そうか。そんなに悪かったのか。見舞い、喜んだだろう。行ってあげるといいよ、身軽なうちは」
……子供のことを言えなかったことが気持ちを曇らせる。
「あなたは?」
「男子会だって夜更かしして飲んでいた。僕、何回も失点したけれど、八汐って呼んでくれる。子供、でかした、って、乾杯してくれたよ」
「よかった」
「あなたの話でいつも二人がいっしょな訳がわかった。実際にそうだった。お義父さんは僕にちょっと厳しい。重信さんが執り成してくれる。爺ちゃんになるとは、って実感湧かないようだった」
父の方が優しいのだ、本当は。きっと内心は怒っている。
「ね。早く婚姻届出そう。お義父さんと僕の親父に証人になってもらう。鷹原は太洋がいるから、僕はあなたの方に入籍して構わない。あなたがよければ。ええと。それからできるだけ早くうちに家族を呼んでお祝いだ。親父と太洋にも出入りを許す。あなたの仕事をどうするか考える。勝手に決めた。どう? あなたの注文全部足していく」
「本当に、気遣ってくれて、ありがとう」
「ごめんよ。産んでもらいたいんだ。怖いの、どうしてもあげられないのに……」
「…………」
「ごめんよ。さあ、楽にして。まず食事をしないと」
「ごめんて言わないでね。八汐くんちっとも悪くないんだから。わたしだけが、ただ、怖いの……」
「……いいんだ、いいんだ……きっと大丈夫だ」
くったりと横たわって言葉がない躰に後ろから添い寝して髪の匂いを嗅ぎ、腰の括れに腕を回し、ああ、どうしたらいいのだろう……