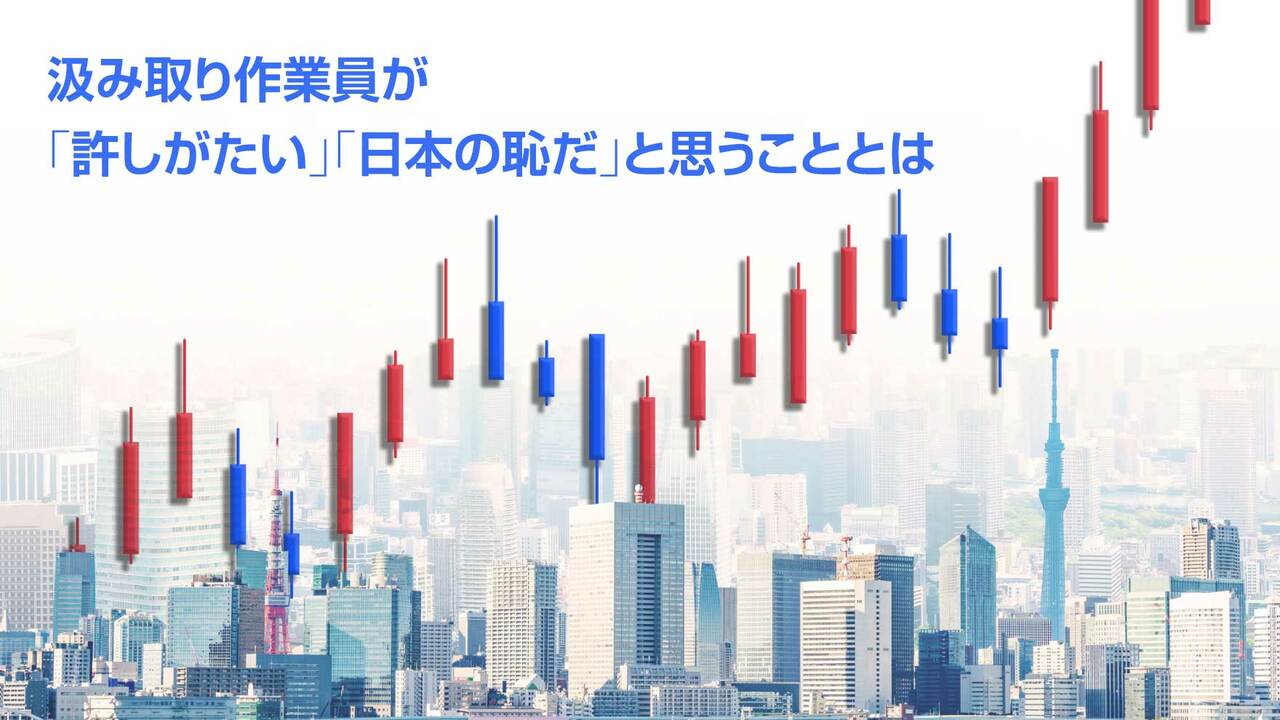糖尿病の治療を怠った末路は…
その頃の加藤家の主はスナックや居酒屋を何店舗も経営していて羽振りが良く、恰幅のいい四十代半ばの男だった。
加藤の自宅は庭が広いうえに、公道から奥まったところに建てられていた。自宅のトイレから公共下水道まで五十メートルもあり、敷地内に下水道を通して水洗トイレ化するのに、業者の見積もりでは、二百数十万円かかるということだった。
加藤はその費用がもったいなく、西方市下水道課からの要請にも従わず、いまだに汲み取り式のトイレを使っていたのだった。
糖尿病の特徴として、よほど重症化しないと、本人は気がつかないことが多く、分かっていたとしてもよほど悪くならない限り、治療に専念しようとする人は少ない。
健一は心配して、ある日汲み取りに行ったときに、
「糖尿病がひどいみたいですね。一度、病院で診てもらったほうがいいですよ」とアドバイスしたことがある。すると、
「うるさい。汲み取り屋なんかが余計なことを言うな。終わったらサッサと失せろ」
とひどく怒鳴られた。
加藤は、人に指図されるのを極端に嫌がる性格だった。加藤の妻も夫が荒れるのを恐れてか、夫の面倒な病気を認めたくない気持ちが先に立ったのか、
「まったく生意気なんだから、あんた早く帰ってちょうだい」
と吐き捨てるように言った。
健一は、次の月から加藤の家では声もかけずに、マスクをして業務用消臭剤を思い切り撒いて汲み取り作業を終わらせ、そそくさと帰るようにした。
それから半年以上過ぎた頃だろうか、健一はコンビニで加藤を偶然に見かけた。あれだけ力士のように恰幅の良かった加藤だったが、そのときの顔はゲッソリとして、ナイフでそぎ落としたように頬はこけ、こめかみのあたりには青黒い血管が浮き出ていた。
目はくぼみ、眼球はギョロギョロしていた。まるでむき出しの頭蓋骨に、なめした革を張り付けてビー玉を埋め込んだようだった。
健一は一瞬息を飲んで立ち尽くしてしまった。いつもなら人を選ばずに近寄っていって、
「こんにちは。いつもお世話になります。今日は暖かいですね」
などとニコニコして声をかけるのが常だが、そのときばかりは加藤に気づかれないように、色鮮やかなノド飴の袋がズラリとぶら下がっている棚の陰に思わず隠れてしまった。
間もなくして、加藤の家も下水道につなぎトイレを水洗にしたので、健一が訪問することはなくなった。また、町で会うこともなくなった。
水洗トイレにすると、排便後の臭いが少なくなる分、体調の変化に気づくチャンスも減る。まして家族を含めて他人から異常を指摘されることなど、まったくなくなる。
健一は、加藤が亡くなったと聞いたとき、一瞬「ざまーみろ」と思ったが、すぐに自責の念に襲われた。怒鳴られたあの後も、奥さんにだけでもそっと病院に行かせるように、毎月言い続けてあげれば良かったと思った。
健一は後悔して、胸が「ヒクヒク」するほど苦しくなった。