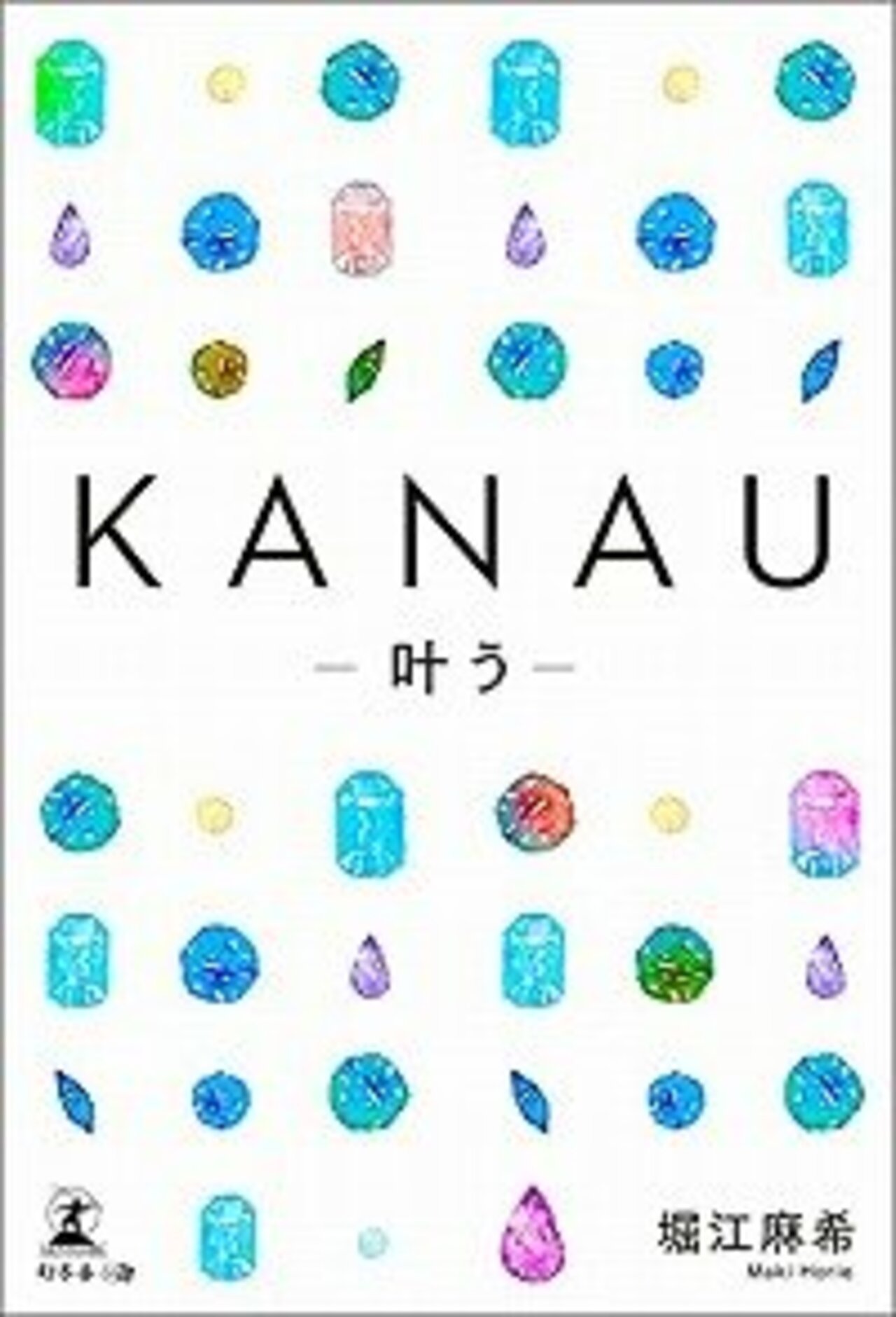優理は奏多につくとしばらく海沿いを歩く。望風は、その間二人の定位置になりつつある海辺のコンクリートの階段で、優理が隣に来てくれるのを海を見ながら待っていた。リュックからランチョンマットとフルーツゼリーとレモン水をだして、用意しておく。
海の方から遅いスピードで冷めた空気が押し寄せてきて、火照った体に現実を突き付けてくる。夜の海は、少し望風を不安にさせることが多かった。海面にうつる月も黒い海も穏やかな波も。夜明けがくるとわかっていても、絶望が過ってしまう。
愛を知ったからだと、望風は考えていた。愛は悲しみを生む。尊く美しい目に見えない感情は、すべてを捨ててでも貫こうとする想いは正義ではなかったのだと、今の望風はそう解釈している。誰かの為に一生演じていてもいいとそう思っていた。でも望風は、愛の早い段階で、何かが違うと気づき始めていた。
自分を取り繕っていることに気づく。誰かの為の自分が本当の自分なのか、そうではないのか、本当の気持ちはどれなのか。毎日毎日、答えを探すように笑ったり泣いたりした。自分の気持ちと向き合うことがこんなに苦しい事だなんて思ってもみなかった。
ガラスの林檎は誰にでも見えるものなのだろうか。なぜあの人に出会って愛を知ったのか。その理由を探すようになっていた。その先に何かがあるだなんて、今の望風には知る由もない。まだ愛から抜け出せずにもがき苦しんでいる。結ばれる、結ばれない、でも結ばれるはずだ。まだ信じている。自分があきらめずにいさえすれば、いつか幸せになれると。愛は永遠なんだと。
でもそう信じて前に進もうとすると、目に見えないバリアにつき返される。そのバリアを打ち破れば、またきっとあの人が抱きしめてくれるんだと。そう信じぬこうと闇の中で耐えていた。でも本当は信じてなんかいない。答えが欲しかった。なぜこんなにも愛したのか。愛を恨んだ時を経て、悲しみを知り、苦しんだその先に、新たな何かをつかみとれるのだろうか。
教えてほしい。私たちは幸せになれるのか。何かを知った傷だらけの戦士は、選ばれし者だ。望風は、世界を救えるかもしれない。嵐の中に立ち向かっていけるかもしれない。答えを知った時、それを説くだろう。
「もかー、タオルもってね? 今日汗がえぐい」
望風は、リュックからとりだしたタオルをひろげ、背伸びして両手で優理の髪の毛をおふろあがりのようにふいてあげた。優理は、望風に身を任せ、望風がそれをやめるまで待って、照れ隠しのように海辺の砂浜を歩きだした。
望風は、その場に座って、優理の後姿を中央に、月明かりだけの真っ暗闇の水平線を背景にして、スマホで写真を撮ったあと、黄昏た。恋ならば奇跡となる。夢も叶う。たくさんの奇跡が集まれば平和になる。悲しみの先に、望風はそんな未来を思い描き、イメージを膨らませた。