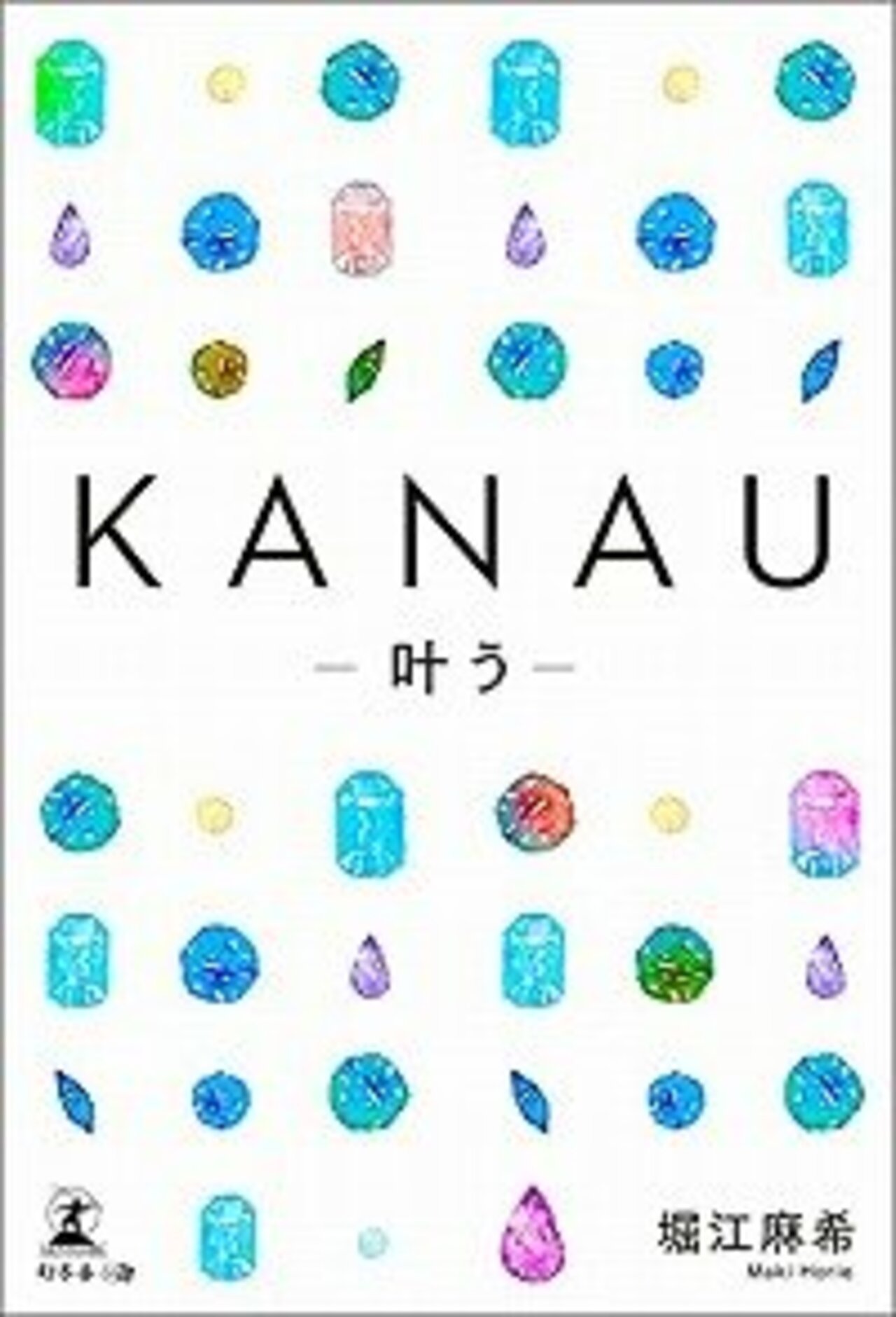KANAU―叶う―
望風には姉が一人いる。男の兄弟はいない。ママに息子がいたらどんな関係性を築いていただろうかと思ってみる。料理好きなママのことだから、今よりももっとレパートリーが多かったかもしれない。パパに愛されるように息子にも愛されただろうなって思っていた。望風もたまにドキッとするくらいキュートなママだ。二人は恋人同士なのかと思うほど、ほほえましく見ていられた。
私がらせん階段をおりてきても、見向きもせずに二人で話し込んでいた。いつものごとく、その間に私は、ランシューをはいて、自転車を歩道にだしてスタンバイしておく。青ベースのロードバイクは、ママが優理のジョギングについていくために買ってくれたようなものだ。優理がこうやって訪ねてきたときは、専属マネージャーのように、走る優理の後ろを自転車でついていく。
優理は、人懐っこくて口がうまく、万人に好かれるタイプだ。望風もアポなしでジョギングに誘われても全くいやな気にならない。むしろ、やったーと叫びたくなるくらい楽しみにしている。優理が玄関で、
「さよさん、またねー!」
と言っている。さわやかに望風の方へ駆けてきて、行くぞっと望風の頭に手をおいた。望風はきゅんとしてしまう。いつも優理は望風の弱みにつけこんでくる。望風の元気が無い事に気づいていたのだろう。望風は常に優理に助けられていた。
優理の5メートルほど後ろをついていく。望風は、ロードバイクに乗るのも楽しみにしている。その間の時間、ひとりきりじゃないけど、いつも深く自分と向き合える。望風にとっては、とても有意義な時間の使い方となりつつあった。優理がいつもこの時間をプレゼントしてくれる。ほっとけないからそばにいるけど、口出しはしない。そんな優しさをプレゼントされてるみたいだ。
二人ともただ黙って前進する。望風の家から奏多までを往復するのが、いつものパターンだ。奏多で休憩をはさんで。自転車のペダルをこいでいる間は、その日の空気を、寒いとか澄んでるとか明日雨かなとか日ごとに感じた後、優理の後ろで、背が伸びたかなとか少し肩幅が広くなったかなとかこのパーカー持ってたっけとか一通り思って、そのうち、どうしてあの人に出会ってしまったんだろうとか今頃まだ仕事かなとか会いたいなとか、好きな人の顔やしぐさや会った時に見た表情とか考えてしまう。
優理の後ろで考えられることが、なんだか守られているような安心感に包まれていて、あまり苦しくならず、さみしさも半減できて、いいのかもしれない。望風にとって居心地のいい現実逃避の時間だった。
優理の走るスピードが少しずつ落ちてきた。奏多が近づいてきたということだ。