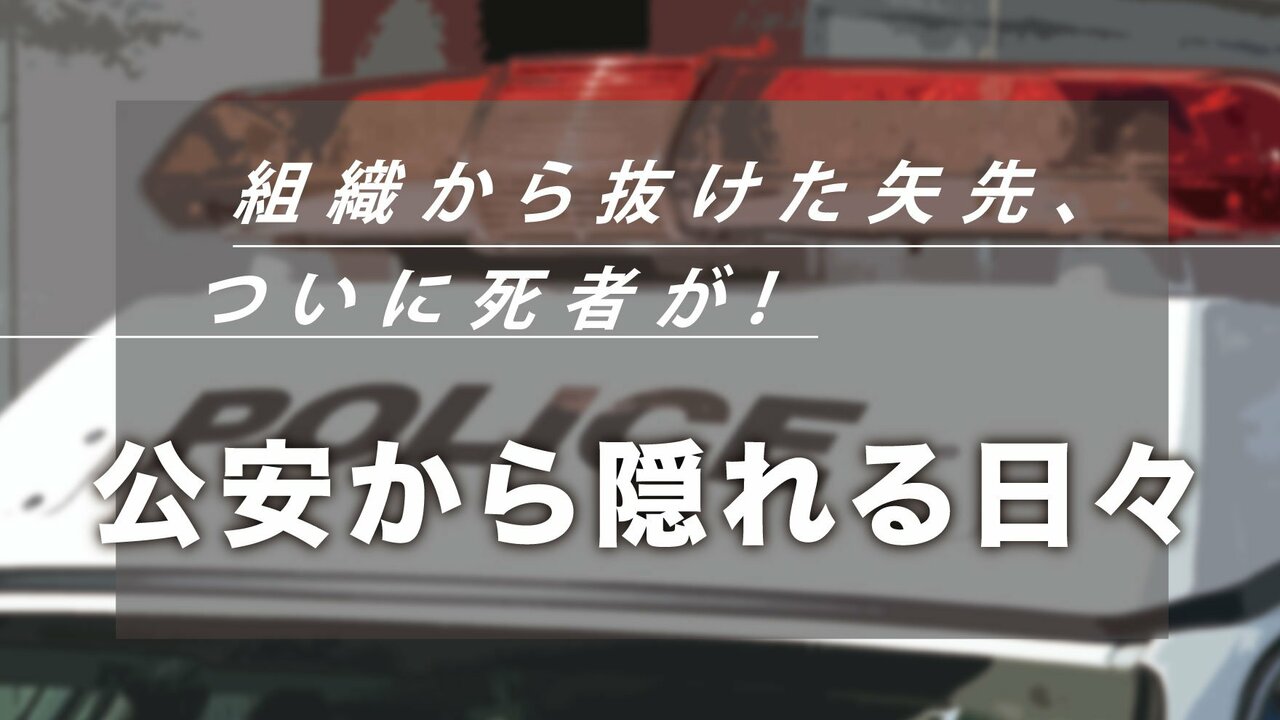しかし、祖父の願いも予感も空しく外れてしまった。私は母から奪うだけ奪って、母を顧みることもなく、不幸の中に死なせてしまった。何と大きな犠牲を払わせたことだろう。何と思い遣ることのなかったことだろう。そしてすべてが過ぎ去って、どうしようもなくなってから、それを悔いるしかなかった。
どうしてこんなことになってしまったのか。それにしても私は優しい子のはずだった。ラジオから流れるアンクル・トムズ・ケビンの放送が悲しくて、家の外に出て泣いた。私が通った教会のシスターは私を女の子よりも優しいと言った。無論、私が優しいとしたら、それは母の優しさだった。私の身も心ももともとは母のものだった。
私はそんな母の中から巣立とうとして身をもがき、母をあとにして一人羽ばたいてきた。そして、いつしか三十余年の歳月を過ぎ越していた。それは私自身が不幸になることによって、親不孝のかぎりを尽くすことだった。
しかし、そんな私の身勝手な人生も終わりに近づいていた。自分の死を予感するようになって、私はしきりに自分の原点、母の中に帰ろうとする衝動に駆られるようになっていた。風雪の荒野をさ迷う少し前、私は姉に頼んで母の骨を手に入れようとしたことがあった。母の骨を抱いて死んだなら、また母の中に眠り込めるように思ったのだ。無論、そんな私の願いはかなうはずもなかった。――母の骨は、姉の教会の納骨堂に父の骨と一緒に眠っている――それもいいだろう。私が死んだなら、どの道、その納骨堂に収まるのだ。母は「今は生きろ」と言っていたのだろう。
アルコール中毒で病み衰えて、死線をさ迷った私は、自らの死への関わりによって、永遠へと回し向けられ、浄化されていくように思われた。それが悲しみを優しさに転化していった母の生き方でもあったろう。
私は、今、この時、この場所で、他ならぬ私が生きてきた人生を、より本源的なところから捉え直し、生き直すことが、自分に残されたなすべきことであり、またそれが自分の犯した罪の償いでも、失われた人生の取り戻しでもあると思うのだ。