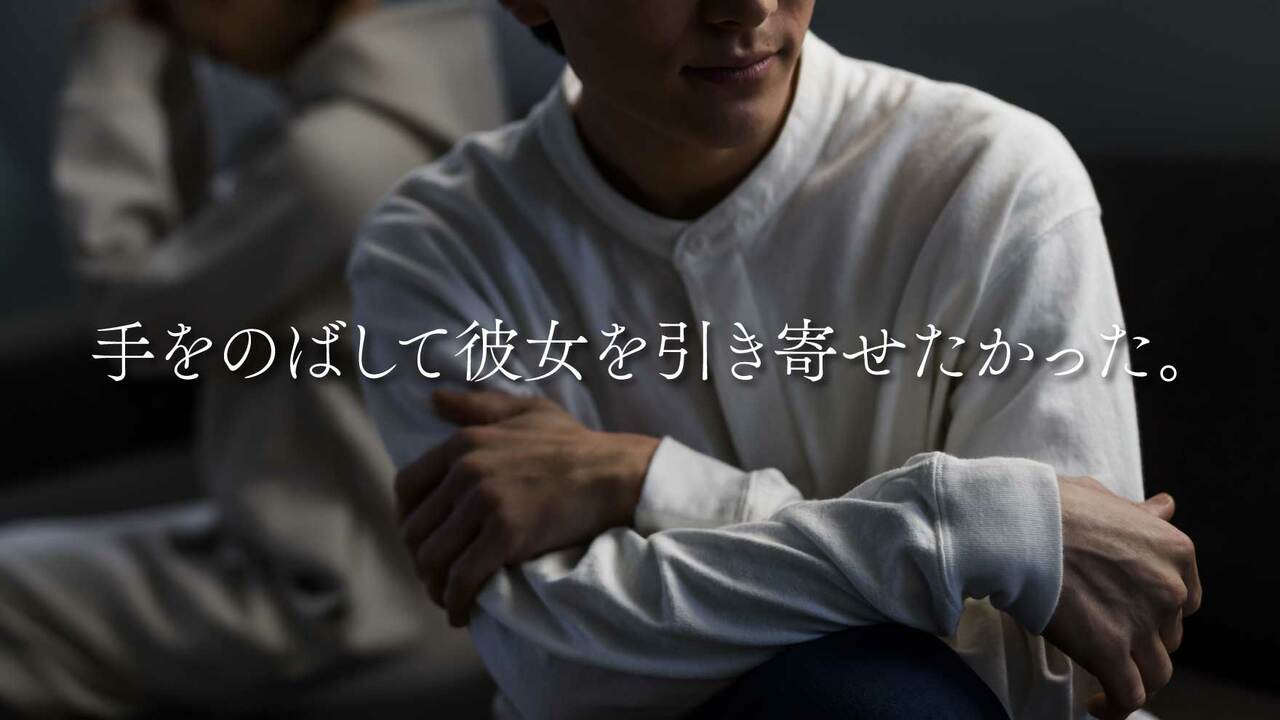「えっ、そんなに切って大丈夫ですか?」
耳たぶまでかかる彼の前髪をクシでとかしながら、長さを確認した。やはり短髪にするとかなりのイメージチェンジだ。笑わせようとわざと言ったことはすぐわかった。
「一気に短く切ってしまうと取り戻せないので、長さを見ながら切っていきますね」
こんな会話ができるのもどれくらいぶりか。シャンプー台にオガタさんを寝かせ顔にクロスをかけると、シャンプーの蛇口をひねりちょうどいい温かさで頭に触れた。頭の上、こめかみ首の後ろまで丹念にヘッドスパを施す。しかし、右手の親指の付け根から強い痛みが走り、力が入らない。ふっと今朝の出来事が頭によぎった。トリートメントをつけて、ホットタオルで肩首をあたためたまま数分おき、しばらくしたら洗い流しシャンプー台を起き上げた。
「はい、終わりましたので上げますよ」
起き上がったオガタさんの表情筋が緩んで、ぱっちりと黒目が開いた。
「あぁ、いつもながら気持ちいねぇ」
「さっき突き指してしまったんですけど、マッサージいつもより弱くなかったですか?」
「えっ、突き指、大丈夫?」
「扉に手を挟んだだけですけど」
「俺さ、昔バスケ部だったからずいぶんと突き指したけどなあ」
「バスケ部には見えないっすね」
「ハハハ、ばれたか」
愛嬌たっぷりの冗談が嬉しくて、久しぶりに笑った。カットは前回よりは少し短めに、耳が半分見えるくらいまで切ると、スタイルはそのまま、すっきりとした印象になった。
「いいねー、このスタイル」
「いつもより短めにしましたが、違和感ないですよ」
黒縁のメガネと黒のジャケットをはおり、前のボタンを留めながらオガタさんは最後にもう一度鏡で頭を左右に傾けながら、全身をチェックした。
「今日は切ってもらってよかった。気持ちも軽くなったよ」
「オガタさん、身体に気を付けてくださいね」
「また来るよ。指、お大事にね」