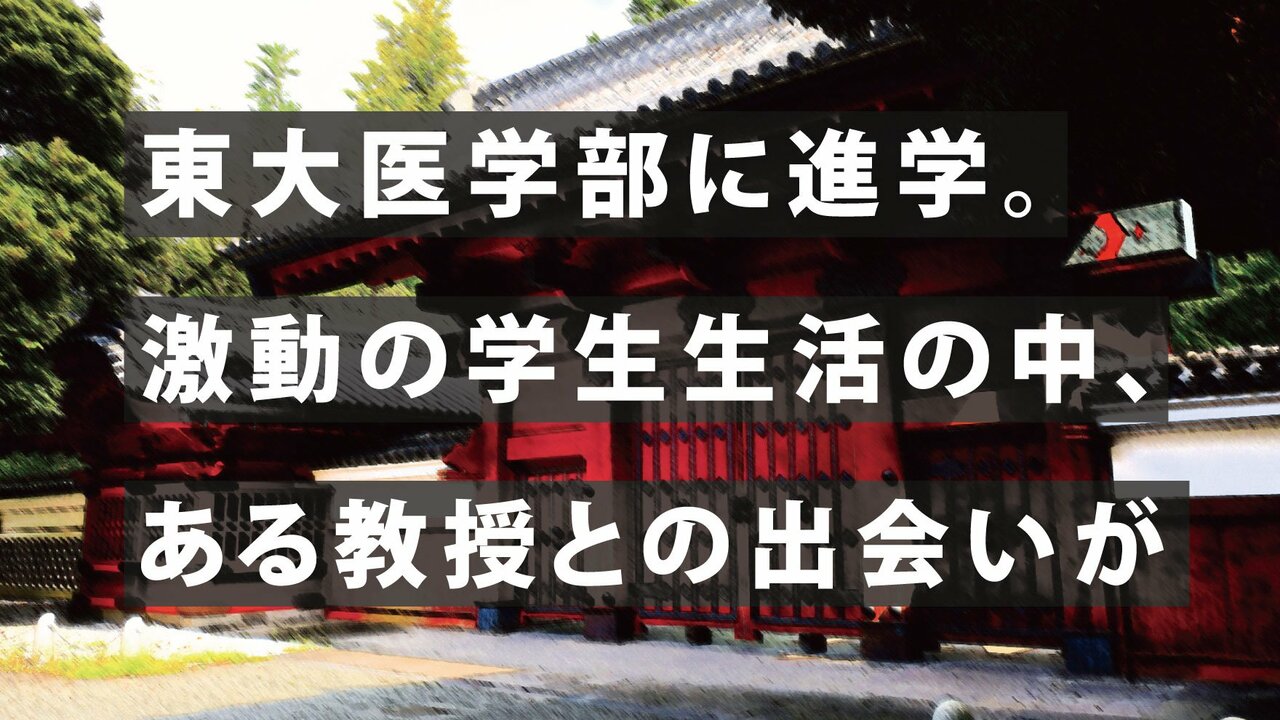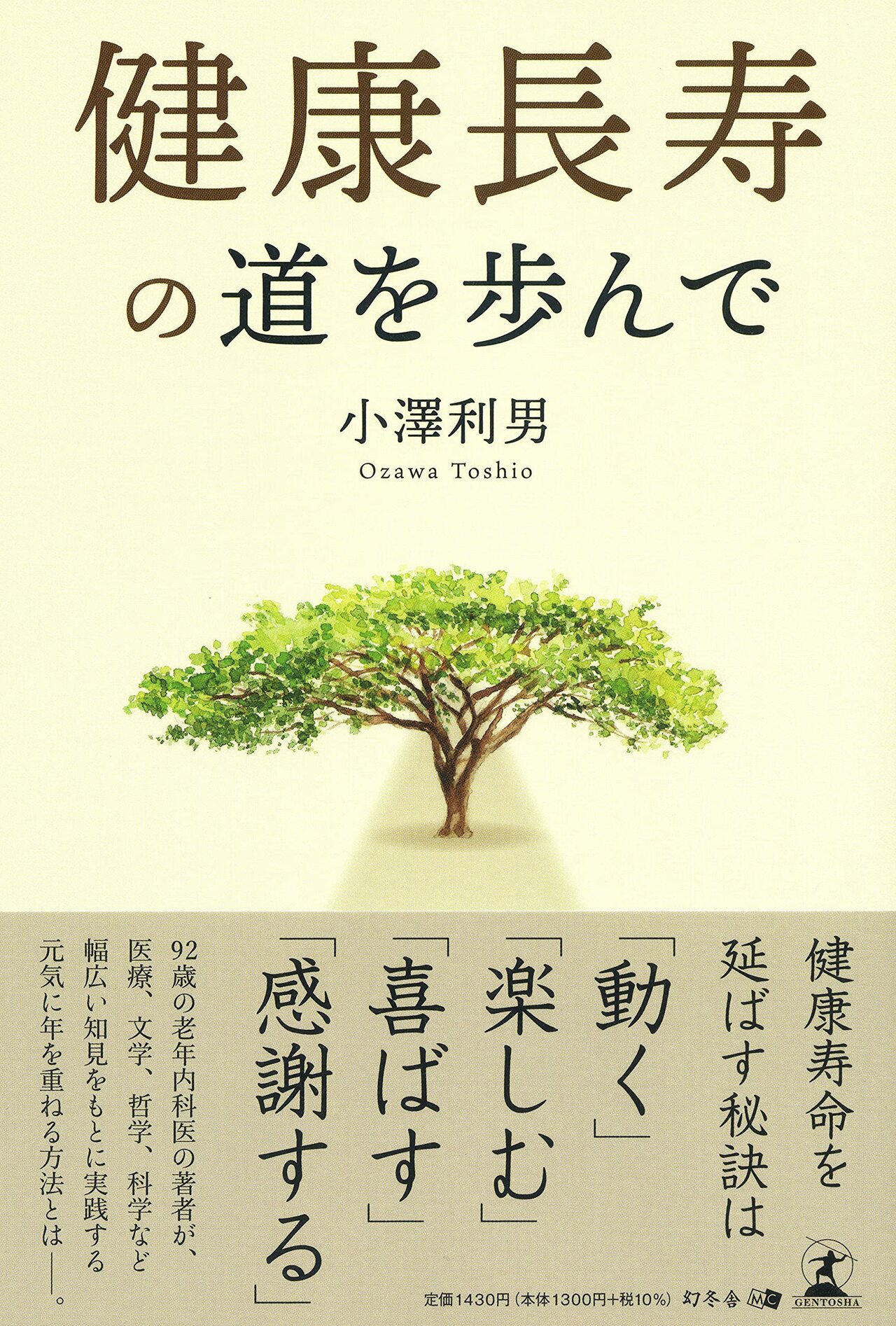【関連記事】「病院に行って!」背中の激痛と大量の汗…驚愕の診断結果は
東京大学医学部
旧制高校三年を終了すれば、自分がどういう職業に就くかを選択しなければなりません。私は、数学、物理、化学などに興味を持っていたので、理工系の学部に進学したいと思いました。しかし兄と弟が技術者として生きる希望があり、共に東大工学部に進学しました。また母からも一人くらいは医師になれとすすめられたので、東大医学部に進学することにしました。
東大の赤門を入って、真っすぐ銀杏並木に沿って歩くと、正面に医学部本館があります。東大医学部は我が国最古の官立大学で、現在も医学・医療の中心的存在です。
だが入学してまず辟易したのが、解剖学の講義でした。とにかく人体臓器の名称を暗記しなければなりません。臓器には細かなところまでラテン語の名称がついています。そのため、はじめにラテン語の手ほどきがありました。講義は大きな図譜を吊るして、砂をかむような骨の講義から始まります。そして二人に一体の解剖実習に移ってようやく学問らしくなります。顕微鏡での観察で、まだ目にしたことのない組織、細胞の微視的世界が広がってきます。
基礎医学が終わって、臨床医学総論になると、教授が原稿を読み、学生がそれをノートするという講義が始まります。これが退屈で意味がなく、一時間半の間、大抵の学生は居眠りをしていました。一方、米国の医学生は、基礎医学を終えると、すぐに病院勤務となり、患者を診ながら直接指導を受けることになるので、卒業時には医師として患者を診る能力が身につくようになります。
我が国のインターン制度は、米国からの勧告で導入されたシステムで、自ら開発されたものではありませんでした。病院にとってインターンはお荷物のような存在で、無給で雑用をさせられました。インターンの時期には閑だから、本郷で麻雀をしている学生がたくさんいました。
要するにドイツ医学教育システムから圧倒的な勢いで流入してきた米英の医学・医療に対応できず、「日本の医学教育をどうすべきか」という基本的構想を全く欠いていたのです。
その象徴が学生から起こった一九六八年のインターン廃止運動で、学生のストライキと団体交渉で始まりました。しかし教授会は交渉で医局に座り込んだ学生に、処罰を以て対抗しました。そのなかに当日不在であった学生の氏名があり、紛争は一気に拡大していきました。