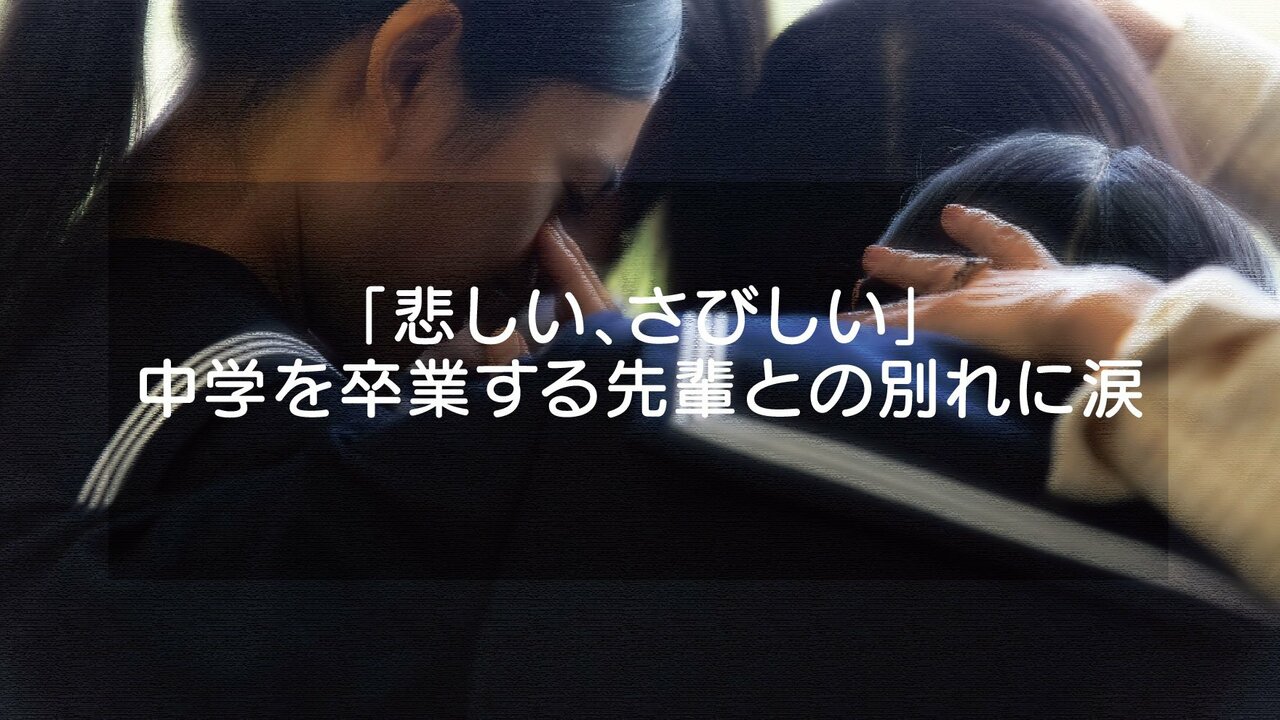「ポンちゃん、トロいとこあるからしかたないけど……。金曜のうちから、一年生の間でもけっこう噂になってたんだよ」
かなりひどい言われようだけど、悲しいかな反論できない。それに、あの日のわたしは、ミュウのことばかり考えていて、そのほかのことは目にも耳にも入らない状態だった。
「じゃあ、そこから話すよ。その事件っていうのはね―」
マオが話してくれた事件のあらましはこうだ。金曜の朝、2-Fで、ある生徒の机の中に死神のタロットカードが入れられていた。しかもそのカードは、血のような液体にまみれ、赤黒く染まっていた。
タロットカード―西洋の占いで使うカードだってことくらいは知っている。けれど、わたしの中にあるのは、不吉で気味の悪い絵ばかり描かれている怖いカード、せいぜいそんな程度のイメージだ。
「その……血のような液体って、まさかほんとに……」
「ああ、さすがに、本物の血ってことはなかったみたい。絵の具とケチャップかなにかを混ぜて、それらしくしてあったらしいよ」
それでも、悪ふざけや冗談で済まされることではない。脳裏をかすめたのは〝陰湿〞という言葉だった。
いったい、だれがそんなことを―。
そう考えかけ、わたしは、はっとしてマオの腕をつかんだ。
「ねえ、それでサキ先輩がどうしたの? その事件とどういう関係があるの?」
「うん……」
マオは、周囲を見わたし、近くにだれもいないのを確かめてから声をひそめた。
「サキ先輩が、この事件の犯人にされてるんだ」
にわかには、その言葉の意味が理解できない。
先輩が……犯人?
「うそよ! いいかげんなこと言わないで!」
「ちょ、ちょっと、ポンちゃん、声が大きいって」
マオは、あわててわたしの唇に指をあてた。
「だって……」
先輩が、そんなことするわけがない。きっと、なにかのまちがいだ。
「わたしだって信じたかないよ。でも、目撃者がいるんだ」
「目撃者?」
「うん……その生徒は、前の日の夕方、だれもいない教室に一人でいる先輩を見たって言ってるらしい」
そんな……。いくつもの疑問が、整理のつかないまま頭の中を駆けめぐる。
「その人は、ほんとのことを言ってるの? そのとき教室にいたのが、先輩だってどうして言えるの?」
「お願いだから、わたしを責めないでよ」
「責めてなんか……」
マオは、目を閉じ、なにかをはらいのけるみたいに首を振った。
「しかたないじゃん」
「しかたないって、そんな! なんでそんなこというの!」
「先輩が認めてるんだ」
え……今、なんて言ったの?
「認めてるんだよ。自分がやったって」
「そんなこと……」
うそだ。そんなことあるわけない。