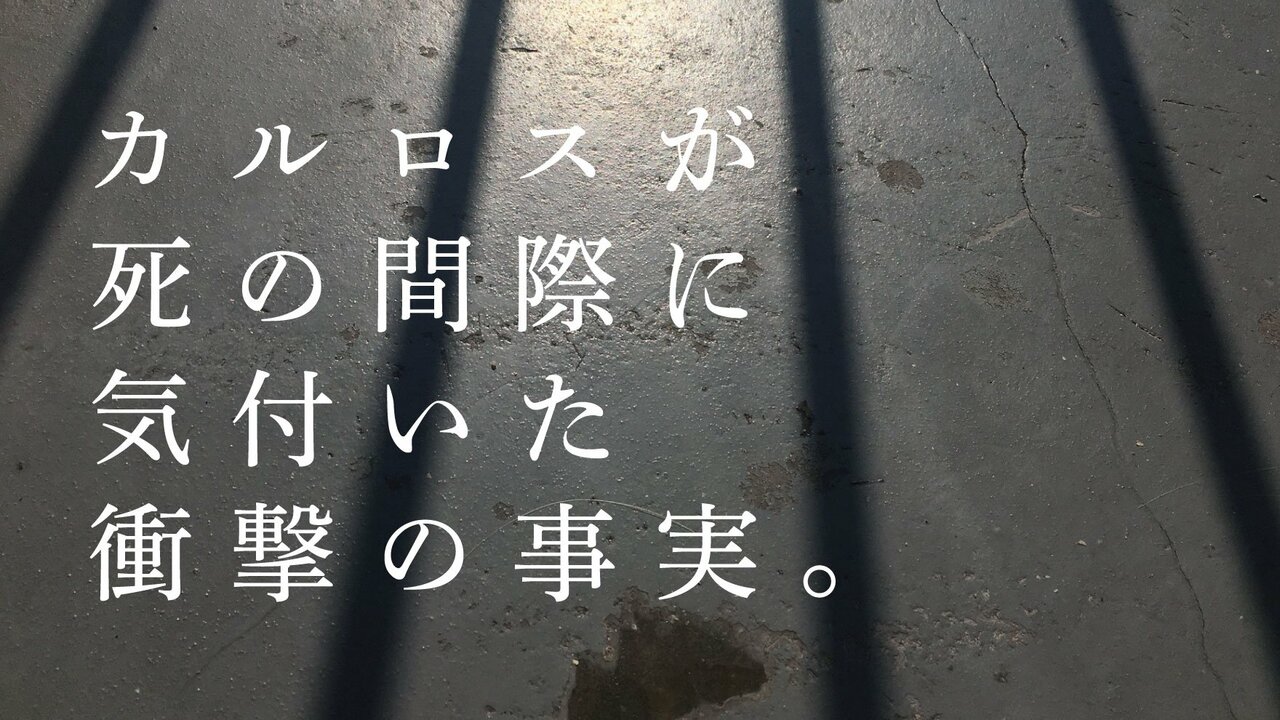次の朝、ラブラドールレトリバーの子犬はケージの中で冷たくなっていた。カルロスは、固くなった子犬をテーブルに置き、メスでおなかを切り、黒い袋を取り出した。子犬は死んでいるので、メスで切っても血も出なかった。取り出した黒い袋を洗って消毒液につけた。
後でこの袋を次の犬のおなかに入れようと考えながら、カルロスは死んだ子犬をプラスチックの袋に入れ、廊下にある大きな冷蔵庫に放りこむと、白衣を着てフィオリーナの手術に取りかかった。フィオリーナがぼんやりと目を開けた。手術が終わった後、薬で眠っていたのだ。おなかには、白い包帯が巻かれている。カルロスがフィオリーナに近づいた。
「そう言えば、お前は昔飼っていた犬によく似ているなあ。あいつとは一日中、牧場で遊んだよな。そうだ、毒蛇にかまれたことがあったな。死にそうになって、とても心配したけど朝起きたらすっかり元気になっていた。でも蛇にかまれた所は、その後もずっと毛が生えてこなくてはげたままだったな」
カルロスは確かめるようにフィオリーナの後ろ足をさぐってみた。どこにもはげた所はなかった。
「この犬があの子のはずがあるわけないじゃないか」
カルロスは苦笑いして手を放した。そして、なにげなくつぶやいた。
「フィオリーナという名前だったなあ」
そのとき、ケージの中に横たわったままのフィオリーナのしっぽが、ふらふらと力なくゆれた。
「馬鹿なちびだな、お前は。お前をこんな目にあわせたのは、この俺だってことが分からないのか? それなのに、この俺にしっぽをふるなんて」
カルロスはうす笑いを浮かべてフィオリーナから離れた。しかし、このときのフィオリーナの姿は、なぜかカルロスの心にいつまでも残った。もし、このとき、カルロスがフィオリーナの体をよく見ていたら、ある大切なことに気付いたことだろう。
しかしカルロスは、フィオリーナを麻薬の入れ物としか考えていなかったので、その大切なことに全く気が付かなかった。フィオリーナの首に自分が作った銀のメダルがかかっていることに。