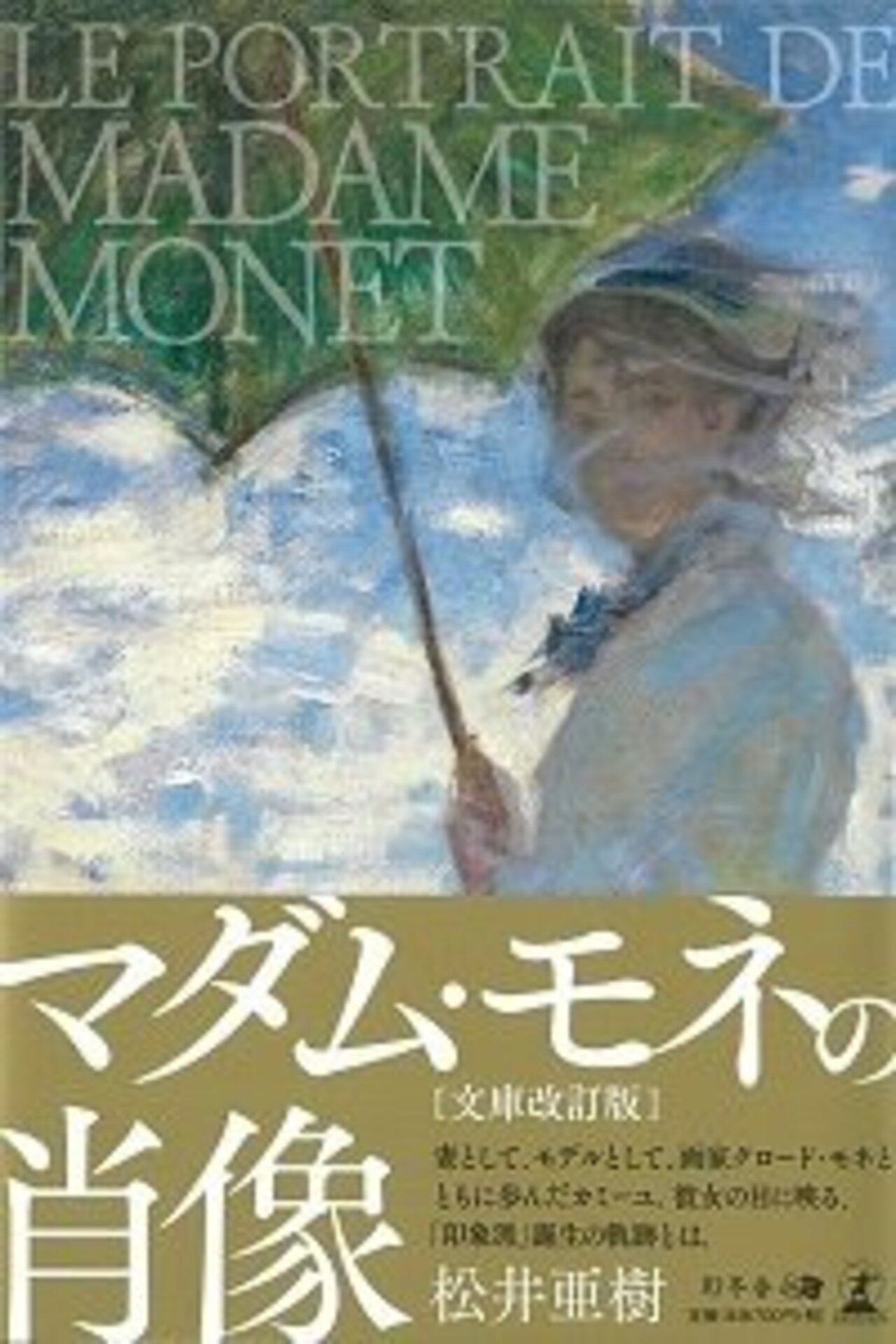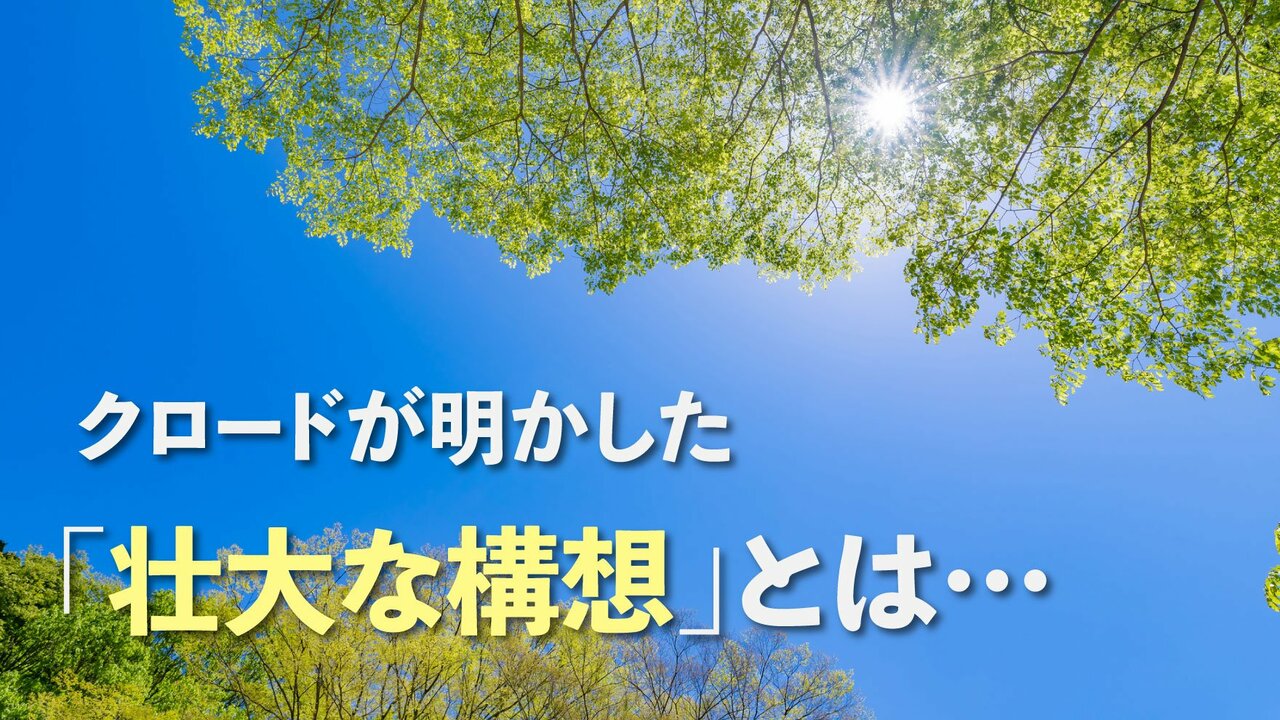振り向いた男は、少し驚いた顔をしていた。柔らかそうな巻き髪。白く額の秀でた顔には鼻筋が通り、明るい瞳は理知的で穏やかだった。上等なスーツを品良く着こなしたその姿は、どこから見てもさわやかな紳士そのもの。この人がエドゥアール・マネ? それはカミーユにとってあまりに意外だった。エドゥアール・マネの名を、ついさっき思い出したところだったのだ。
この人は二年前にも大スキャンダルの渦中にあった。その二年前の一八六三年、マネがサロンに提出した『水浴』(のち『草上の昼食』と改題)ほか二点は落選した。その年は三千点以上が落選の憂き目に会い怨嗟(えんさ)の声が上がっていた。マネらは落選作の展示を求める請願書を皇帝ナポレオン三世に提出。皇帝が「落選展」開催を決定すると、多くの落選者が嘲笑を恐れて出品を見送る中、マネは迷わず落選作三点を出品した。
サロンと回転ドア一枚隔てた落選展会場に『水浴』が展示されると、そこでもセンセーションを巻き起こした。作品を取り囲む大きな人だかりから、一斉に罵声と嘲笑が浴びせられていたからよく覚えている。
森の中で昼食を摂る二組の男女。女性だけが裸で、やはりまっすぐに鑑賞者を見ている。ルネサンス以来重視されてきた遠近法は無視され、アカデミーが言うところの“完成作”に必要な仕上げも疎かだと罵倒された。
同じ年、より劣情を誘うと思われるアレクサンドル・カバネルの『ヴィーナスの誕生』はサロンに入選し、ナポレオン三世によって国家買い上げの栄誉に浴したというのに、マネの絵はやはり不道徳だといって世間の非難を浴びた。
「ええ、私がエドゥアール・マネです」
一瞬驚いた顔を見せたのに、応える口ぶりはいかにも紳士然として落ち着いていた。ごく周辺にいてこの会話を耳にしたわずかな観衆は、やはり不思議なものでも見るようにマネを眺めた。これまで散々言い散らかされていた悪口雑言(あつこうぞうごん)も、少なくともそのごく周辺ではピタリと止んだ。
皆、意外だったのだ。すでに二年前から、マネといえばアカデミーに反旗を翻す、悪趣味な外道(げどう)画家だと誰もが思い込んでいた。外見もそれにふさわしく、いかにも不道徳なボヘミアン風だと想像していたのだろう。