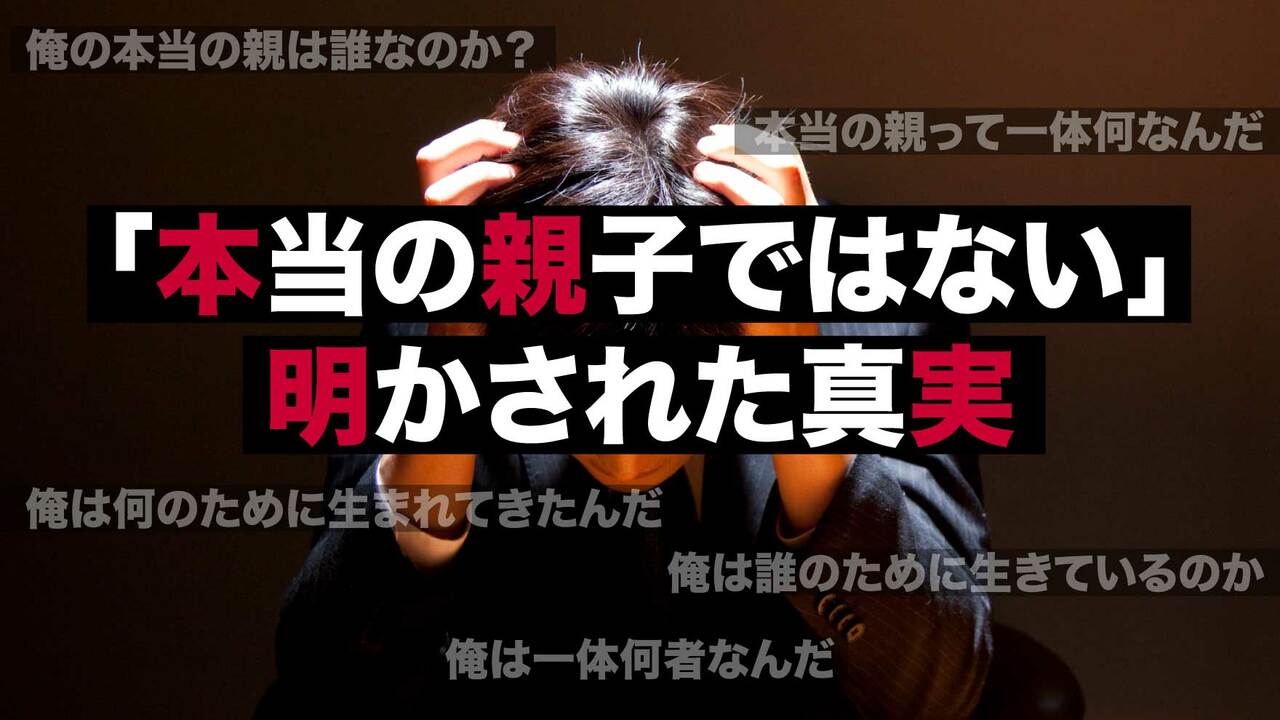矛盾と迷走
次の日曜日。
蓮は永吉とあおいに連れられて、市立の総合病院へ出かけた。日曜日のため受診する患者は殆どいなかった。病院の窓からは、その街で一番大きな川が眺められ、川のほとりにある芝生には子供たちがサッカーをする姿が、蓮の瞳に懐かしく映しだされていた。
「ねえ蓮君。この前のこと、お母さんに聞いてくれた?」
蓮はすっかり忘れていたあおいとの約束を、ふいに思い出した。
「宮﨑さん、中へどうぞ」
廊下で座っていた永吉と蓮は、二人で診察室に入った。
「じゃあ、私ここで待ってるわね」
「うん」
あおいは手を振って、二人が診察室に入るのを見送った。二人は中に入り、用意されていた椅子に座ると、早速、看護士が綿棒を口の中に入れて、唾液を採取した。
その後、検査の説明が看護士からあったが、蓮の耳には殆ど入ってこなかった。蓮はB型だと診断されたあの日のことを思い出していた。あの日も、こうやって看護士の前で、血液型の話をされたのだ。
「あなたの血液型は、B型ですよ」
事の発端は、看護士のその一言からだった。あの時、健康診断を受けていなければ、こんな不安に駆られることはなかったのだろうか。看護士の声は少しずつ遠ざかっていった。
家族って、なんなのだろうか。親子って、一体なんなのだろうか……。
数日後、結果は永吉の自宅に届いた。
「あおいちゃん、ポストに入っていたよ」
「あら、ありがと」
仕事から帰宅した永吉は、スーツの背広を脱ぎながら、郵便ポストに入っていた封筒をあおいに渡した。表紙には、「○○市総合病院」と記されている。
永吉は直ぐに、この前に蓮と二人で受けたDNA検査の結果だと気づいたが、やはり自分では開けるのをためらった。あおいは何の躊躇もなくはさみで封筒を開けて、中から三つ折りにされた一枚の紙を広げた。
「どうだって?」
「やっぱり」
あおいはその用紙を永吉に戻した。
「鑑定の結果、父と子の関係は否定されました……」
永吉は大きくため息をついた。
「やっぱりあの女、私たちを騙していたのよ。絶対そうだと思ったもの」
あおいの気持ちよりも永吉は、この結果を蓮に伝えなければならない事の方が気がめいっていた。
「まあ、これで証拠も揃ったことだし。あとは、弁護士に相談しようかしら」
あおいはキッチンに戻って、夕食の支度の続きをやり始めた。
「なあ、あおいちゃん」
「なあに?」
「やっぱり辞めないか? この話」
「え? どうして」