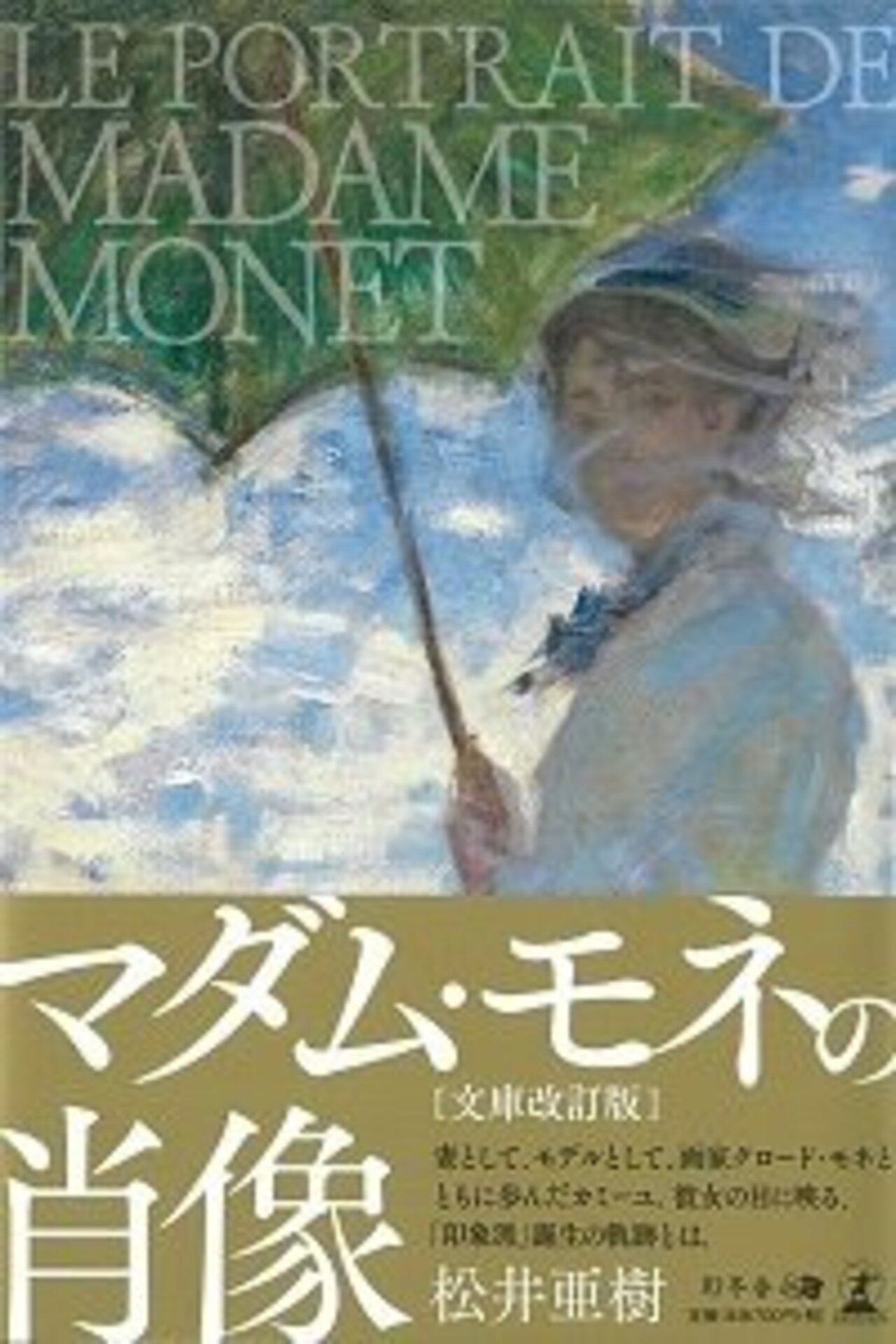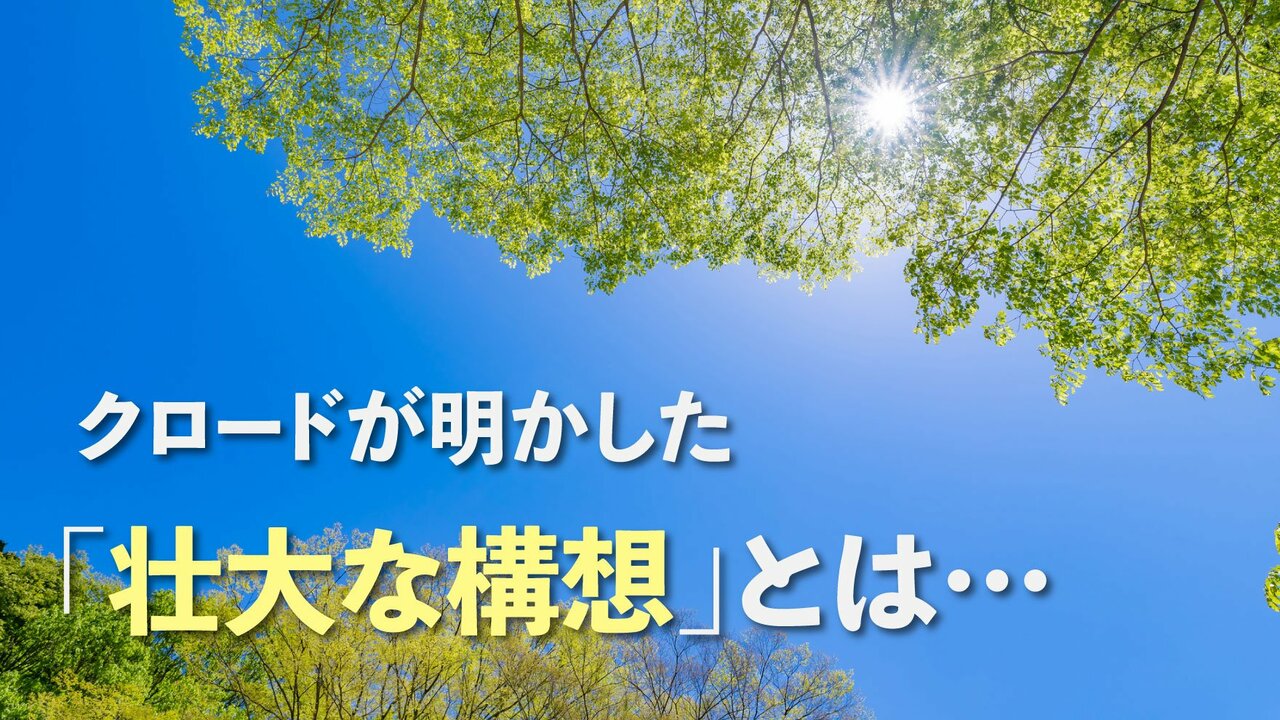ラクじゃない
二月最後の日曜、カミーユがアトリエに入っていくと、モネは別の作品に取り組んでいるところだった。
バジールはカミーユの耳元で小さく囁いた。
「クロードは今、サロン出品作を制作中なんだ。ああいう状態のときは声掛けても機嫌悪くてね」
しばらく口出しできないということらしい。今や世界に冠たる芸術国家。そう自負するこの国では、芸術家の育成・展示・表彰といった特権を独占する王立アカデミーが十七世紀半ばから存在した。
そのアカデミーがルーヴル宮殿のサロン・カレ(方形の間)で開催する公募による展覧会「サロン」は、さまざまな絵画や彫刻などを一堂に展示する唯一の大規模な美術展であり、画家にとっては自分の作品を世に出す唯一無二の場。
新聞や雑誌はこぞって出品作を論評し、その評価は画家の価値、すなわち作品の値段に直結した。
二十四歳のモネは、今年初めてサロンに出品するとかで、イーゼルを三つ立て、その二つに海を描いた作品を立て掛けていた。今朝はもうすでに、それらのキャンバスに向かっていたらしい。
「去年、一緒にノルマンディーに行ったんですよ。これはそのときスケッチしてきたものを作品化してるんです」
と、バジールが言った。
「うまいもんでしょう、クロードは。僕ら仲間うちじゃ抜群の腕前です。特に風景を描かせたら巨匠もびっくりだ」
心底誇らしげに言う。
「僕はモンペリエの出身でね」
バジールは、まだまだ時間が掛かりそうだと思ったのか、カミーユと自分用にカフェオレを運んでくると話し始めた。
「実家はワイン製造業を営んでいて、まあ、金には困ってない。最初は、医学を学ぶためにパリに出てきたんですよ。親父のたっての希望でね」
「まあ、医学を?」
それがどうして……。
「でも僕は、もともと絵が好きだったんです。子どものころはね、僕が絵を描くと両親だってよくほめてくれたもんです。せっかくパリに出してもらったのに、なかなか医学には打ち込めなくて、両親に内緒でノートル・ダム・デ・シャン街にあったシャルル・グレールのアトリエに出入りするようになってね。そこで出会ったのがクロードたちですよ」
バジールは、制作に夢中なモネを眺めながら、手にしていたカップに口を付けた。