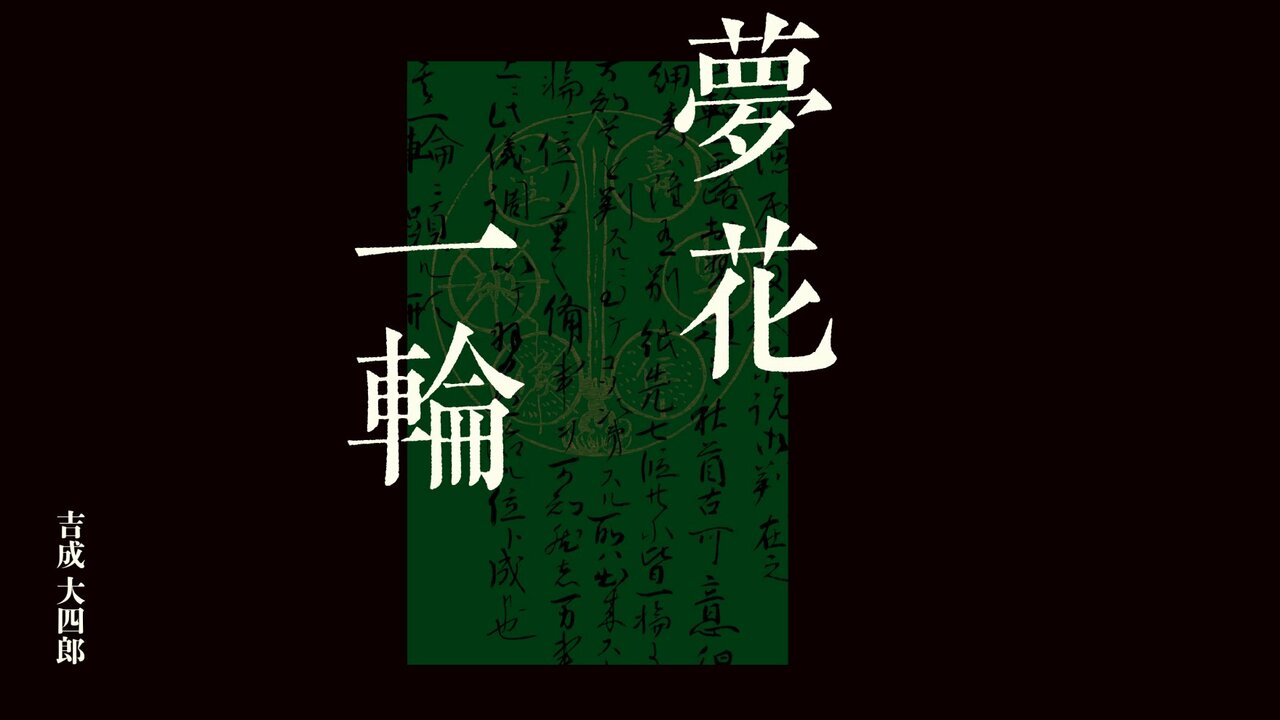一
弥三郎が足繁く観世の座へ通う内、三郎に替わって十郎が稽古を見てくれるようになった。弥三郎は嬉しく思いつつも、次第にある微妙な居心地の悪さを感じるようになっていた。
三郎はその時々の舞台に必要な稽古を徹底的にやるという、非常にわかりやすい方針で弥三郎を鍛えてくれたのだが、十郎は違った。十郎が主に教えてくれるのは、初心の者に学ばせるような、ごく基本的な型で構成された仕舞が多かった。
中には弥三郎もほとんど空で覚えているようなものもあったが、十郎はそれを事細かに、型の一つひとつの仕組みを解き明かすように、丁寧に教えてくれるのであった。
型には一つひとつ意味がある。弥三郎はそんな風に思うようになった。型の意味とは、月を見たり、喜びを表したり、そういう型ももちろんあるのだが、それだけではない。舞全体の中で、その型がそこにある意味、ある型からその型へ、そして次の型へとつないでゆくその流れ、それが舞の流れを作り、舞全体の姿を形作っていく。
それを意識すれば、型への入り方も、次の型へのつなぎ方も通り一遍ではいられなくなる。その舞の中のその型の、こうでなくてはならぬという姿があることに、目を開かされたのである。
それは三郎が口癖のように言う、序破急(じょはきゅう)というものに大きく関わることのように思えた。
「序破急をつけろ」「序破急がない」と、三郎が謎のように投げかける序破急という言葉を、十郎はそれと言わずに柔らかく解きほぐして教えてくれているような、そんな気が弥三郎にはするのであった。
これは、ものすごく大事なことを教えてもらっているのではないだろうか。弥三郎は次第にそんな風に思うようになった。そしてそのことが、段々と重荷に感じられるようになってくるのだった。不思議なことであった。
十郎の態度には押しつけがましいところが微塵(みじん)も無い。純粋に能を教えるのが楽しく、弥三郎がそれを吸収して成長するのが嬉しいと心底から思っているのがわかるのだ。それなのに、弥三郎の方にはどこか疚(やま)しいような気持ちが兆(きざ)している。
同じ大和猿楽の仲間とはいえ、結崎と円満井という別々の座に属する者どうし、言わば競争相手である。立合の能ともなれば奥の手は隠しておいて、いかに相手を出し抜くかに心を傾ける、それが当たり前のことだと思っている。
そのことと、十郎から寄せられる好意の大きさが弥三郎の中で折り合わず、何か大きな借りをつくっているような、そんな気持ちになってしまっているのであった。