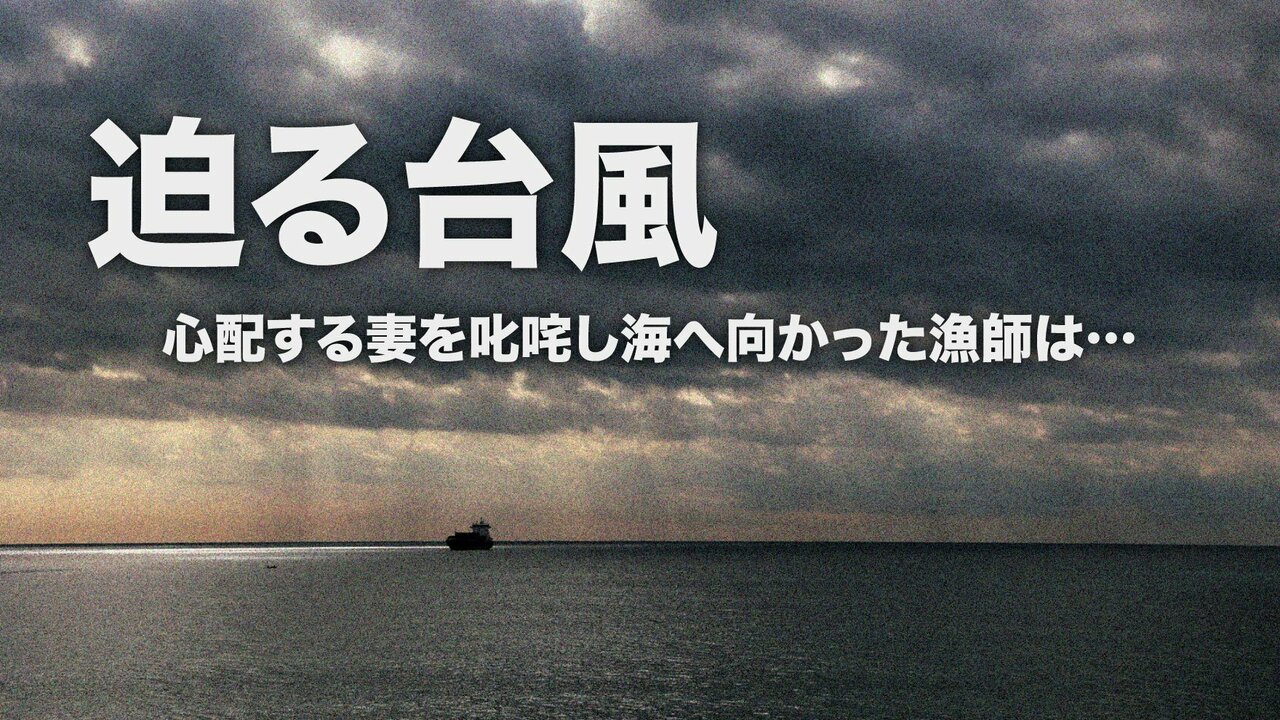幹也は授業があまりわからないことに焦りを持っており、母が帰るまで炬燵で教科書を広げるのを日課にしていた。冬休みに入ってもそれは同じで母の出勤したあとは遅れを取り戻そうとひたすら勉強に励んだ。
「ほな、お母さん、行ってくるわ。お昼は冷蔵庫に入れてあるで、レンジでチンして食べて」
朝食の後片づけが終わったあと、そんな言葉を残して出勤していく雅代を幹也は、毎朝既に教科書が積まれている炬燵の中で見送った。
大阪は都会であり田舎出の幹也には物珍しいものが沢山あったが、一人で街に出るのは心細く、また、勉強が気に掛かりそれほど出たいとも思わなかった。
それに志摩の事件以来、なぜか自分のような者は世間のあれこれに積極的に関わってはいけないと思うような気持ちもあったからだった。
冬休みの頑張りが功を奏したのか三学期からの授業はついていけないということはなくなったが、まだ遅れを感じていた。授業での焦りと悔しさ、さらには、仕事で出ている母のいない寂しさを幹也は勉強にぶつけた。
国語、算数、社会など科目を選ばず教科書や副教科書などを舐めるようにして覚えた。社会科の授業の時間だった。担任教師が大分県の農業特産物を質問した。
クラスの幾人が手を挙げた。手を挙げたのは塾に通い成績の優秀な者ばかりだった。幹也も手を挙げたがそんなことは初めてだった。
「おっ! 転校生が手を挙げてるやん。間違えんときや」
誰かがそう囃した。クラスに冷笑が起こった。幹也は恥ずかしさのあまり頭に血がのぼりすぐに挙げた手を引っ込めた。しかし、担任教師は幹也を指名した。
幹也は立ち上がり少し恥ずかしげに生産高日本一の特産物を三点ほど言った。勉強の成果というよりスーパーマーケットで各地から集まってくる生鮮食料のレジを打つ母からの受け売りだった。
担任はよく知っていますねと褒めてくれた。