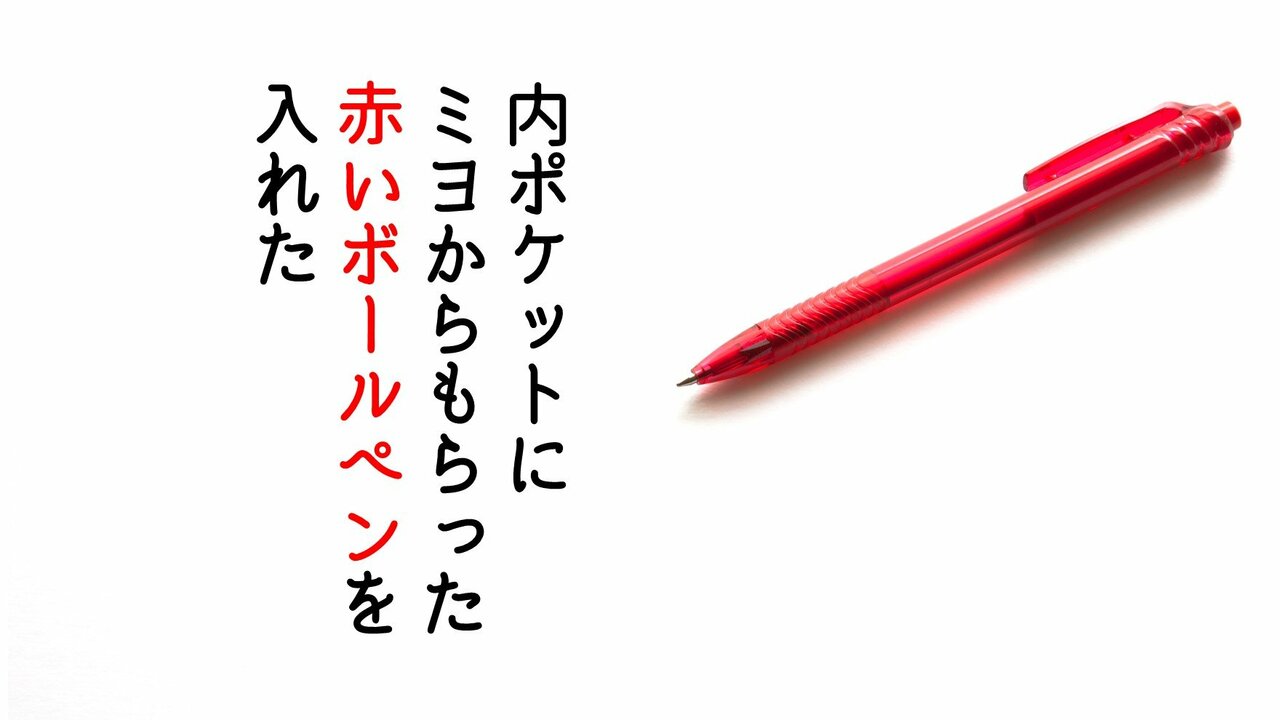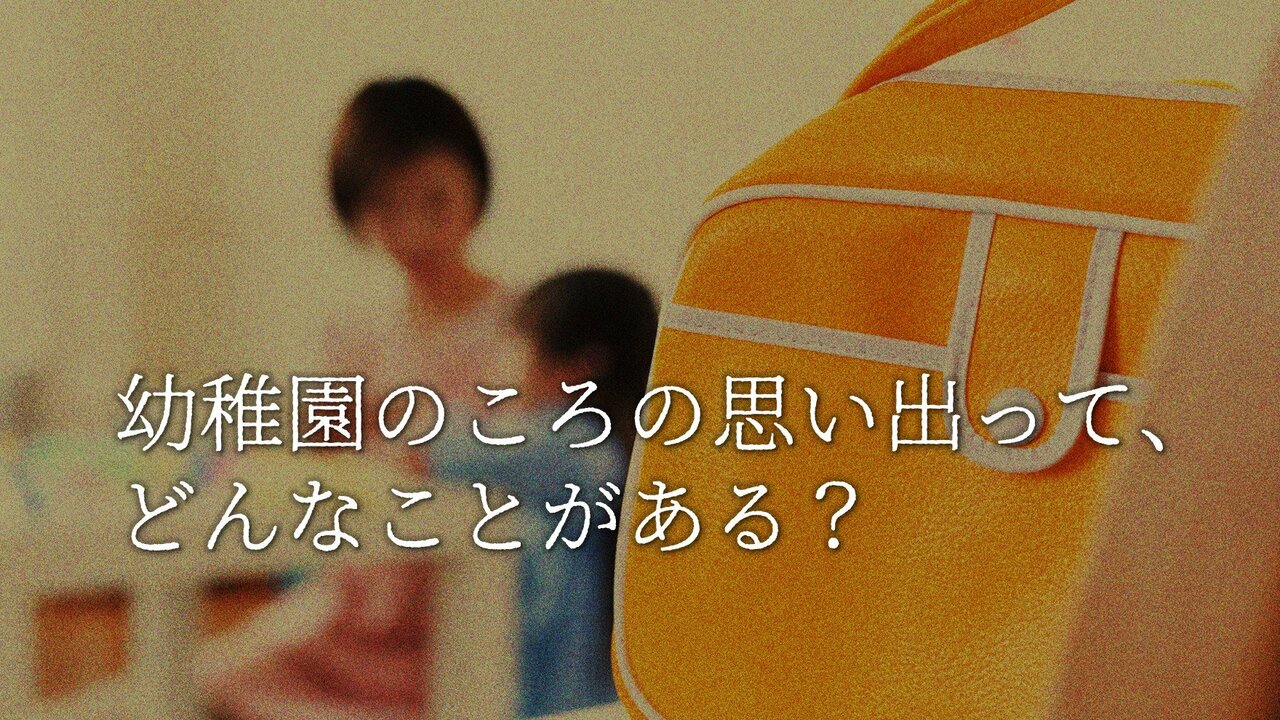第一章 赤い光
「お前、携帯持ってないのか? これから必要な時に、お兄さんたちにお金持ってきてもらわないとな。ママの財布からパクってくりゃあ簡単だろう?」
「さぁ、教えろよ。携帯の番号をよ」
「教えろよ」
三人の男は口々に繰り返しながら、達也を蹴り続けた。
「……教えてください」
「あぁん?」
男たちは顔を見合わせた。達也はなんとか体を起こし立ちあがった。
「……教えてくれって言ってんだよ」
達也は下腹を押さえながら、ふらふらと男たちに詰め寄った。
「なんだ? コイツ。イカレちまったんじゃねえか?」
「教えてくれよ。たとえ勉強しても僕はお前らみたいになってしまうのか? 兄さんみたいになれない僕は……僕はどうしたらいいんだよ!」
「わけわかんねぇこと言ってねぇで、さっさと携帯の番号教えろよ!」
「教えてほしいのはこっちなんだよ! どうしていつも僕ばかり……僕はどうしたらいいんだよ! なあ、教えてくれよ。大学に入れるほど、今までたくさん勉強してきたんだろ? 僕はなんのために勉強するんだ? どうすればいいんだよ!」
達也はリーダー格の男の腕をつかみ声を張りあげた。今まで積もりに積もっていた怒りが爆発していく。
「離せ、コイツ。キモイんだよ! おい、もう少しヤキ入れてから帰るとしようぜ」
三人は顔を見合わせ、また達也を蹴りはじめた。
「や……やめて……」
意識が遠のき視界がぼやけはじめたその時、赤い光がにじむように見えた。スーツ姿らしき男性がこちらへ走ってくるのも、かすかに見える。
「何をしてる!」
「やべっ、逃げるぞ!」
達也は安堵の闇へと落ちていった。どこだろう、ここは。気づくといつの間にか暗闇の中に横たわっていた。目を凝らして
辺りを見回しても何も見えない。
体を起こして、おそるおそる周囲に手を伸ばしても触れるものは何もない。大声をあげてみる。母親の名。父親の名。兄の名。祖父母の名。学校の先生の名。友達の名。そして自分の名さえも叫んだ。
何も反応がない。無音の空間をひたすら走った。
どこへ行っても、どこまで行っても何もない。
たしかに自分は「ココ」に存在しているのに、自分の存在をたしかなものとする術がない。
自分は、「無」。
漆黒の天を仰いで嘆息した。
すると先ほどまではなかった赤い光が、上空に輝き出した。
安堵の吐息をもらした時、赤い光のまばゆさに思わず目を閉じた。優しく何かに包まれていく心地よさ。いつまでもこうしていたいと思っていると、遠くで何か聞こえてきた。
何だろう。あれは、声。人の声だ。達也は自分を呼ぶ声の方へと、導かれていった。
達也は目を開いた。白い天井がゆっくりと広がった。視線を移すと、心配そうに達也を見つめる父と母の姿があった。
「ああ……達也、よかった」
「達也、わかるか? 父さんと母さんだ」
両親が顔を見合わせて笑みを浮かべている。
「ここ……は?」
「塾の近くの信州(しんしゅう)中央病院よ。あなた、塾の帰りに悪い奴らに襲われてね」
母が布団をゆっくりとかけ直す。
「そこを助けてくださった方がいたの。打撲はひどいけれど、幸いほかに異常はないみたい。今晩はゆっくり休むのよ、達也。お医者さんも、このまま安静にって」
達也の頭を優しく撫でる。
「こんなにひどい目にあったのに、意識が戻る前のあなた、なんだか落ち着いた表情していたのよ。どんな夢を見ていたのかしらね、この子は。こっちは心配で心配でたまらないっていうのに。本当に呑気なんだから
母の目に涙が浮かんでいる。
何も考えられなかった。達也はただ、白い天井を見つめている。
「塾、辞めたい」
そうつぶやくと、やがて達也は深い眠りに落ちていった。