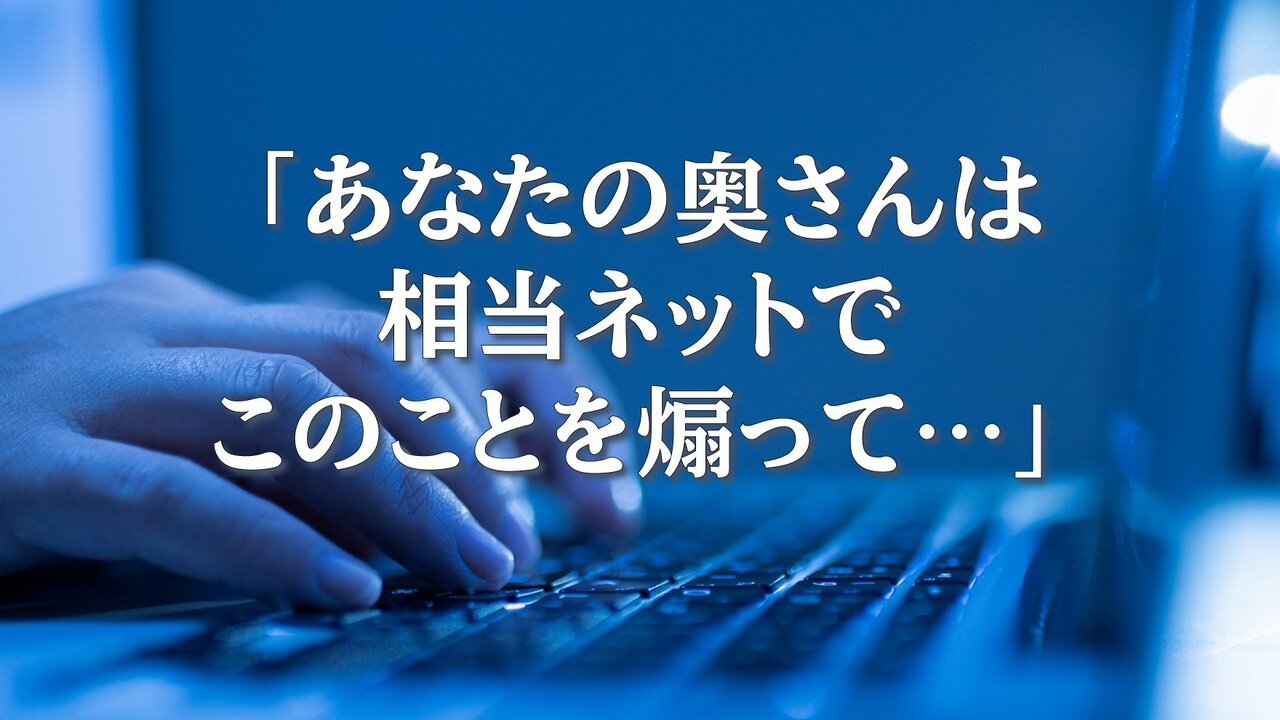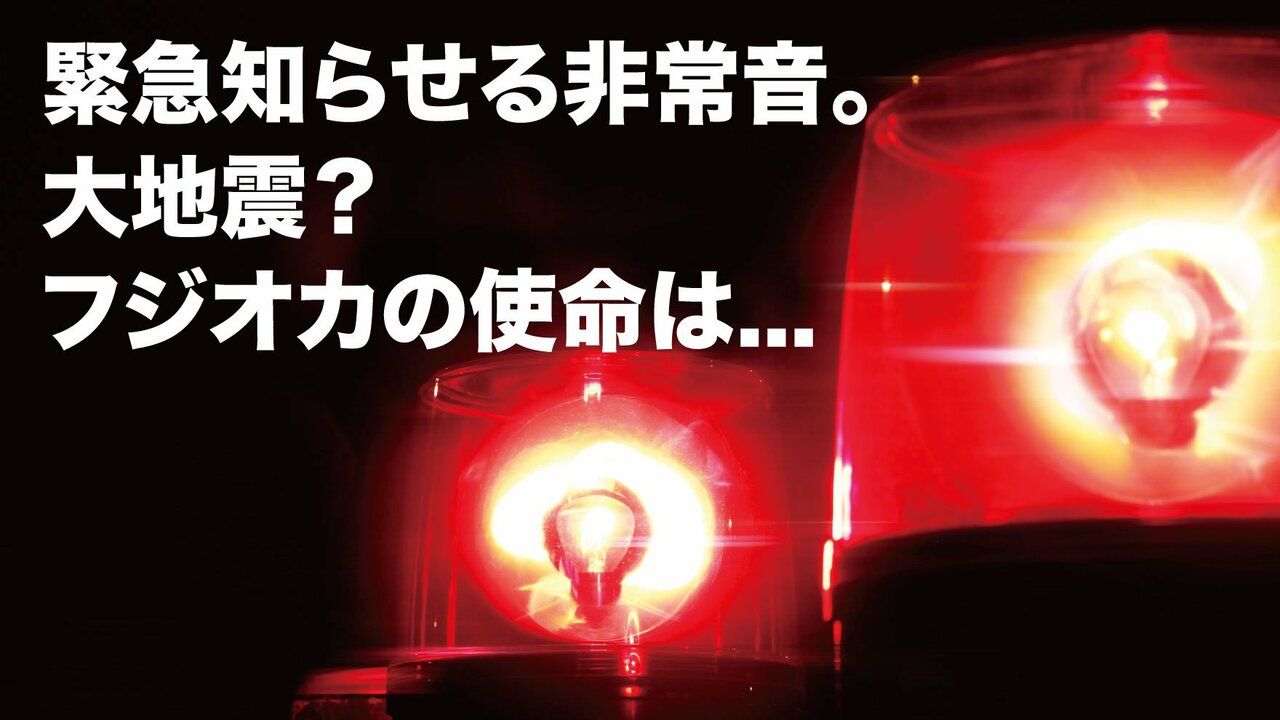須戸麗花は急に険しい口調になり、
「別にあなたに対して怨みがあるわけじゃない。ただあなたの奥さんは相当ネットでこのことを煽って、父を精神的に追い込んだそうだがな」
「……」
「だからというわけでもないが、あなたには話す義務があるように思うんだが」
吉岡吾郎は、重い口を開く。
「まあ、あっしも今も、『アニオタ病を支援する会』から支援をいただいている身で、それで刑務所の中でも比較的いい思いができてるわけなんですけどね。……で、何を知りたいんで?」
「吉岡家に起こった不幸の背景。あなたの奥さんを死神湖というモンスターにしてしまった本当の原因はなんなのか」
「原因……といっても、ねえ」
吉岡吾郎はゆっくりと、自分の生い立ちから語り始める。
「もともとは妻とは、半分見合いだか紹介みたいなことで、妻の父親の経営する自動車修理会社にそのまま就職しました。三十代のころ、会社の資金繰りが悪くなり経営者が代わり、私も失職せざるを得なくなりました。
その当時、『Iターン』っていうんですかねえ、北海道の農業経営の募集があって、申し込んだんですが、行ってみると話とは大違いで。農地もほとんど荒地みたいな土地で、廃屋みたいな家にはとても住めそうになかったので、石を運んで一から建て直しました。
『共済会』という古いしきたりの組織が仕切っている村で、共済会の機嫌を損ねたらゴミを出すこともできませんでした。妻も息子も事あるごとに様々な嫌がらせを受け、家族は次第に心を病んでいきました。息子の純が『アニオタ病』という奇病にかかってからは差別はますますひどくなっていきました。そこにあの事件です。あとはまあ、お嬢さんのご存じの通りで」
「あなたの奥さんは、いつごろからあのサイトというか、ああいうことをやり出したんですか」
「ああ、あれはまあ『アニオタ病を支援する会』の西崎なにがしに利用されたんでしょう。息子がああいう目に遭ってからは、もう復讐の鬼のようになってましたから」
「大体は分かりました。お話ししにくいこともお話しいただいてありがとうございました」
「ねえ、お嬢さん」
「なんですか?」
吉岡吾郎は、遠くを見る様な目つきで言った。
「人間ってえのは、なんですかねえ。不幸なもんは、生まれつき不幸になる様にできてるんですかねえ」
「それは私にはわかりません」
「あんたのような、賢くて財力もありそうな方々が、貧乏人を救ってくれるような世の中にしてはくれないんですかねえ。貧乏人は夢も見ちゃいけないんですかねえ」
「発明や、科学の進歩で世の中が良くなることはあると思います。例えば『洗濯機』や『掃除機』なんかで家庭の主婦の家事労働は軽減されてきたと思います。ただ、それを羨んだり、阻んだりするなんらかの意思が、必ず出てきます。姑さんや近所の目を気にして、あるいは自分が夫に楽をしていると思われたくなくて、そういう便利な道具を使うことができなかった奥さんは、たくさんいたんじゃないですか」
「ウチの家も最初は電気もなかったですねえ……」
「それは一つの例です。石油に代わるエネルギーなどはとっくに発見されているんですが、すでに利権を持っていてその実用性を阻む勢力が存在します。この世から妬み・嫉みなどの悪意がなくならない限り、足の引っ張り合いみたいなことはなくならないのではないでしょうか」
「悪意がまた新しい悪意を生む。まるでウチの妻が今やってることのようですな……」
「吉岡、時間だ。出ろ」
吉岡が連れていかれる。
「吾郎さん、あんたの息子さんだけど」
「ああ、ロシアのどっかで野垂れ死んじまったそうですがね」
「生きてるぞ」
「ええ? 今何をおっしゃったんで?」
「今、ワタシのすぐそばにいる。顔はすっかり変えられてしまってるらしいが、元気にしているぞ」
吉岡吾郎は全く訳が分からず、名残り惜しそうに麗花のことを振り返り、振り返り見ていた。
「……それはきっと、何かの間違いだな」
吉岡吾郎は低く呟いた。