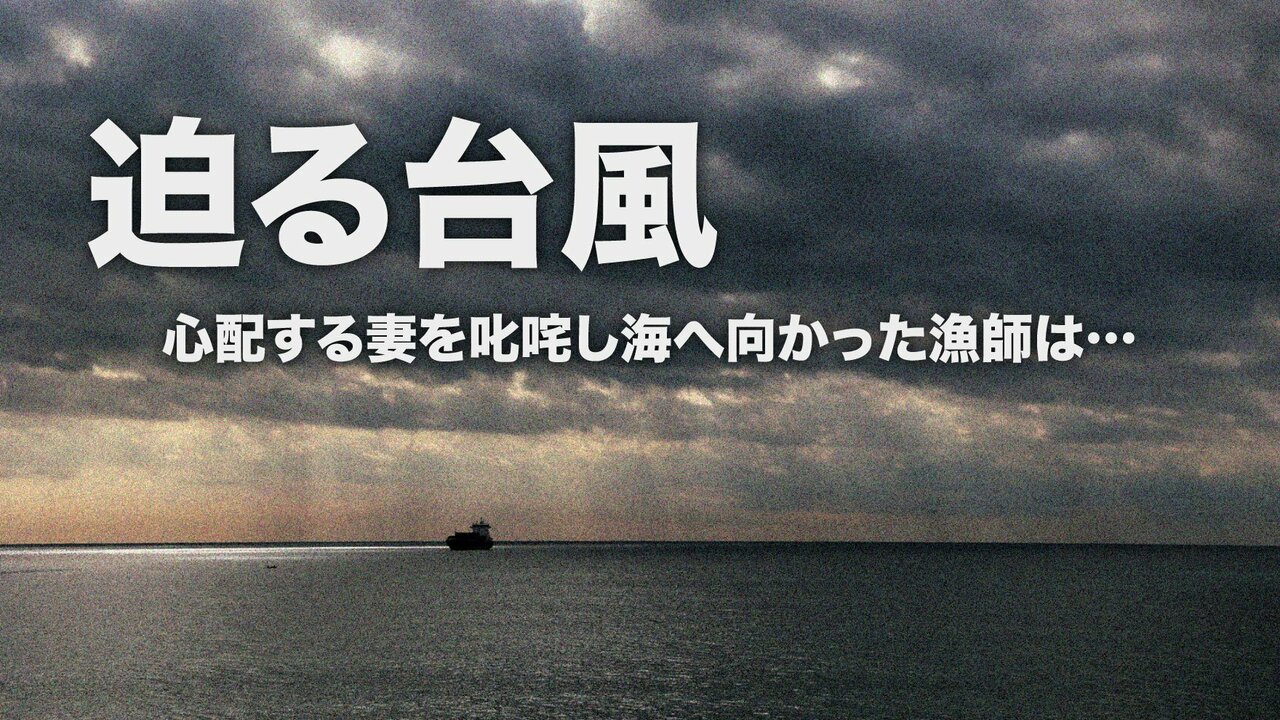「ここへ来るにはあんたらも調べて来たと思うが、あの子には母親が出て行っておらへん。そやけどな、片親ながら儂が立派に親をしとる。叩く躾も愛情の裏返しじゃ。あんたらに言われんでも幹也とはキチンと愛情の絆で繋がっとるわ。手が足らんので掃除や洗濯は満足にできへんが、息子には三度三度食べさせ、ちゃんと着るものは着せとるわい!」
そう言って逸男は頑なに虐待していることを認めなかった。子に着せて食べさせる。育児の基本である。未熟な父性の悲しさか人の成長にはそれだけでは足らないものがあることにこの父親は気づいていない。
上原は逸男の言葉をそんな風に受け取った。逸男は、あの事件以来、漁の仕事に家事に育児にと一人三役を熟して来た疲れが重なり、苛立つことが多くなっていた。
それに加えて自分を嘲るような世間の視線にもずっと耐えている精神的な負担もあった。つらく思う度に逸男は身勝手なことをして家を出た嫁を恨んだ。
「あの女だ。あの女が俺を裏切り、俺の人生を狂わせた」
そう思うと無性に腹が立ち、心の守ができずに酒に逃げた。日毎に酒の量は増えていき明日の漁に差し障ることも構わずに飲むこともあった。
酔うと目元の似ている幹也があの女に見えてくる。酔いに任せて憂さを晴らすかのようにただ似ているという理由だけで何の罪も無い幹也を捕まえては叩いた。
しかし、覚めれば後悔の念に駆られた。逸男は弱い立場の子供につい当たってしまっていることを自覚していた。そのことに悩んでもいた。
しかし、今日の家庭訪問でそんな気持ちは言葉には出さなかった。
自分の前に並んだのがすべて女であり、これ以上世間の女どもに馬鹿にされて堪るかとの思いが胸に蟠ったからだった。
幾度かの実りの無い押し問答を繰り返し、女性職員と担任教師は溜息を吐きながら帰って行った。
それでも家庭訪問が少しは功を奏したのか、二か月ほどは虐めもなくなり新たな痣はなかった。
しかし、幹也の腕にまた新しい痣ができ始めた。児童相談所は警察にでも協力を求めたのか新しい保護者として大阪にいるという幹也の母を探し出した。
親権がどうのこうのと逸男と揉めはしたが、どう話をつけたものか幹也は母親に引き取られ大阪に転校することになった。
美紀は、幹也とはそれほど口を利いたわけではなかったが、教室の後ろ、校庭の片隅、授業の間の休みの廊下など学校ではその姿は当然のように美紀の視線に触れることができた。
しかし、幹也が大阪に転校していって十日も経つと美紀の視線の中に幹也の姿が無いことに意識が巡り、寂しさを感じて切なかった。