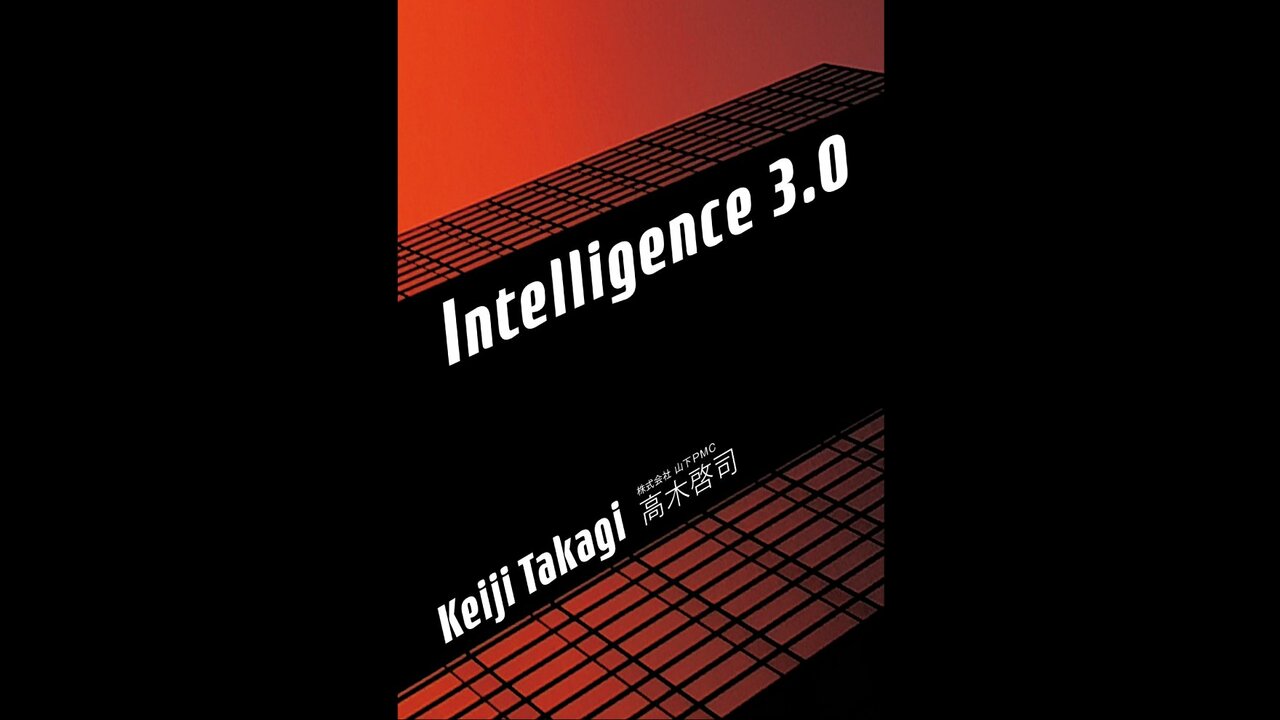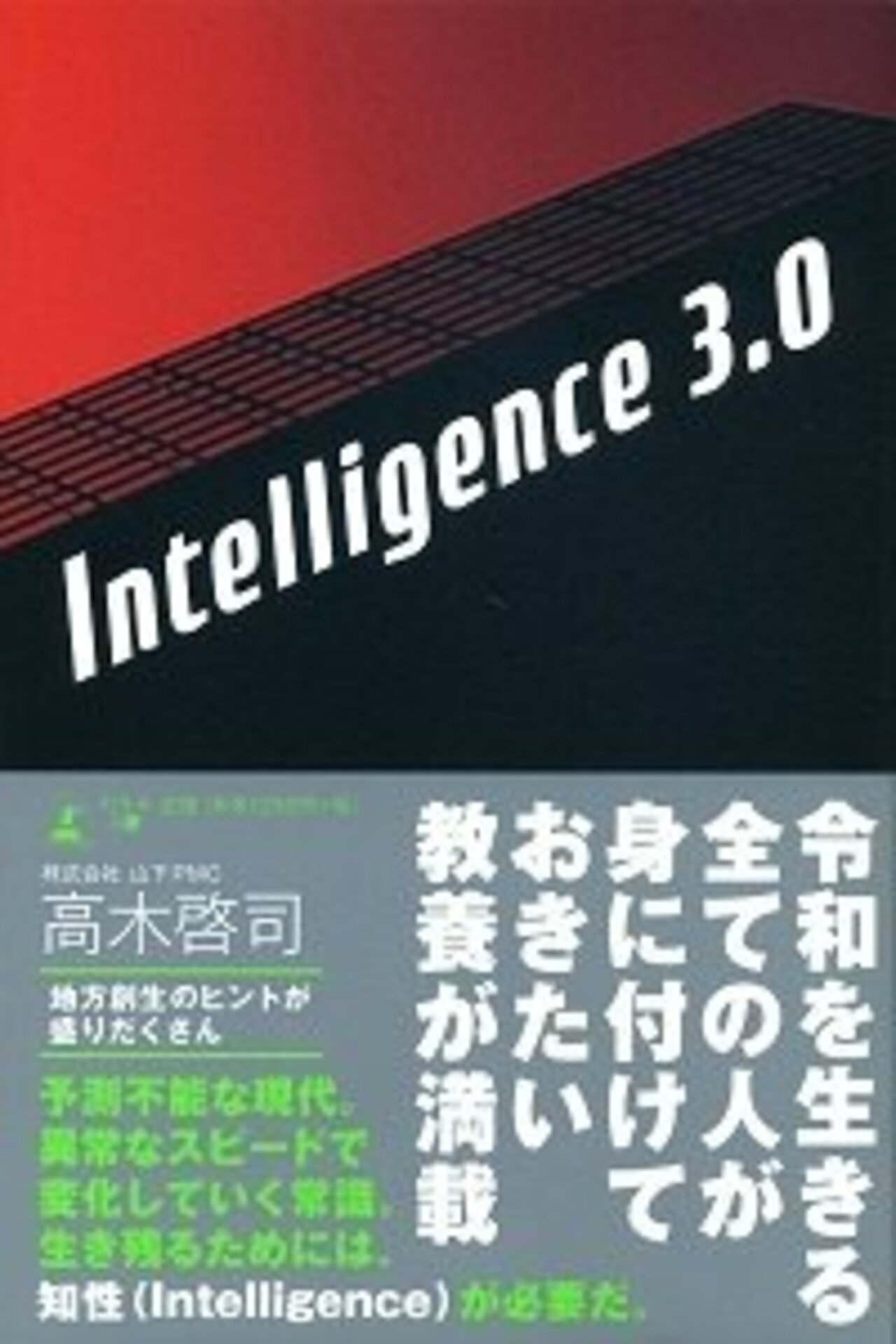紀貫之と日本語の欠陥
ある店でかつて、知人2人が私の目の前で繰り広げた会話です。
A「あなたみたいなブスは見たことがないわ。少しぐらい見かけが良いと思っていい気になっているみたいだけど、中身が空っぽなことがわからないの」
B「何よ、女性に向かってそんなこと言うなんて。あなたの方こそ最低の男ね!」
A「あら、だってあたしオンナだもの。前から言っているでしょ」
後日、Bさんは私にこう言いました。
「あんなに私にはっきりと意見を言ってくれた男の人は、あの人が初めてだった。2人で会いたい」
その旨を、Aに伝えると
「私はオンナだって言っているのに、まだわからないのかしら。そんなことより、あなたを連れて行きたい店があるんだけど。そこは男だけしか入れないのよ」
「あなたは見かけだけ」
男性が女性に対して面と向かって言うセリフとしてはなかなか刺戟的です。
冒頭の女性Bさんの発言「男のくせに……」は大勢がいる場での女性への罵倒に対しては正当な感じもしますが、「あら、だってあたしオンナだもの。……」はその文脈という防御壁を破壊し、それが故にBさんの心にグサリと突き刺さります。
そして後日、Bさんは私を通して、以前の会話を男女関係の文脈に再回収しようと試みたのです。Aは、その再回収を拒絶し、自分のポジションを私に対し再確認します。自分はオンナだと主張するのになぜ、男しか入れない店に2人で向かうのか。
今のLGBTという言い方がなかった時代のことですが、私の飲み友達でもあったAは、有名なゲイバーで「男役」として人気がありました。
男なのに男役という複雑な役回りは私生活でもあまり変わらず、しばしば女性に対して容赦ない口撃を与え、このような騒ぎを起こしては面白半分に私を巻き込むことが度々ありました。
さて、冒頭に挙げたような会話は、ジェンダー間の言葉のフレームワークをずらしたり無効化したりしながら、普段は表現できない内面性を見せたり隠したりする言葉のゲームとも言えます。
私はここに、「男言葉」「女言葉」のそれぞれに固有のニュアンスやルールが紐づいているという、日本の言語文化のバックボーンを感じます。