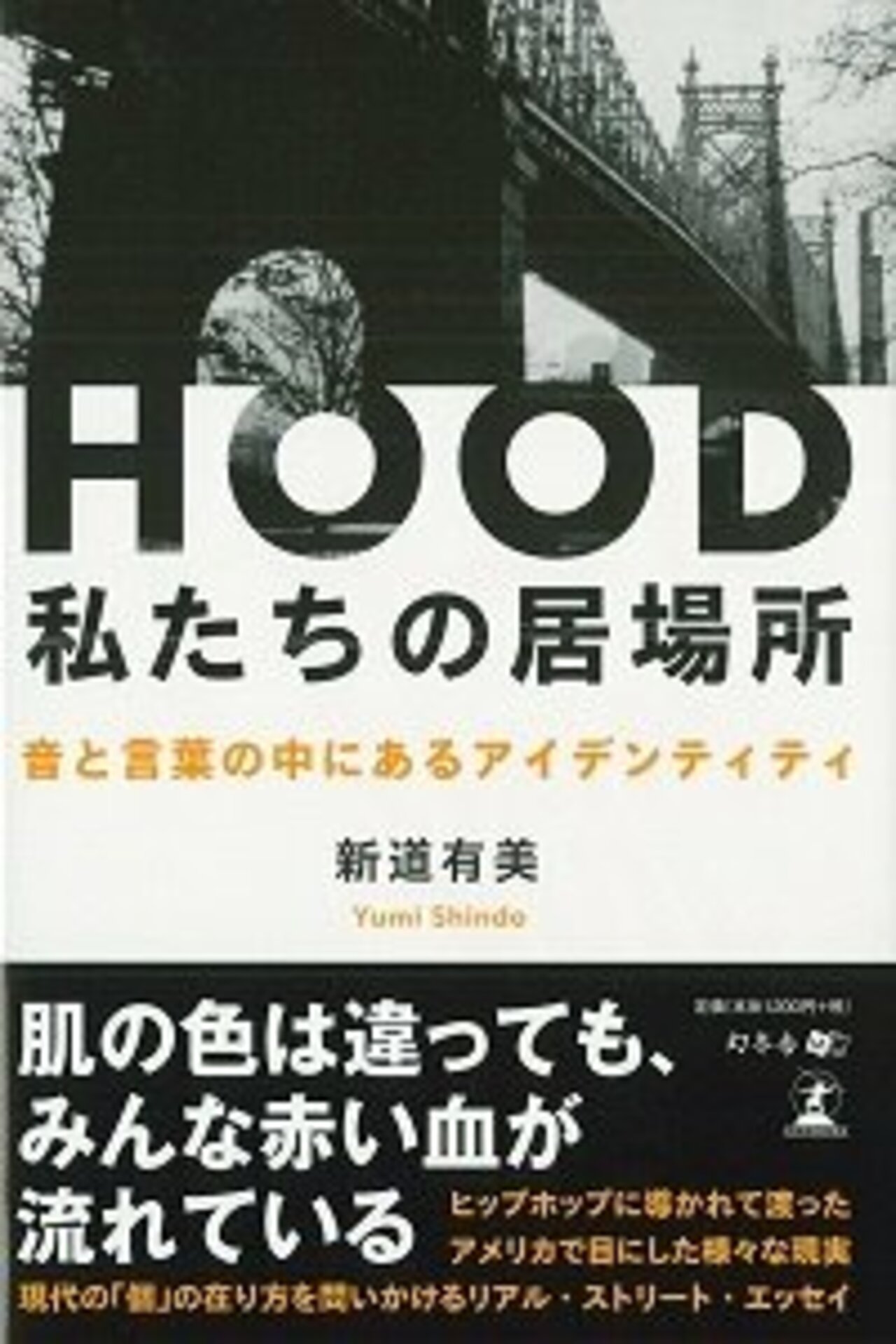四六時中ハイになる
いつの間にか辺りは真っ暗だ。新たに仲間が加わり、4人で酒を買いに行くことになった。ドレッドは公園で待つという。
急に風が強くなってきた。
「着ろよ」
スキンヘッドが真っ青なパーカーを貸してくれた。
私たちは公園を抜け、ストリートへと出た。一人で歩いていると見えなかったものが見えたり、聞こえなかった音が聞こえてくるような気持ちになる。ストリートで生きる人間はまわりの状況に非常に敏感だ。
彼らには暗闇の中でも、さまざまなものが見えるのだ。少しでも人の気配を感じると話を止める。少しの物音や、暗闇にかすかに浮かぶ人影、においさえも逃さない。鋭い五感を用いて、いま自分たちのまわりで起きている状況を把握しようとするのだ。誰かがストリートを歩いていれば、どんなに遠くにいようと、その人間が何者かを確認することがストリートの常識である。
「あいつはオレの仲間の○○だ」
「あいつらは隣のブロックの××だぜ」
Liquor Storeまでの数ブロックの間に彼らは何度か足を止めた。また、相手も私たちの存在に気付き、同様に私たちが敵か味方かどうかを峻別しているのだ。
Liquor Store に着いた。その横にはDeliがある。店の明かりにストリートが照らし出され、散乱したゴミが目に入った。
店付近は、どうやら彼らの溜まり場となっているようだ。“Yo, whut up?”彼らはストリートでたむろする仲間と一人ひとり挨拶を交わす。ここが、彼らにとって単なる居場所ではなく、その他の目的を通じて、集まって来ている場所であるということも、彼らの目付きや態度から容易にわかった。
Liquor Storeの横に背が高く、がっしりとした体型の男性が立っている。非常に鋭い目をした強面の男性である。太いゴールドのチェーンを首から下げている。
「オレの兄貴」チャビが言った。
“Hi. I’m Yumi.”私は笑顔で手を差し伸べた。彼は一瞬、目線を下に向けたが、またすぐにストリートに視線を戻した。その目には全く隙がない。彼は表情を一つ変えず、獲物を狙うかのように、ただ遠くを見ている。声をかけても微動だにせず、無反応だ。
「俺から放れろ」。無言で彼がそう言っているように感じられた。
仲間の一人、ダークスキンの黒人男性(以下、チョコレート)が、腹が減ったと言ってデリに駆け込む。一分も経たないうちに店から出て来たかと思えば、菓子パンの袋を歯で乱暴に食いちぎって開け、大きな口でパンを頬張った。ゴミはそのままストリートに投げ捨てられた。
私たちは酒や菓子を買い込み、公園へ戻ることにした。途中、スキンヘッドとチャビが前方を歩いている一人の男性を指差し、こう言った。
「あいつ、すっげークレイジーなんだぜ」
「どうして?」
「頭がイカレてる。コカイン常習者だ」
「それって悲しいよね。身体が心配だよ」
「心配?? 冗談じゃねーよ。クレイジーだよ。いつもオレらに媚び売って、ヤクをくれってすがってくるんだぜ。マジ、気持ちわりーよ。」
その男性は足取りも弱く、静かにストリートを歩いていたが、やがて暗闇に消えた。
相変わらず大木のようにどっしりとベンチに腰をかけたドレッドの姿が見える。
「奥の公園に移動しようぜ。」