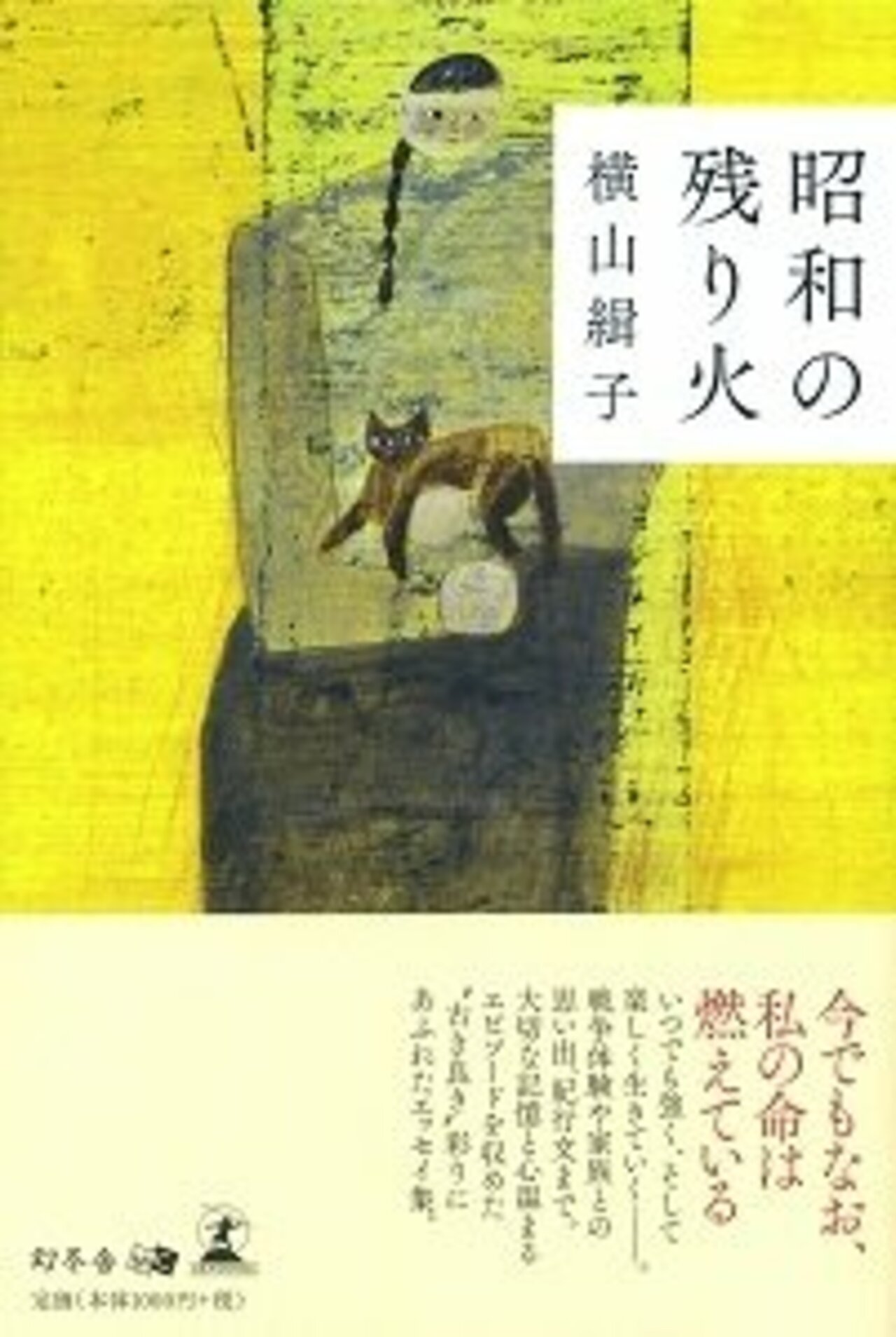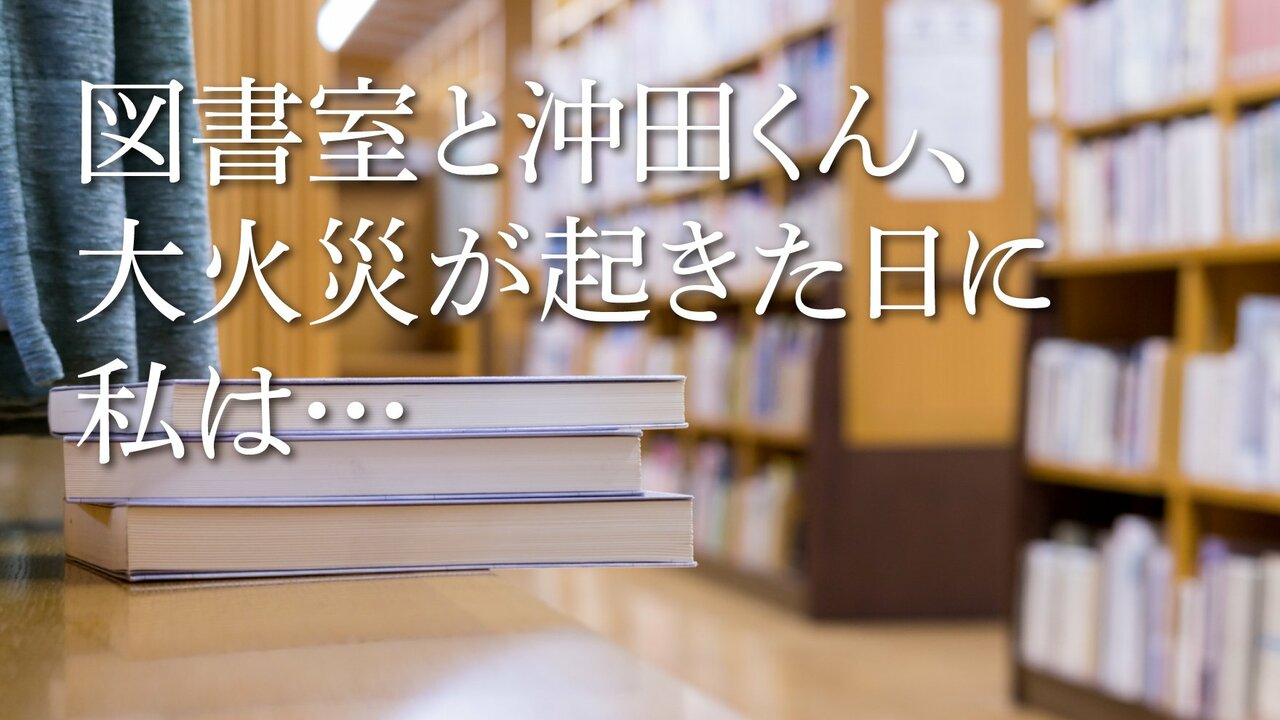二人とも同じ中学に上がり、また同じクラスになった。小学校の頃は男子も女子も隔てなく話をしていたのに、中学生になるとまるで見えない壁が間にあるかのように互いを無視した。それでいて陰では男子のことをあれやこれやと話のタネにして面白がった。沖田くんが急に背が高くなったというのも、そんな話題の一つだった。
中学校は武家屋敷の跡にあり、古びてはいるが大層な武家門をくぐって登校した。
門の左右に白壁と格子窓の、かつての侍詰所があって、左側の狭い部屋が図書室に当てられていた。窓越しに入ってくる光は乏しくて薄暗かったが、外の音がくぐもって聞こえる空間が私は気に入っていた。
山陰の秋は短く、運動会も早々と終わった。その頃出版されたばかりの『ドリトル先生』シリーズを見つけて、放課後にせっせと図書館に通うようになった。
気がつくと、沖田くんがいた。沖田くんは、いつも理科のコーナーで図鑑のような分厚い本を広げて読みふけり、私には目もくれなかった。
十五、六人も入れば満員になる室内である。一旦気になりだすと、いやでも目についた。入口の重い引き戸を開けると、まず来ているかどうか目を走らせる。いない日は何か拍子抜けした気分で、本の面白さも半減した。
一年の秋と冬はそんなふうにして過ぎた。
二年生になって間もない昭和二十七年四月十七日、午後のまだ早い時刻にその大火災は始まった。
鳥取駅近くで使っていたドリルが過熱して発火したとか、蒸気機関車から飛んだ火が民家に燃え移ったなどと言われたが、原因は分からず終いだった。小さな火種が折からのフェーン現象による強風に煽られてあっという間に燃え広がり、市街地の半分近くを焼き尽くしたのだ。
私の家は久松山の裾にあったので、駅からは大分距離があった。
学校から帰って、いつものようにおやつを食べていると、父から電話がかかってきた。
電話を切った母が慌てたように言った。
「大変、駅のほうで火事が広がっているのよ。お父さんは帰ってこられないから、万が一の用意をしておくようにって」
「えーっ、煙も見えんし、音もせえへんのにぃ?」
「そんなこと言ってないで、あんたはお姉ちゃんなんだからしっかりしてちょうだい」
私の下に小さい妹や弟が三人いた。
しばらくすると家の前の道に、家財を積んだ大八車やリヤカーを引いたり、大きな荷物を背負ったりした人たちが次から次へと現れるようになった。
メガホンで「二階町は全焼しました」などと連呼する声も聞こえた。
暮れかかる頃そそくさと夕飯をすませ、母はおにぎりを作った。乳母車に必要なものを積み込んで避難に備えた。
日が落ちても空は夕焼けのように赤く、二階に上がると炎が見えた。それはときどきぱっと高く上がったかと思うと、風に煽られて横に大きくなびいた。むっとする熱い風がこちらにも渦を巻いて吹きつける。燃えカスも飛んできた。
記録によれば、その日は気温二十五度、湿度二十八パーセント、最大瞬間風速は十五メートルにも達していた。
避難してくる人の数はますます増えた。二軒ほど先の広い丁字路は人でいっぱいになった。私は二階と玄関先を忙しく行き来して、逐一母に報告した。
そんな時、前の道に沖田くんが現れたのだ。