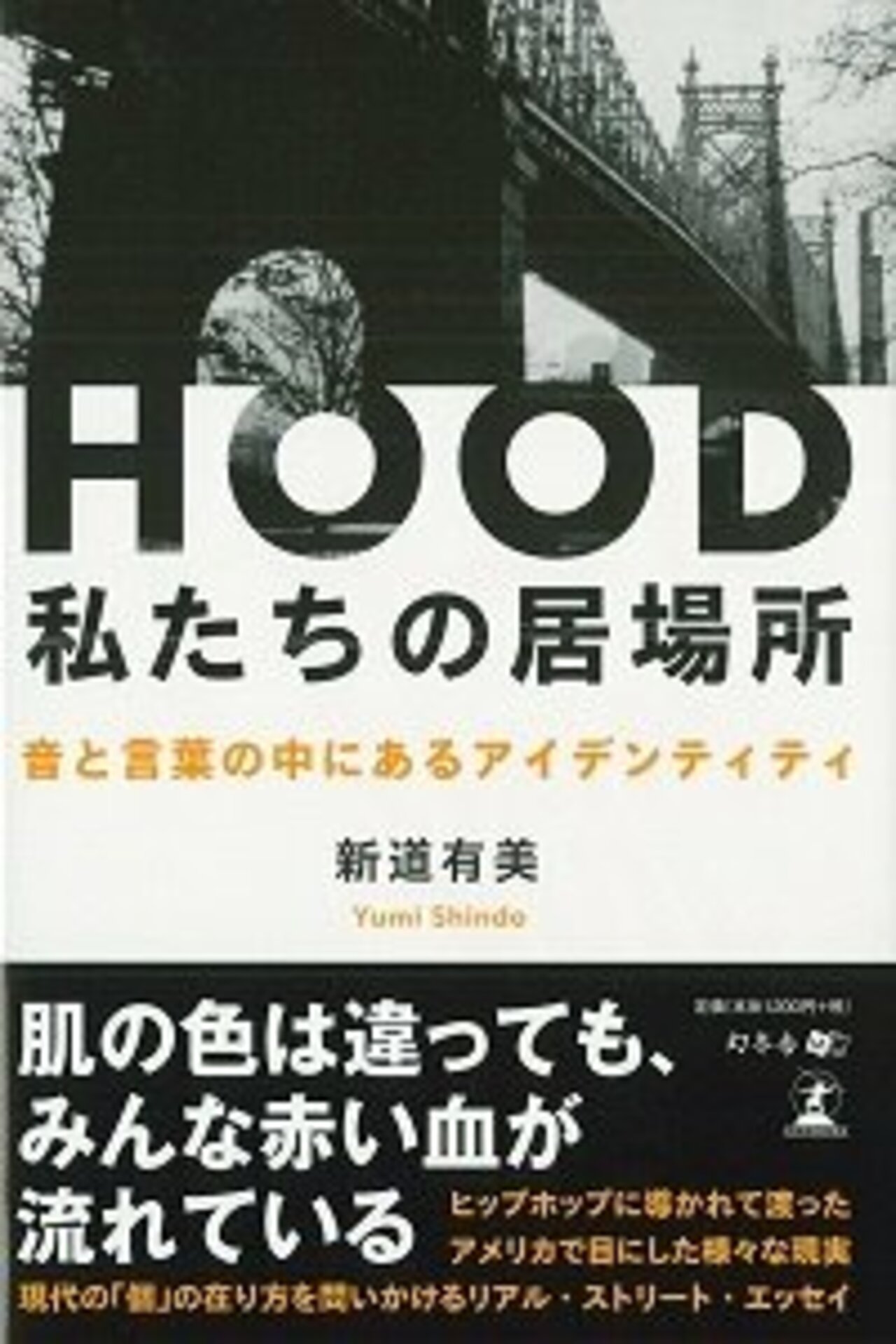We don't give a f**k !(そんなことどうだっていいぜ!)
「これ」
と言って、スキンヘッドとチャビが見せてくれたものは、腕や首筋、肩や背中に彫られた大きなタトゥーだ。
「写真撮ってもいいかな?」
私が尋ねると、
「ダメだ。ちょっとワケありでさ」
と彼らはいっせいに頭を横に振った。
「写真はだめだ。見るヤツが見れば、この写真の人物がオレってことわかっちまうからな」
タトゥーは自分が信じるものへの忠誠心であり、自分自身のシンボルでもある。彼らの身体に深く刻まれたタトゥーに一体どんな意味があるのかはわからない。
ただそこには確かに、彼らの命を懸けた「覚悟」が感じられるのだ。
「そう言えばさ……」
チャビが静かに語り始めた。
以前、チャビがバスに乗ろうとしたときのことである。突然、黒人2人組の男たちに襲われた。男たちはチャビのこめかみに銃を突き付け、彼が首に下げていた$750相当のネックレスを無理やり引きちぎって去って行ったという。この事件以来、チャビはむやみに高価なアクセサリ類を身に付けないようにしているそうだ。運良く命を落とすことはなかったが、まさに危機一髪だった。こめかみに銃を突き付けられたときの恐怖は、いまでもはっきりと甦ってくるという。
ストリートで生きていれば何が起こるかわからない。彼らは銀色の小型銃を護身用としてつねに持ち歩く。
ドレッドは先ほどから全く話に加わろうともせず、ただ大木のようにベンチに腰をかけ、私たち3人のやり取りを観察している。
「なんでそんなに静かなの? キミって、シャイ?」
「オレはオブザーバー(観察者)さ。みんな、オレのことをそう呼ぶんだ。」
彼の荒んだ瞳は、どこか深い悲しみを感じさせる一方で、強烈なエネルギーを放っているようにも見える。
突然、ドレッドが口を開いた。
「ねぇ、キミは大学に行った?」
「うん」
「卒業はした?」
「うん」
「すげぇな。オレ、いまカレッジに通ってんだ」
「そうなんだ。何を勉強しているの?」
「国際時事問題とか。ねぇ、キミはテロ事件やブッシュについてどう思う?」
彼の目は真剣だ。
するとスキンヘッドが呆れながら言う。
「また、始まったよ。いつもその話ばっか。」
ドレッドは全く動じる様子もなく、私の答えを黙って待っている。私は言った。
「9.11はあまりにも残酷で、悲惨な事件だったと思う。でも、同じアメリカ人の中にも、私には関係ないとか、どうでもいいことだ(I don’t give a f**k.)って思ってる人も実はたくさんいるような気がする。本当に悲しいことだけど。」
スキンヘッドとチャビが大きく頷いた。
「彼女の言うとおりだよな」