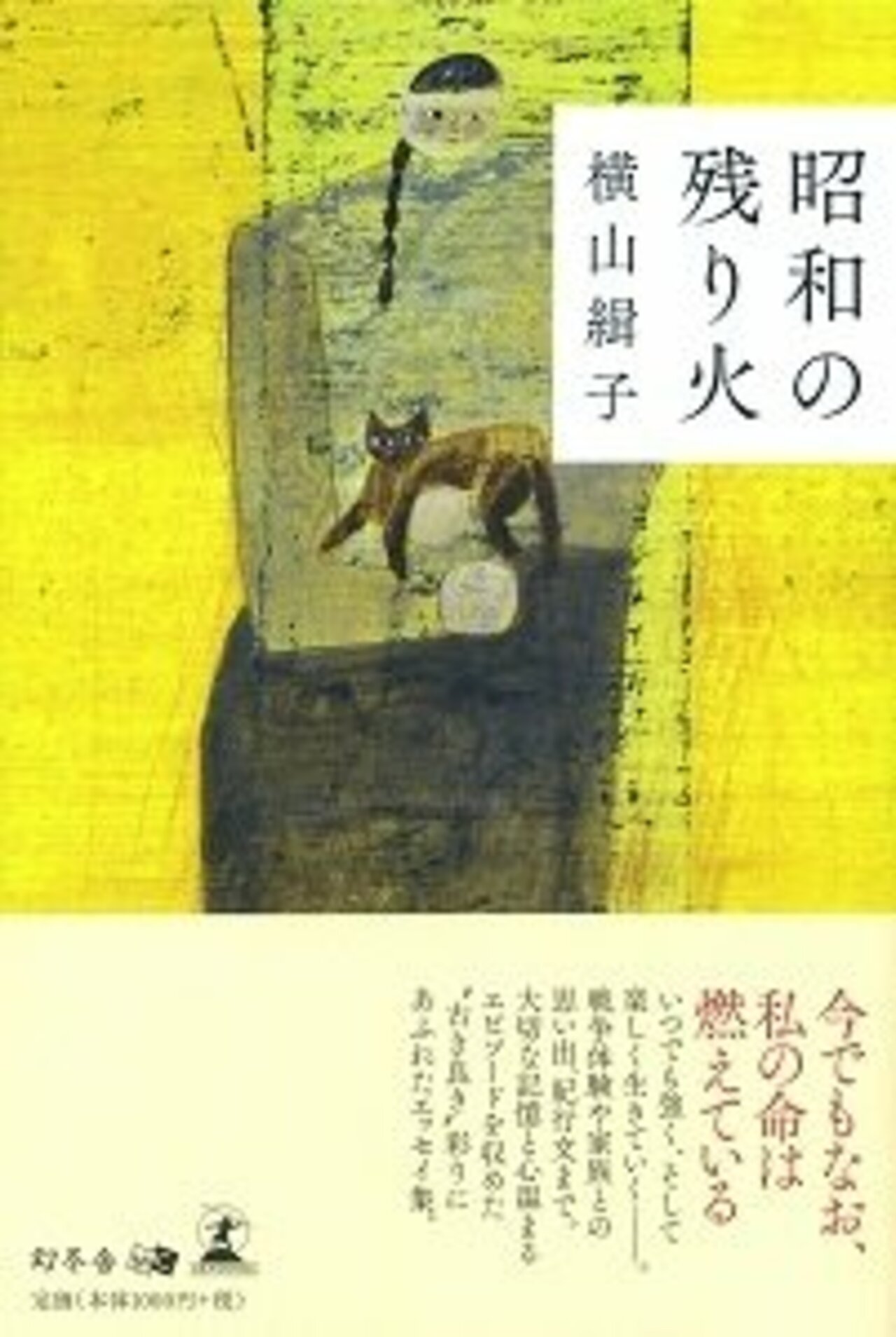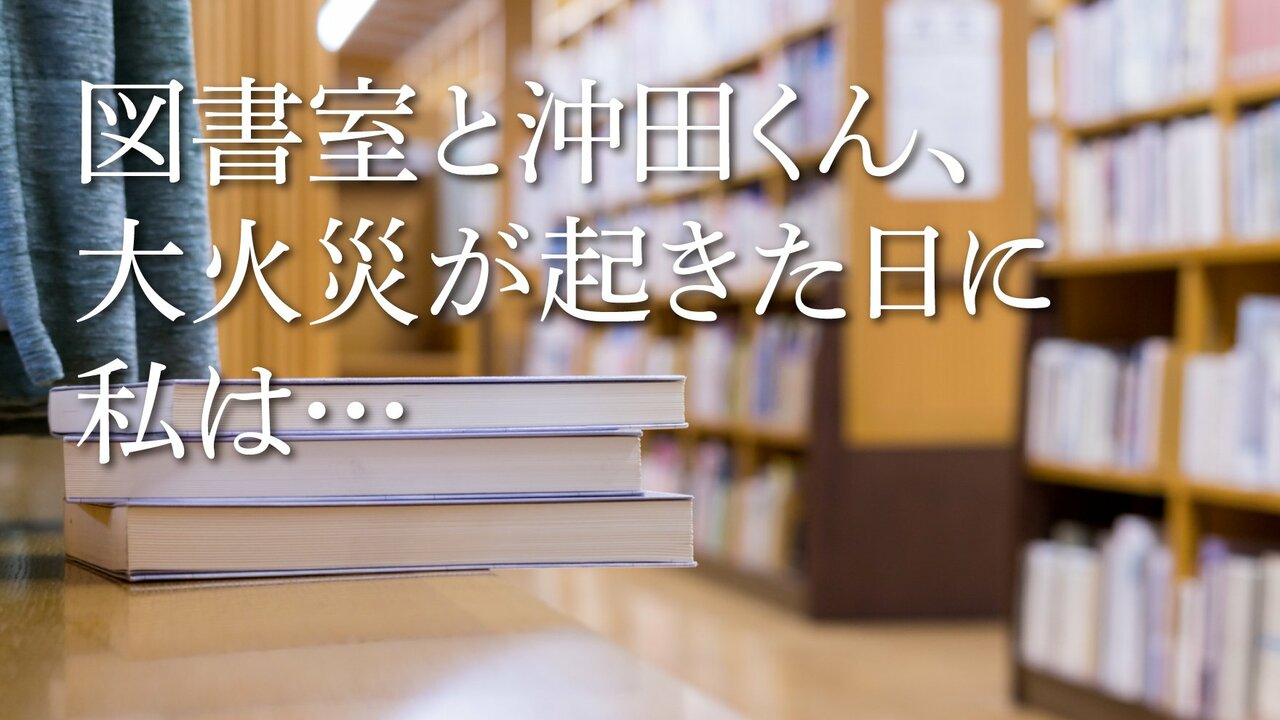堀の周りは武家地で、敷地が広く、建物も立派だった。その外側に馬場町、御弓町、大工町、二階町などの職人町があり、昭和十八年の地震、昭和二十七年の火災と二度の大災害に見舞われたにもかかわらず、中世と近世の遺構をよく残し、久松山とその山麓一帯は国指定史跡になっている。
私の家は武家地の東の端、職人町との境目で、掘割から山裾に沿って真っすぐに伸びた広い道が急に狭くなる丁字路の角にあった。
十月ともなれば霰まじりの雨が降り始め、三月までは雪や雨に明け暮れる町は決して明るいとは言えないが、茶道や華道が盛んで、人々の気分はしっとりと穏やかだった。
転校して最初に座らされたのが沖田くんの隣だった。沖田くんは、いがぐり頭の小柄な子で、誰のお下がりか、色の褪せた緑色の詰襟を着ていた。
生徒の数も少なく教室も小さい村の学校からやってきて、私は少しばかり気後れしていた。沖田くんはそんな転校生に向かって「おまえの言葉は変だ」とか「給食の食べ方が遅い」などと、あれこれ文句をつけた。
勉強も、前の学校とは進み具合が違ってなかなかうまくいかなかった。
沖田くんは返された私の答案を覗いて「なんや、たったの五十点か」と馬鹿にしたり、テストのときは「見たらいけん!」と自分の答案を大袈裟に腕で隠したりした。
私は家に帰ると、あんな学校はいやだと言って泣いた。
けれども鳥取弁を自在にしゃべれるようになるのにそれほど日にちはかからなかった。
私は本来の自分を取り戻して、何か言われても必ず言い返すようになった。沖田くんは悔しがって、ますますいきり立った。
社会科の授業で、防雪トンネルの話が出た。私が「うち、見たことあるで」と言うと、沖田くんは「嘘や!」と大きな声を上げた。 雪国育ちでもないくせにと言いたかったのだろう。社会科は彼の数少ない得意科目の一つだったから、自分が知らないことを知っていると言われて悔しかったのかもしれない。
「ほんまに見たんやで!」と私。秋田に父と行った時、防雪トンネルらしきものを見たのをかすかに覚えていたのだ。
そんなやり取りはいやでも先生の耳に届いた。
「そこの二人、何やっとるか! おまえら、いつもうるさいぞ。顔、洗ってこい」と元軍人の先生は恐い顔で言った。