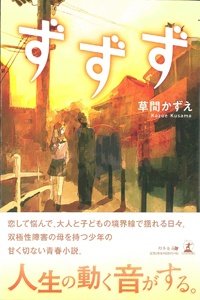「ねえねえ、アッキーママが具合が悪くなると、どうなるの?」
「別にお化けに変身する訳じゃないけど、それに近いかも」
「お化け屋敷のお化け?」
「うん、まず口を利かなくなる。まったく話さない。髪型もぐちゃぐちゃ。シャワーもあびないもん」
「なんで? シャワーを浴びたらサッパリして具合悪いのも良くなるんじゃないの?」
「うん、そうだよな。それは俺も思うよ。でもさ、よくよく考えれば俺、インフルエンザにかかった時、お風呂に入りたい、なんて思わなかったからな。家の中で苦しそうに、インフルエンザにかかったみたいにいつも寝ているから、少しはアッキーママの気持ちがわかるんだよな。一緒に暮らしてなければ、わかるはずないさ」
「そっか~、ごめんね、サッパリなんて言って」
「ひまりが謝ることじゃないよ」
「アッキーママのご飯はどうしているの?」
「基本、バナナと牛乳みたい。夕食は食べないよ。アッキーパパが炒飯を作って食べろ、食べろって言っても要らないってか細い声で返事をしてるさ。それに二階から降りて来ないから何日も顔を合わさない事も、しょっちゅうさ」
「え~、え~」
ひまりは言葉を失った。そして、
「初めて、コンサートでぶつかった時のアッキーママじゃなくなるんだね。『うつ』ってそんなになっちゃうんだ。辛すぎる」
そう言うと、もう、アッキーには何も尋ねることはしなかった。さっきまで白い三日月がほんのりとだいだい色に変わっていた。桜図書館の椅子から見えている、その三日月の上に四十五度に傾いたひこうき雲がひまりに何かを伝えていた。