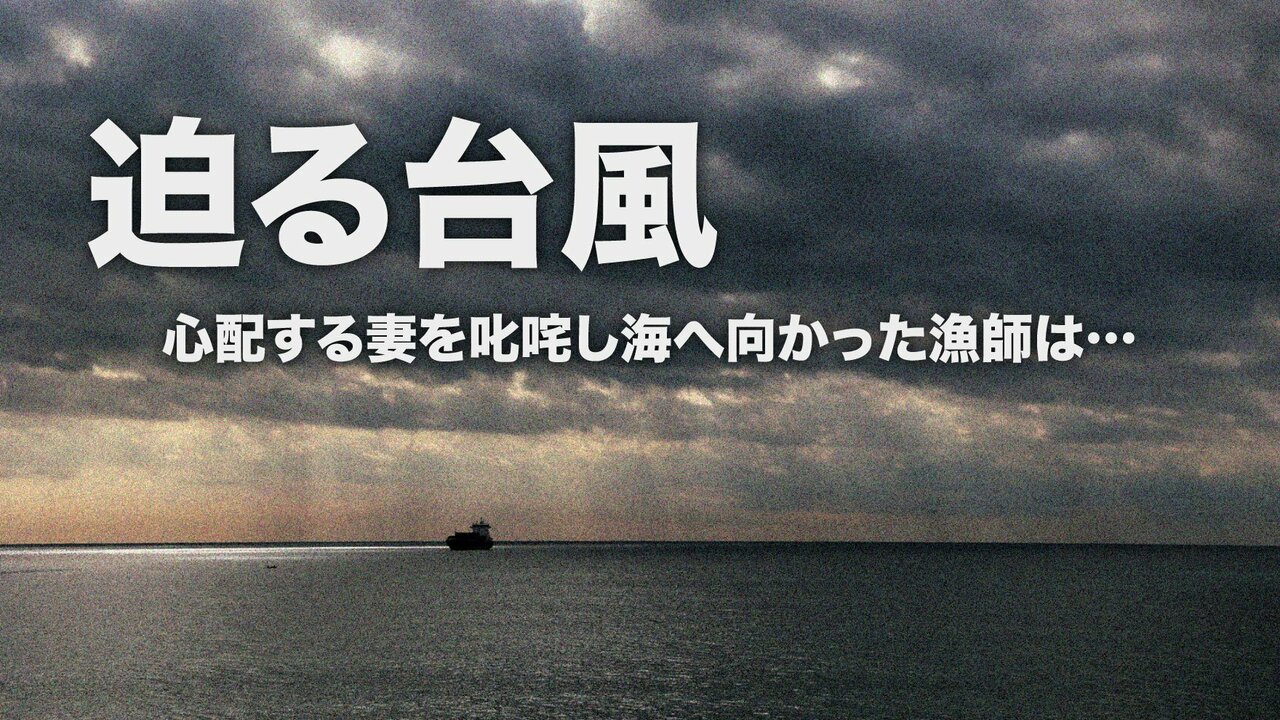そのあと、沙耶は、しばらくは食事が喉を通らず寝つかれぬ夜が続いた。リストカットも考えたがどうにか思い留まった。マー君がいる会社には居づらくなり同じ伊勢市ではあったが小さな衣料店に転職もした。
失恋から六年ほどが経ち伊勢市に落ち着いた生活の基盤を造り挙げた頃だった。父親から母親の様子がおかしいので自分では手に余るから戻って来いと連絡が入った。母親が進行の早い認知症を発症したのだ。即座に弟を呼び戻せと言ってみたが、あんな者が頼りになるか。頼りはお前だけだと泣かれてしまった。
病気がちな男親一人に任せることもできず沙耶は泣く泣く実家に戻り志摩の水産会社のパートタイマーとして働くことになった。そんな中、水産会社のパートだけではどうにも家計のやりくりが苦しく、先に漁火で働いていたパート仲間の康代の口利きで漁火のホステスとなったのだった。
「そんなことがあったのよ。あたしって、馬鹿でしょ」
話し終えた沙耶は意外とサバサバとしていた。
「彼氏とは別れたというより振られたのね、あたし。でも、こんなもの背負っていたのではもうお嫁には行けないわね」
沙耶は自嘲気味にそう言った。
「男の言いなりに背中に墨まで入れてしまって、彼を恨んでいるの?」
「恨んでいないって言えば嘘になるわね。騙した彼は悪いわよ。でも、あたしも初心だったのよ。こんな一言で片づけるのも何だけど、いい勉強をさせて貰ったわ。そうでも思わなきゃ遣ってられない……。でも、ほんと、女って言うか私ってだめね。好きになっちゃうと前が見えなってしまうのだから。それからはね、彼のことは考えないように努めた。男なんてもうこりごりとそう思うようにしていたの。でもやっぱりだめ」
「だめって、まだ諦め切れないの?」
「違うのよ。また、好きな人ができちゃったってこと。あたし、ただ今、恋愛中〜。今の彼、背中の墨を見せても黙って抱いてくれたの」
沙耶はそう言って無邪気に笑った。相手はパートタイマーとして勤め出した水産会社に配送を任されているトラック運転手だった。元彼に少し面影が似ていて沙耶の方から言い寄ったのだと言った。沙耶の二度目の恋だった。深い仲になったあと、相手には妻がいることがわかったが、沙耶に将来どうしたいという望みはなく妻と別れて結婚をしてくれと相手に迫ろうとは思っていないとも言った。
沙耶がつらい恋愛経験をあっけらかんと話し終わると、奈美はお願いをして背中の入れ墨を覗かせてもらった。背中には、優しい眼差しの悲母観音が微笑むように彫られていた。それはまるで傷ついた沙耶を優しく包むように庇う守護霊のようだった。