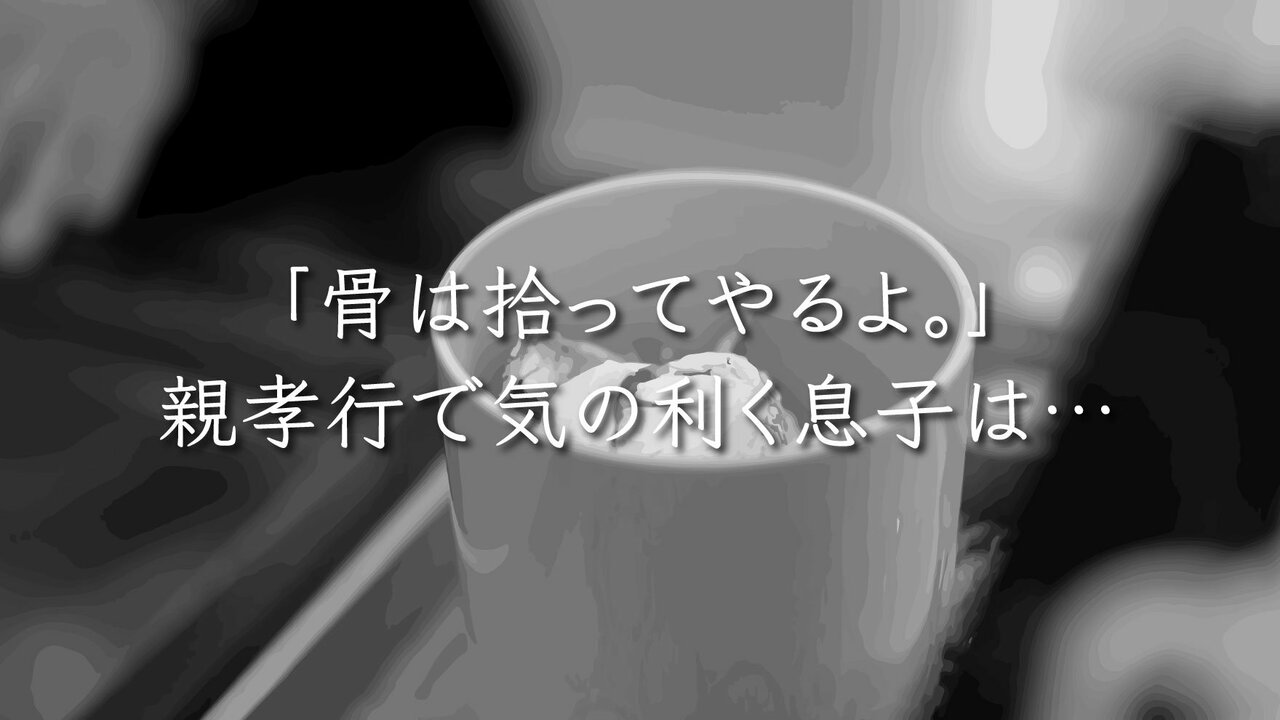「溝原朗子さんという人がいてね、山岳捜索隊なんだけど、たぶん六十歳は過ぎてると思うの。すごい健脚で鉄人て感じ。その人が二日間、息子達に付き添ってくれたの。今日、どうしても私が気になる左衛門小屋で、たとえサクラがいなくても、サクラの名前を呼んでほしい、とイオリに頼んでいたのね。イオリがサクラを呼ぶと、左衛門小屋の周りの高い草木に向かって、一緒に叫んでくれたって。ありがたいわ」
姉は一度言葉を切った。
「それから、ヒョウゴはね、今日、登らなかったんだけど、竹谷温泉から三時間半くらい自動車道を歩いて、捜してくれたの。もしかしたら、自動車道で滑落してないかって。あとね、サクラの職場の同僚で、ちょうどいなくなる一週間前に一緒に山に登ったっていう女の人が二人、差し入れに飲み物を持って来てくれたの。私、全く気がまわらなくて、いただいた飲み物を皆さんに配れて、有り難かった」
「そう」
「今日ね……」
姉さん?
「本当は休みを取っていて、サクラと山へ行く約束、してたんだって。おじいちゃんとだって約束してたし、自殺なんてするわけないよね」
自殺?
「警察がね、自殺したんじゃないかって。何か悩んでなかったですか、とか、様子おかしくなかったか、って聞くの」
「そんなこと、あるわけないよ! 姉さん、おじいちゃんと出かける約束もしていて、会社の人とも約束していて、心配して個人的に来てくれるくらい、信頼されていたのに、自殺なんてするわけないよ!」
「そうだよね。ごめん。話すとキツイ。ありがたいけど、何かあればおばあちゃんに電話するから、聞いてくれる?」
「わかった。わかったよ」
姉の悲しみが胸に伝わって、痛みがいつまでも拭えなかった。