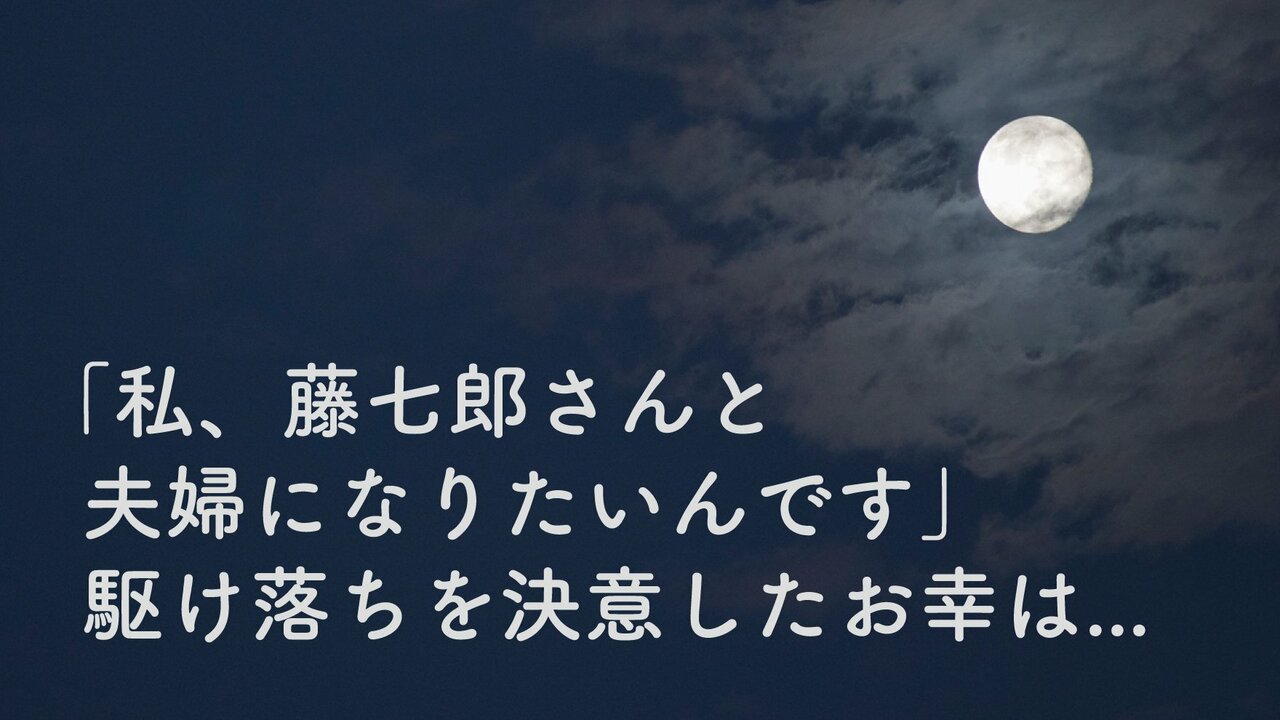『水蜜桃の花雫』……?
夫婦というのは正反対の者同士が上手くいくとよく耳にするがせめて茶の煎れ方くらいは同じであって欲しいものだ。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
「そう言えば水蜜桃があったな。取って来るから少し待っていてくれたまえ」
私が薄い茶を飲み終えると、友人は思い出したように膝を叩いて立ち上がり、台所へと姿を消した。数分後には綺麗に剥かれた水蜜桃が所狭しと並べられた皿を持って戻って来た。
「美味そうだな」
「ああ、かなり美味しい」
「君の煎れた薄い茶の口直しに頂くよ」
「――君という人間は本当に口が減らないね」
「君ほどじゃあないさ」
ふんっ、と鼻を鳴らしてしかめっつら。この友人は眉間に皺を寄せているのがデフォルトなのだから別に気にしてはいないが、笑うのも悪くないと思うのだが。
「――美味いな」
「だろう?」
「ああ、美味い」
水蜜桃は本当に美味かった。甘くみずみずしい水蜜桃は先程までの嫌な気分を払拭させてくれた。
「そう言えば君、何用で来たのかね」
御巫(みかげ)がふいに思い出したように問うた。
私は〝スランプ〟と答えた。
御巫は
「スランプなんていつものことだろう?」
と笑った。
「君に面白い話をしてあげよう」
御巫は近くの本棚から一冊の本を取り出すと私に渡した。
「何だい?これは」
「君は輪廻転生を信じるかい?」
「はあ」
「陽子(ようこ)が今大学で卒業論文を書いているのだが、内容が吉原遊郭についてなんだ。いいネタになると思わんか?」
陽子とは、彼の妹で大学生だ。先週此処を訪れた際、今年卒業をして大学院に進む予定だと御巫が言っていた。
「……私はその手の知識は皆無なんだが」
中学時代から突拍子もないことを言う奴だったが、それはまだ健在なようだ。
「きちんとしたことを書かなくてもいいさ。君が書く物語はフィクションだ。虚実が八割でも真実が二割あれば大丈夫だよ」「そういうものか」
「おいおい。物書きは君の本職だろう。何を言っているんだ」
「まあ、……フィクションだしな」
「そうだ。必要な資料は家から持って行っていいよ」
「ああ、それは有り難い。助かるよ」
「少し奥の棚にだいたい揃っているはずだ」
「わかった」