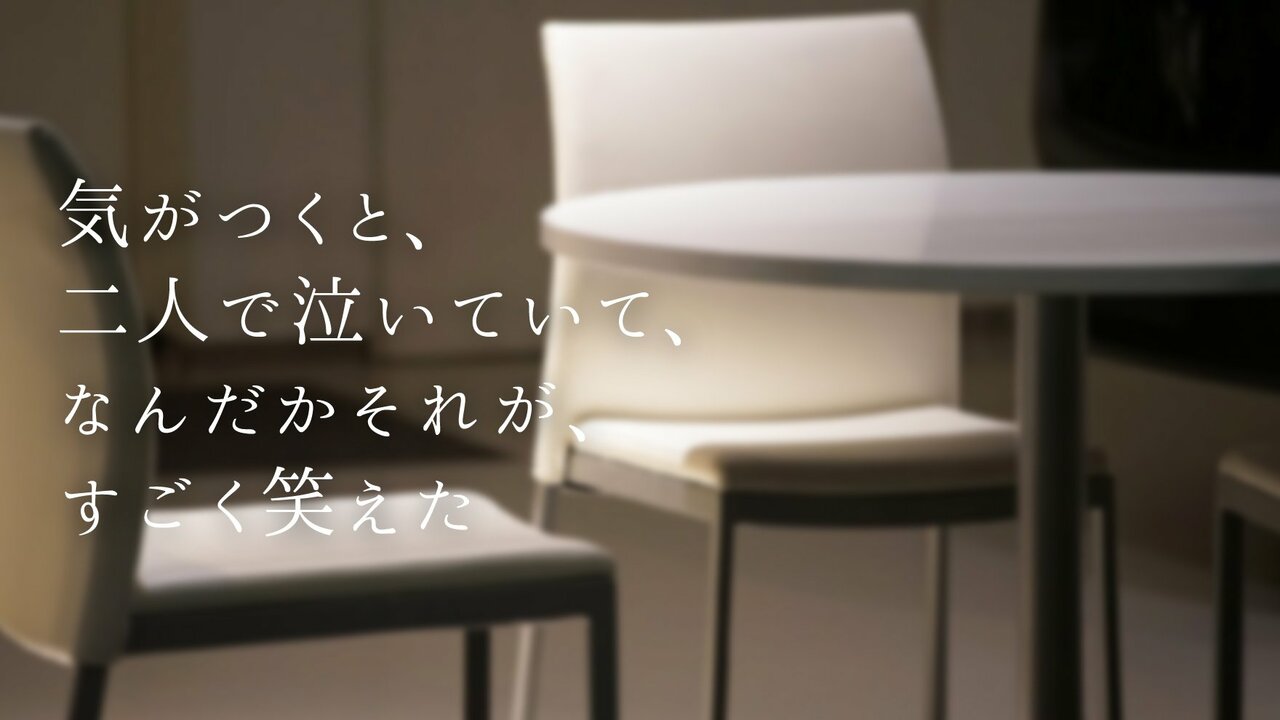彼のお店は細い2階建ての木造の建物の1階で、もともとは小さな本屋さんが入っていた。歳を重ねて営業していくのが難しくなったおじいさんが、借りてくれる人を探していたところに彼はやって来た。おじいさんは、借り手を大々的に探していたわけではなく、密やかに、心で思う程度の話だった。むしろこのまま借り手なく、空いたままでも困らない環境ではあったので、よほどの人にしか貸さないだろう自分の頑固さも、おじいさんはわかっていた。
閉店します。という、表のドアに小さく書かれた貼り紙を見て、彼は尋ねた。
「この後このお店は、どうされるのですか?」
おじいさんは、ルーペで分厚い本の小さな文字を読むのをやめて、彼を見た。
「君か。何度か来ているね。あの、島の歴史書は、見つかったかい?」
「いえ。なかなか見つかりません。なにせ、小さな島ですから、もしかしたらそういうもの自体がないのかもしれません」
「私も一度、行ったことがあるよ。小さくて、いい島だ」
「住んでいたんです。小さな頃に、出てしまいましたが」
おじいさんは、無垢の木でできた古さが充分に出たテーブルの上で、いつも作業をしていた。そのテーブルは、濃い茶色につやつやとしていた。同じ場所で長い時間、使い続けられた風合いが、歴史が、そのテーブルを見てもわかる。おじいさんは、重ねた本のタイトルを見ては、分別して本を重ねていく。
「物件を、探しているんだろう? 何を売るのかね」
「シャツです。シャツの専門店をするんです。このお店くらいの広さが、僕の理想だなと思っています。木の感じも、奥に小さな庭があるのも好きです」
「古いけどね、この店を、私は本当に大切にしてきたんだよ。沢山の物語が重ねられている。シャツも、使えば使うほど、味が出てよくなってくるんだろう? 物はすべて、そうでなければならない」
彼は、おじいさんの質問とも独り言とも思える話に頷きで答え、言葉を続けた。
「もし、お店をお借りするとなったら、塗り直しも、改装も考えていません。照明を少し暗くしようと思います。あとは本棚たちを外してもらわなくてはなりませんが、壁一つ分の棚は残してほしいと思っています。それから、できたらそのあなたが作業されているテーブルを、私にも使わせていただけないでしょうか」
そうしておじいさんは彼にお店を、破格の値段で貸すことにした。本棚は、彼が言う通りに、壁際のひとつだけ残してもらい、おじいさんがコレクションしてきた古い本の中から、彼が興味をそそられた本たちをそのまま残してもらった。
私は先日の取材でその話を聞きながら、残された本棚も、ひどく気に入っていた。