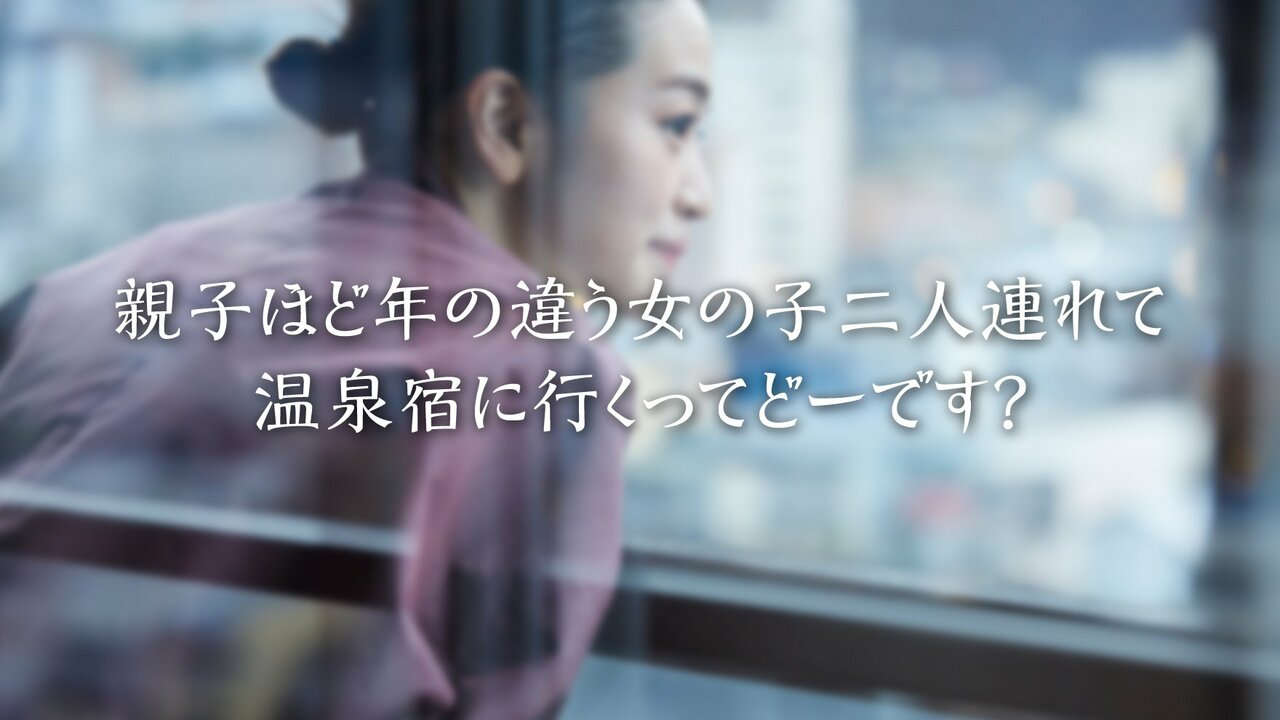猫座敷の裁判
彼女は正式にはこの大学の学生ではなかった。女子大生だが離れた場所にある薬学部に通っていた。医学部とは何も関係がないので、それが気のゆるみになったのだと思う。
最初に近寄って来たのは彼女だ。本当は医学部に行きたかったらしい。無邪気であけっぴろげな感じで薄く化粧をしたきれいな肌に利発そうな澄んだ目をしていた。
赤いピアス以外に装飾品は何もない。ごくシンプルなワンピースとサンダルだけだがそれで十分に魅力的だった。もう恋愛心など感じる歳ではないと思っていたのに胸がトクンと鳴った。
それから真剣な顔をして質問をしてきた。質問は次から次に出てきたので医学書を渡した。ついでに携帯の番号。
姉がいると言ってまるでコピーのようにそっくりな娘を連れてきた。彼女は双子だった。一緒じゃなきゃいやだというので二人とも連れてイタリアンやフレンチにも行った。
なんだか不思議な娘たちだなと思ったのは、彼女たちは何処に行っても最初は違う惑星に来たみたいに顔を輝かせてそれから大喜びする。その無邪気さが楽しかった。
あかぬけて綺麗だったが、ひどい田舎にすんでいたらしい。洋服やアクセサリーも買ってやろうと思ったのだが彼女たちはいらないと言って、代わりに医学書や色々な実用書ばかり欲しがった。
海のそばで育って、海しか知らないというので山の温泉に行こうと言うと、一瞬顔を見合わせてから「温泉って?」と言った。最初はふざけているのかと思ったが、本当にその言葉しか知らないらしい。