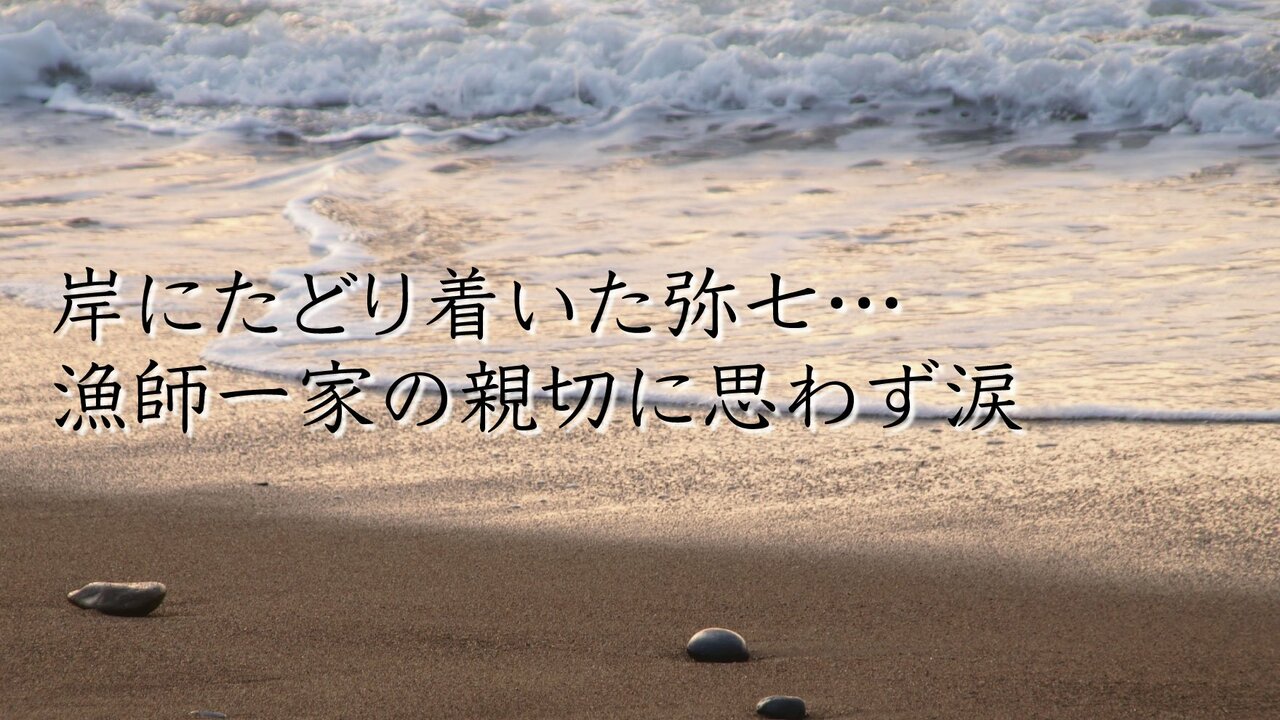弥生編
「ここでのことは、なかったことにしよう」と言うと、そいつも即座に「それはありがたい」と言った。矢をつきたてられて苦しんでいるムカルの子分は、失踪してこの方、山の向こうの村にいたに違いない。このまま、そちらで生きていてくれれば、むしろいざという時のよい証拠となる。
地面にべちゃりと広がっている黒い何かは、よく見ると、熊皮を継ぎ合わせ、木枠を中に入れただけのものだった。警戒は緩めないままそれを拾い、南へ向かって撤収した。これは、丘の村の長にだけ見せるとしよう。
アトウルは魔物に遭い、辛うじて勝ったが、逃げられたのだ。左頬と左肩の傷は、ムカルのそれと違って本物の闘いの痕である。ムカルの言う通り、魔物は確かに実在した。そいつは人の心に棲んでいるのだ。
*
初雪の舞う頃、里の村に一人の老人がやって来た。里の長が出迎えてみると、なんと丘の長その人であった。丘と里の二つの村は、先祖代々に亘って良好な関係にあるが、丘の長が一人で訪ねて来るというのは、さすがに異例である。
老人は、頬とあごに長い灰色の髭をたくわえた顔に満面の笑みで、「元気であったか、若いの」と、達者な里の言葉で言い、手土産の袋を差し出した。焼き栗の香ばしい匂いがする。里の長ももう決して若いという年ではなかったが、彼の父親が生きていればそのくらいの年であろうこの老人にかかっては、若いの、と言われても怒る気にもならなかった。