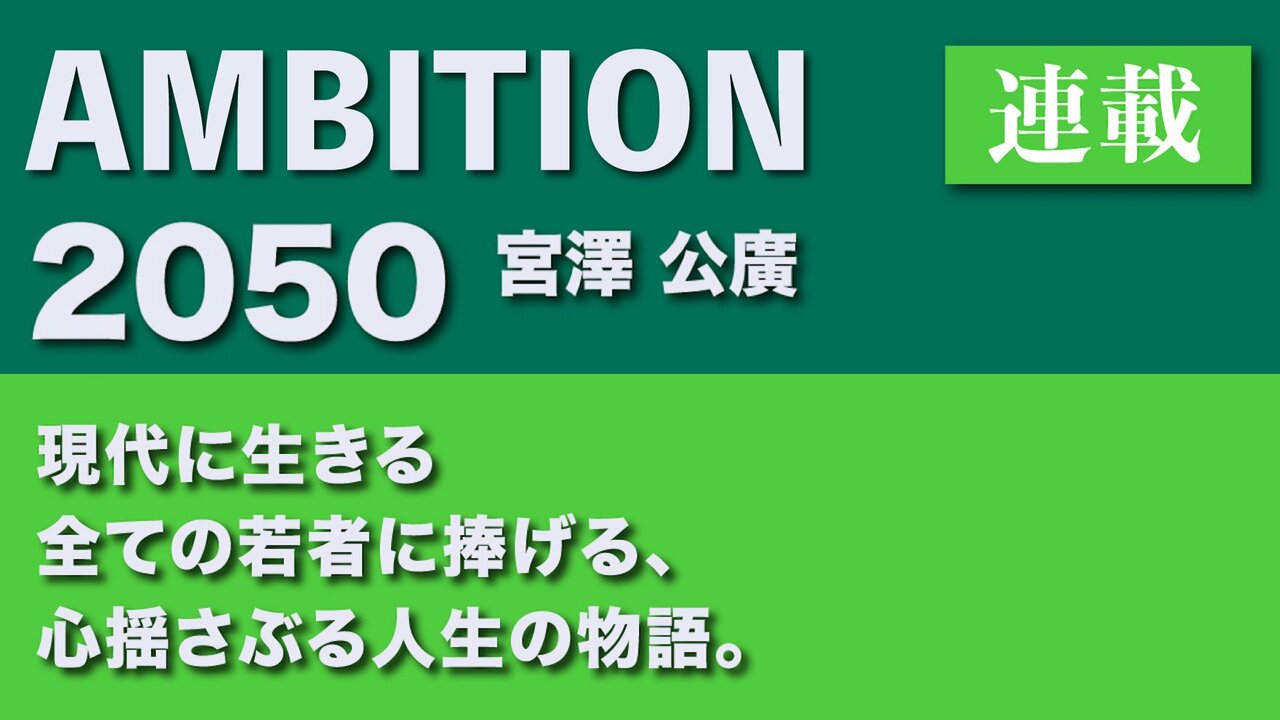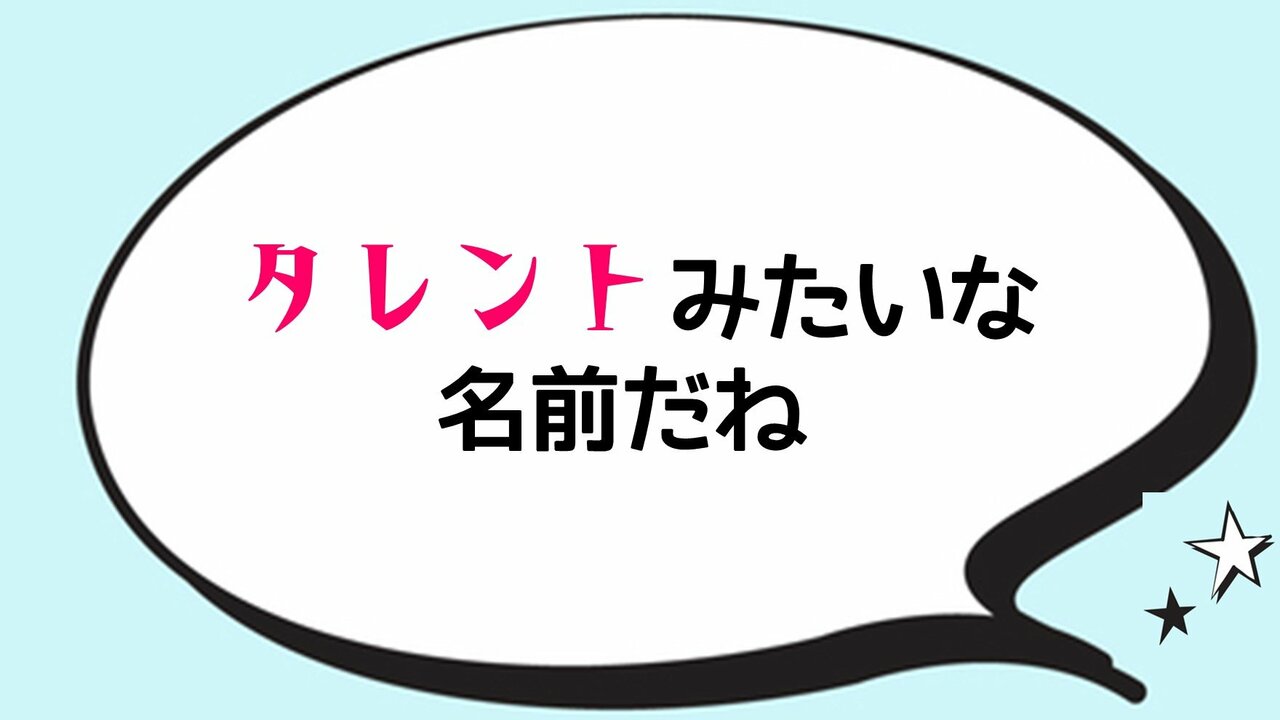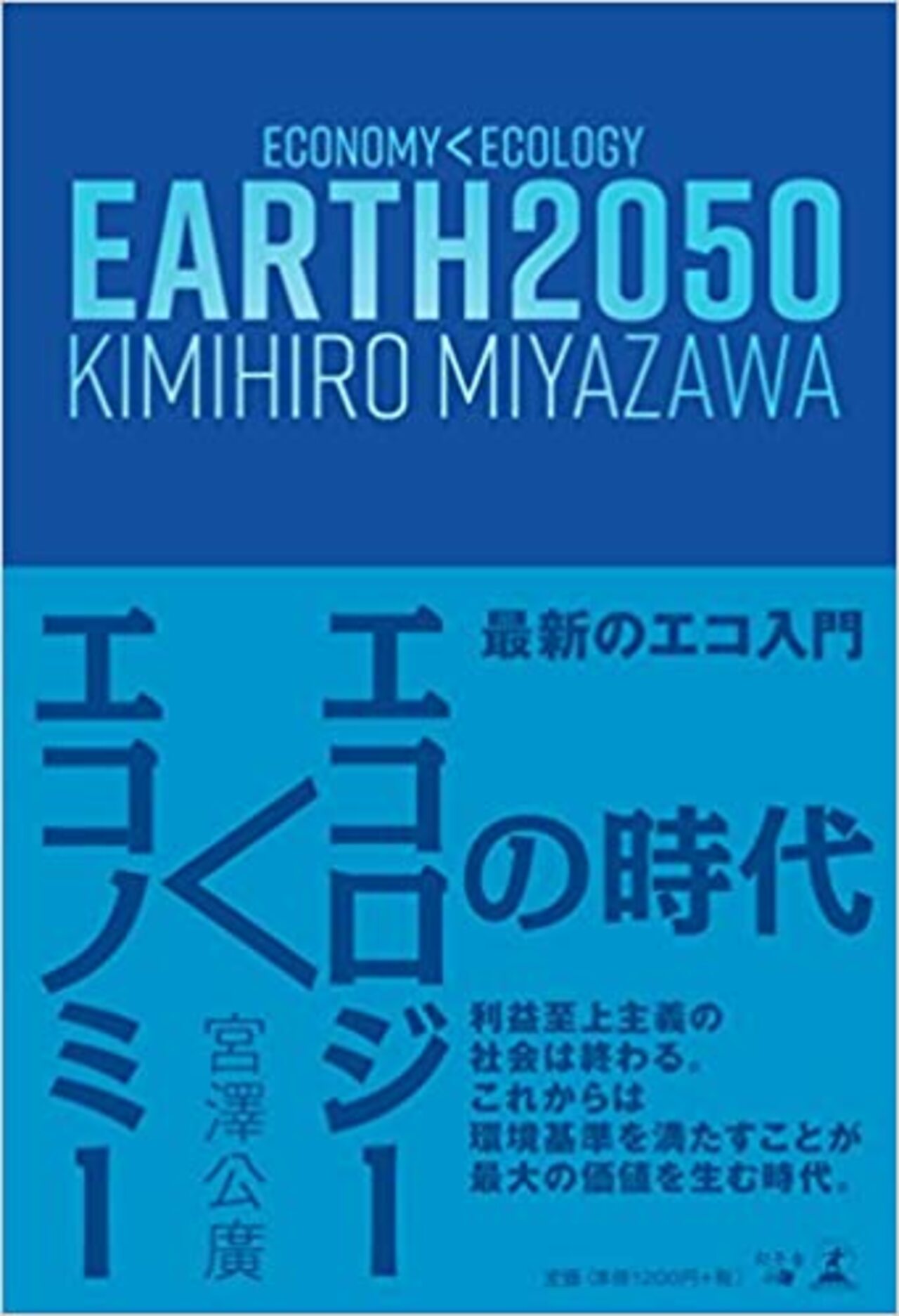第一章 道 程
【6】
ふと窓の外を見ると、眼下には夕陽を反射して輝く瀬戸内海が広がっていた。海辺の高台に建つこの民宿は登山サークルの定宿らしく、十年以上お世話になっているがゆえ、宿泊料金を値引きしてくれたり料理の量をサービスしてくれたり、いろいろと融通してくれるらしい。またオーナーはオリーブ園も運営しており、土産にはいつもオリーブを持たせてくれるそうだ。
「すみません、ご飯のおかわりできますか?」
隣に座っていた上杉が声を上げた。大喰らいの彼は、この日も茶碗に山盛りの白飯をよそってもらっていたが、あっという間に一杯目を平らげたらしい。厨房から「はーい」と声がすると、「あ、今度も大盛りで!」と、威勢よく強調した。
「お待たせしました、ご飯大盛りです」
そう言いながら、ごはん茶碗を乗せたお盆を両手に持った女性が、笑顔で厨房から姿を見せた。その瞬間、宮神は息を止めた。
肩まで伸びたつややかな黒髪。吸い込まれそうなほど透き通った瞳。ノースリーブからのぞく小麦色に焼けた肌。その一つひとつがみごとに調和していた。
上杉は女性をチラリと見ただけで、一心不乱に白飯を頰張り始めた。宮神はただただ厨房に戻っていく女性を眺めていた。
「おい、顔が赤いぞ」
上杉にそう言われ、宮神は我に返った。たしかに頰が火照っている。
「惚れたな?」
「い、いや、そんなことはないけど――」
言葉とは裏腹に、宮神は先ほどの女性に心を奪われていることに気づかされた。食事に夢中になっているのかと思いきや、他者の心の機微まで察知する上杉には感服するしかない。
「おし、俺に任せとけ」
上杉は白飯をかきこんで茶碗を空にすると、「もう一杯おかわりください!」と叫んだ。すると、先ほどの女性が笑いながら大きなおひつを持って現れ、「お客さん、たくさん食べるみたいだから、ここから好きなだけよそってね」と、しゃもじを手渡してくれた。
「ここのご飯、美味いですね」
「そうでしょう? 水がおいしいから」
「十杯はいけそうだな」
「それは食べすぎね」
「お姉さんはアルバイトですか?」
「ううん、ここの娘。大学が夏休みで帰省してるの」
「そうなんだ。俺は上杉で、こっちは宮神。秀星大学の一年です。お姉さんは?」
「奇遇ね。私も大学一年よ。名前は美穂、渚美穂です」
「タレントみたいな名前だね」
「ちょっと、名前負けしてるって言いたいの?」
「まさか。よく似合っているよ。あのさ、俺たち、あさってからは自由行動なんだ。良かったら、一日だけ島を案内してくれない?」
「いいよ。ちょうど退屈してたとこじゃ」
「やった! じゃあ約束ね」
「その前に、食べ過ぎでお腹を壊さんように気をつけて」
「安心してください。胃腸だけは丈夫だから」
上杉のフランクな雰囲気が奏功し、直球の誘いが見事に成功した。美穂は「いけない、洗い物」とつぶやきながら厨房へ戻っていった。
「お前、すごいな」
「今から予言をする。俺はお腹を壊すぞ」
「え?」
「これから毎食、飯を食べ過ぎてお腹を壊す。あさってはお前と美穂さんのふたりで出かけてこい」
「は? ちょ、ちょっと待て」
思わぬ展開に宮神は狼狽したが、上杉は「どうにかなるさ」の一点張りで会話を打ち切り、新鮮な刺身をおかずに、ひたすらに白飯をかきこんでいる。
厨房を見ると、美穂がエプロンをつけて食器を洗っていた。運動をしたわけでもないのに、宮神の心臓は急に早鐘を打ち始めた。