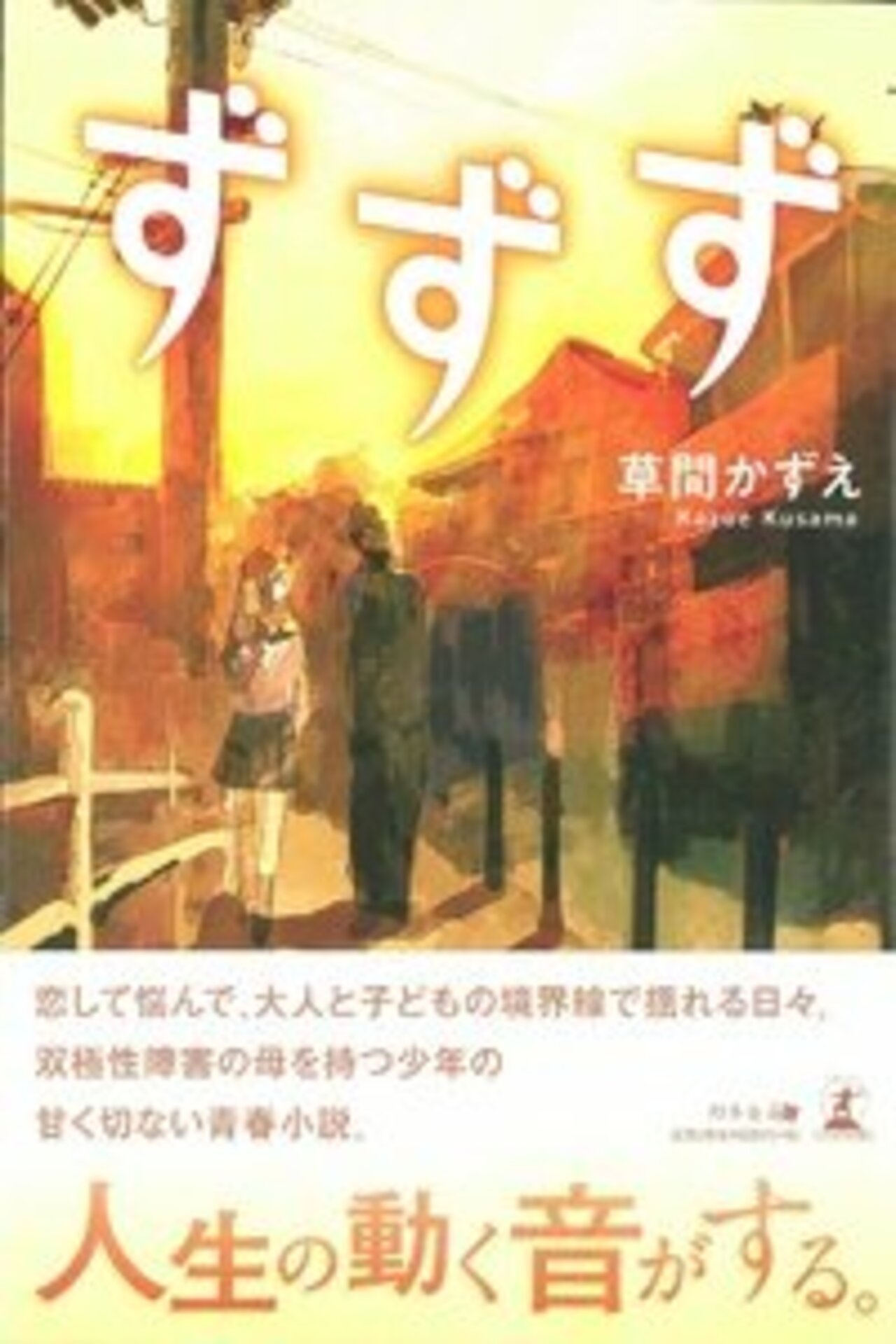アッキーママはどんな顔をするだろうか、びっくりして、そして喜んでくれるだろうか。
そう思いながら走っていると、後ろにひまりの気配が無い。少し後ろで座り込んでしまっている。アッキーは後ろに戻りひまりに優しく、
「どうした、疲れたか? なら、歩こう? きっと間に合うよ」
「もう無理。歩くのも無理だよ、アッキーママに手紙を渡して来て、お願い」
そう言うとひまりは道に座り込んでしまった。アッキーはもう少し頑張ろうと言っても立ち上がろうとしない。
ひまりにとってこれが限界なのだろう。面会を諦めて帰るか、アッキーがひまりを一人ここで待たせて、アッキーママの所へ行くか、それとも……。
アッキーはひまりの目の前に行き、くるりと後ろ向きになるとしゃがみ込んで無言のままその姿勢でいた。アッキーはひまりを、おんぶ、するしかないと決めた。
諦めることも、アッキーが一人で行くことも出来なかった。やはり、どこまでも、ひまりと一緒に行きたかった。
ひまりはそのアッキーのしゃがみ込んでいる姿勢を見つめながら、ダメとか無理とか言った自分がとても小さく思えた。アッキーは真剣にひまりの事を考えて思ってくれている。
ひまりは座り込んでいた腰をあげて、遠慮深くアッキーの背中に身体をくっつけた。そしてアッキーはひまりを背負い込み、小走りでアッキーママのもとへ急いだ。時間はあまりない、間に合うだろうか?
背中のひまりは無言でアッキーにおぶられていた。ひまりは自分のお尻や腰のあたりにある、アッキーの熱くなった手を意識していた。ひまりのお父さんの手とはまるで違うが、何かに包み込まれている優しい安心感があった。
そして、アッキーも背中にある膨らみ始めた二つが背中に押し付けられて、小走りになる度に二つは小さくゆれ、背中にとても弱いけれど押し付けられた。アッキーの心臓の鼓動は大きくなって、こそばゆい感じがしたのだった。