須佐之男は出雲の国の斐伊川の
岸の辺に降りたちにけり
【大河(たいが)の氾濫を治め得た者が国土の支配者となる。古代中国の帝王も、大八島(おほやしま)も同じである。】
*斐伊川 島根県を南から北へ流れ下り、宍道湖(しんじこ)に注ぐ大河。下流の出雲市では、天井川となる。
人家は斐伊川の水流より低い所に建ち、強固な堤防によって守られている。
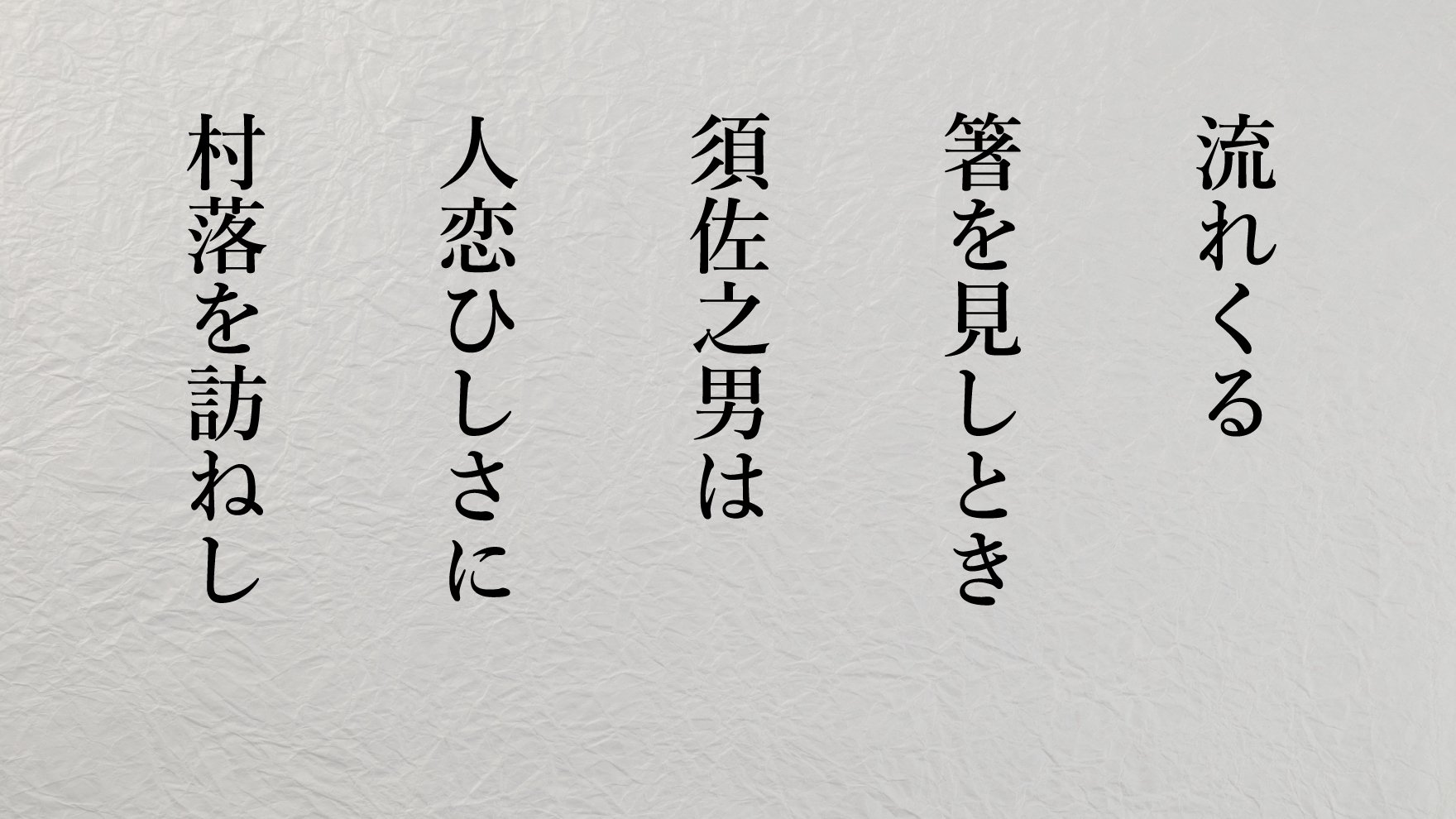
流れくる箸を見しとき須佐之男は
人恋ひしさに村落を訪ねし
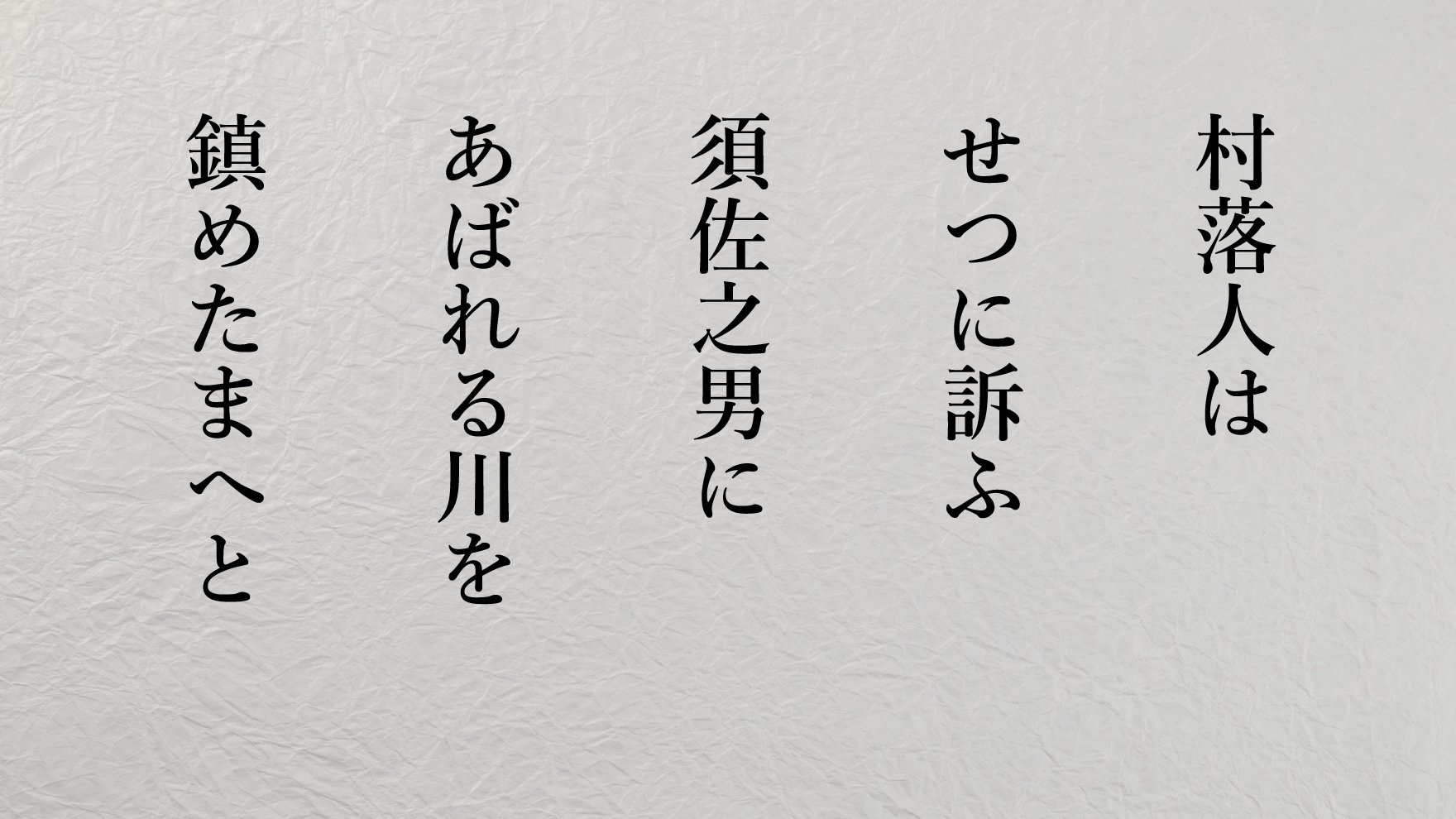
村落人はせつに訴ふ須佐之男に
あばれる川を鎮めたまへと
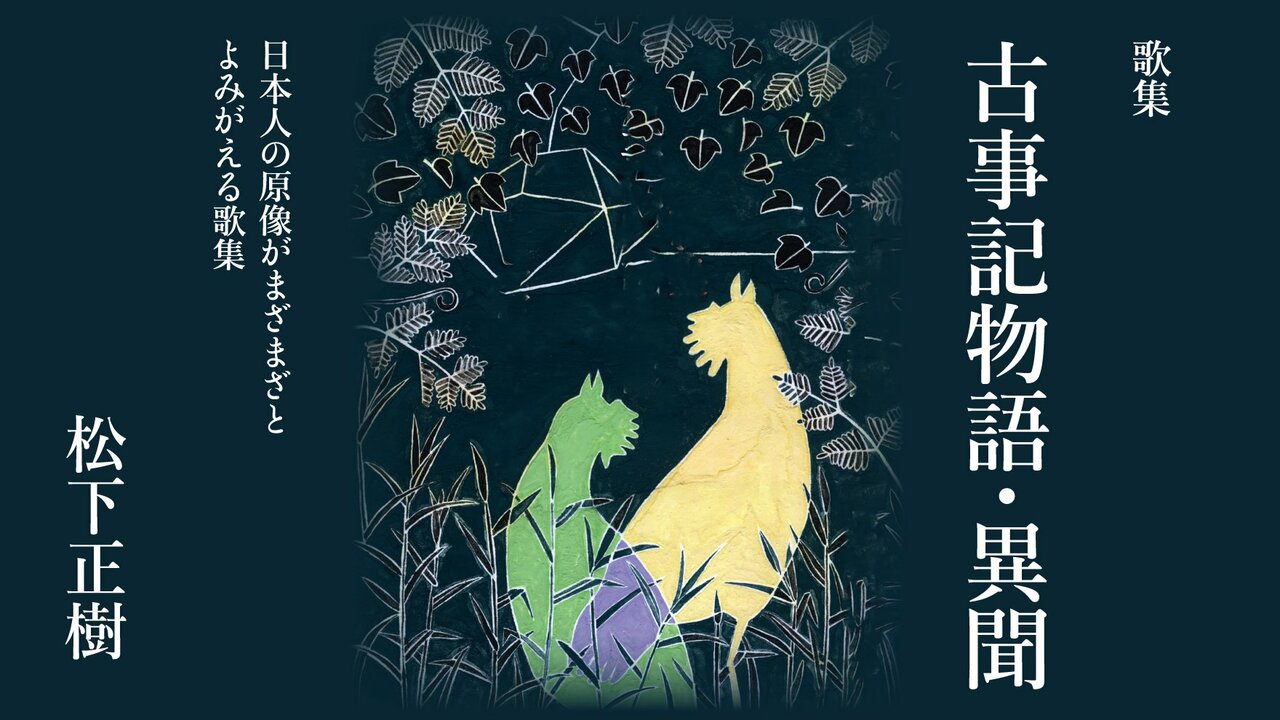
私たちの太陽(アマテラス)はどこへ行ったのだ?
日本人の原像がまざまざとよみがえる。
日本最古の史書『古事記』に登場する神々の世界を詠う、他に類を見ない叙事的な歌集。叙情的な文語と明快な口語を絶妙に組み合わせながら、神々の悲哀と愛憎をつぶさに表現する。
日本の神々は、民と交わり、民とともに働き、人間同様死にゆく存在でもある。
王国の成立と興亡の歴史が秘められた『古事記』の世界を、人々の悲しみと喜びを歌で再現。日本人の原点の物語を連載でお届けします。
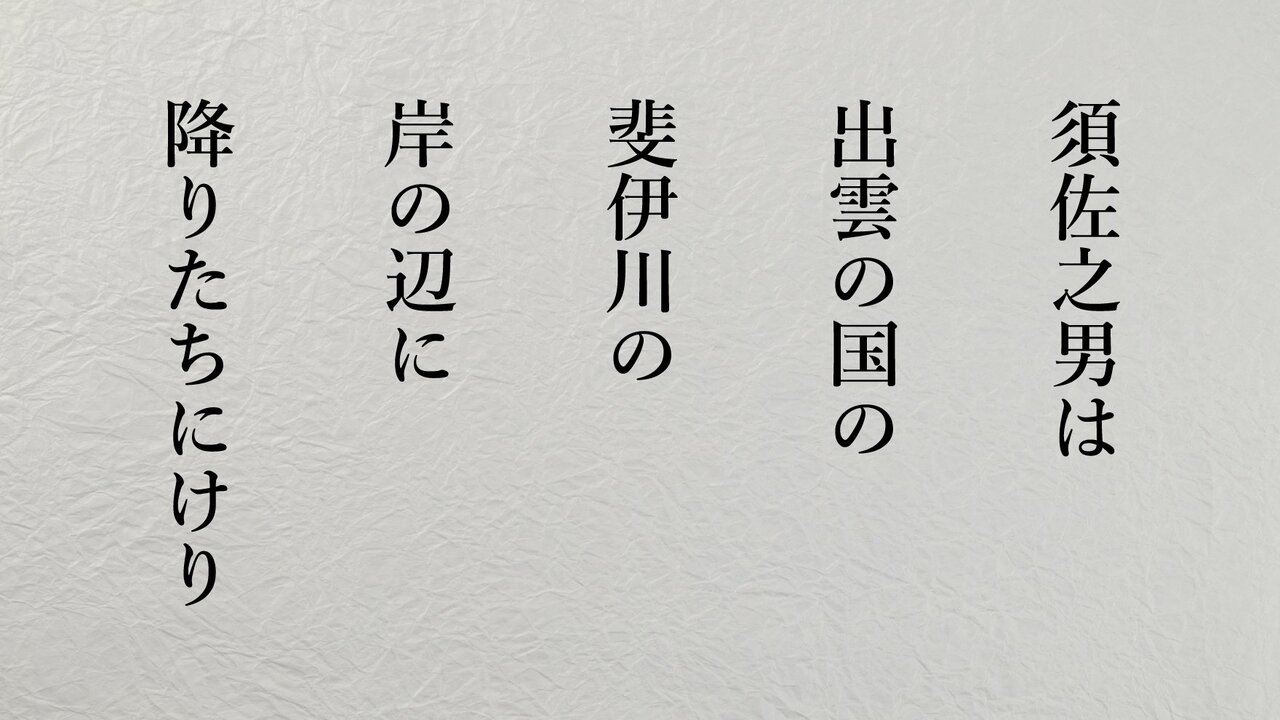
須佐之男は出雲の国の斐伊川の
岸の辺に降りたちにけり
【大河(たいが)の氾濫を治め得た者が国土の支配者となる。古代中国の帝王も、大八島(おほやしま)も同じである。】
*斐伊川 島根県を南から北へ流れ下り、宍道湖(しんじこ)に注ぐ大河。下流の出雲市では、天井川となる。
人家は斐伊川の水流より低い所に建ち、強固な堤防によって守られている。
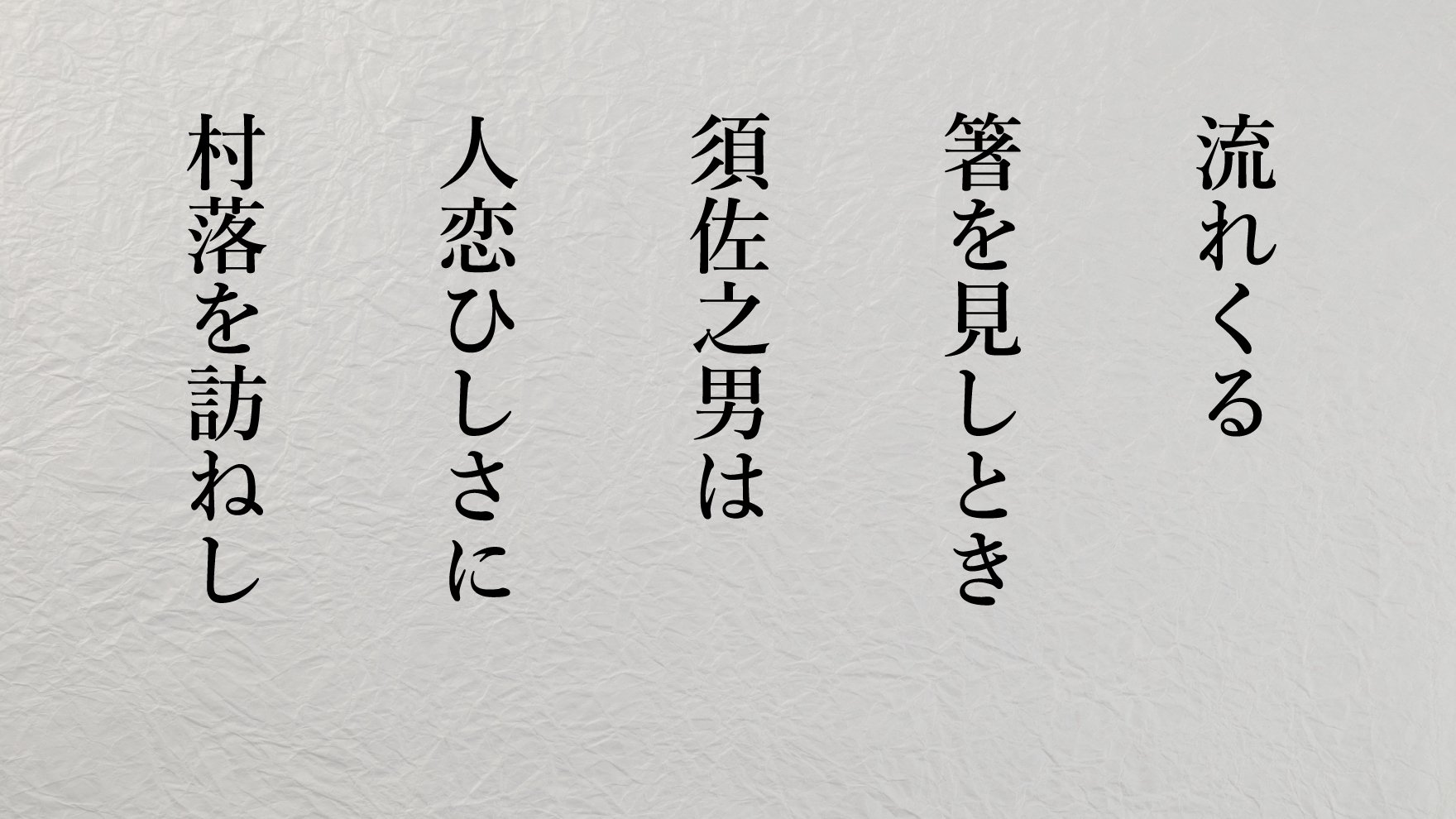
流れくる箸を見しとき須佐之男は
人恋ひしさに村落を訪ねし
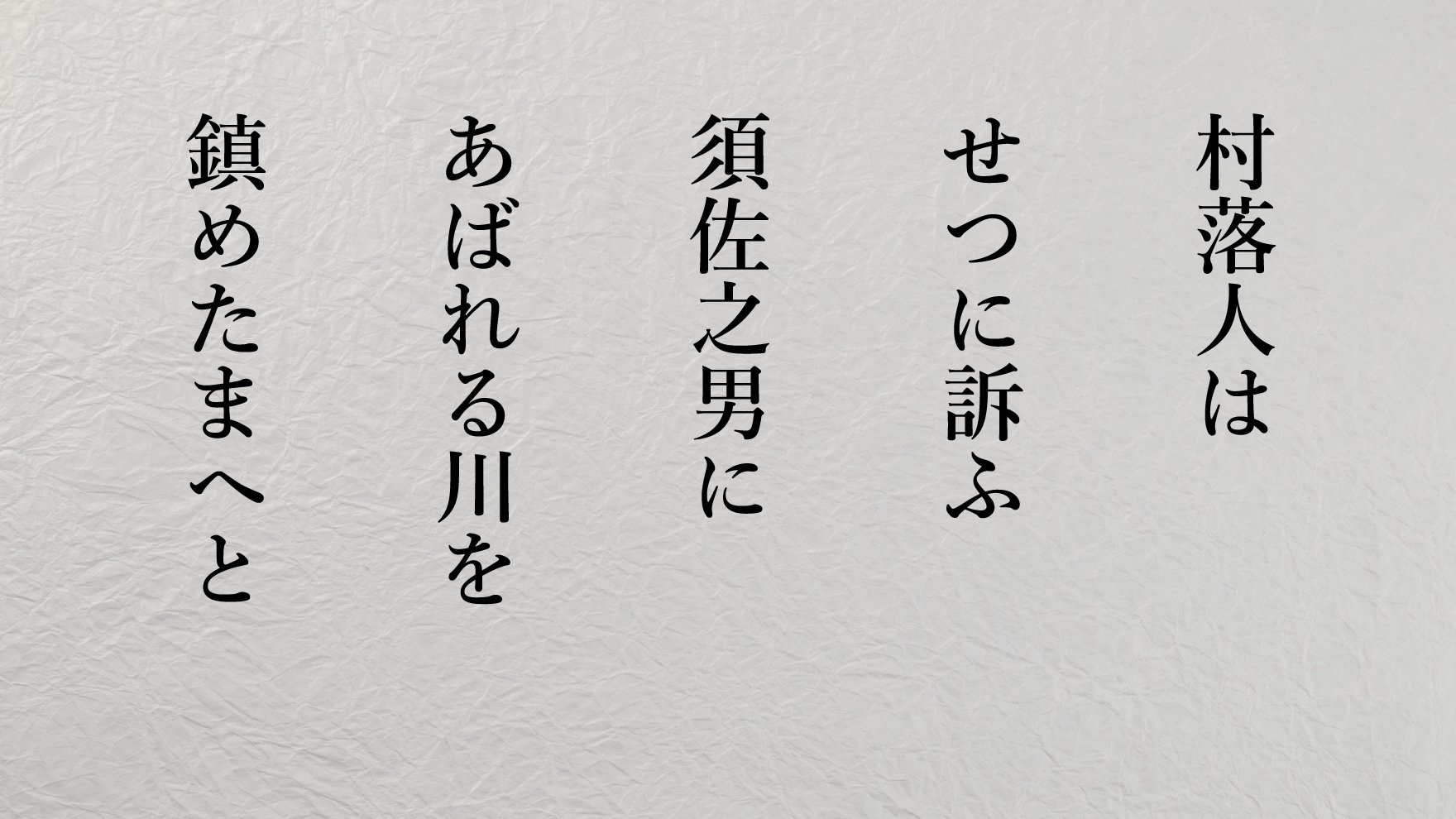
村落人はせつに訴ふ須佐之男に
あばれる川を鎮めたまへと

